1906年、アメリカ・東海岸のボストンにて産声をあげたニューバランス。
100年以上の歴史を誇る老舗メーカーながら、近年急激に売り上げを伸ばしている、2007年に15億ドルだった売り上げは毎年前年比10%増の伸びを記録。2018年度には45億ドルにまで拡大した。
その背景にあるのが、熱狂的なファンの存在だ。日本でも、2010年代に入ってブームが再燃。ファッション誌やSNSで数多く取り上げられ、新モデルは販売開始直後に売り切れてしまうものもある。なぜこの老舗ブランドは、人々を魅了し続けているのだろうか。
その謎を解くために、CX DIVE 2019 AKIでは『なぜニューバランスというブランドに惹かれるのか?』と題したセッションを開催。ヤプリ執行役員 CCOの金子洋平氏をモデレーターに、Moonshot代表取締役 CEOの菅原健一氏、インフォバーン ソリューション部門部門長/執行役員の羽村悠己氏、そしてNew Balance Japan DTC E-commerce部 Sr.Managerの牧嶋琢実氏を迎えた。
ニューバランスの「信者」を自称するほどの熱狂的ファンであるこの面々。はたして、彼らは何を語るのか——。
日本市場を牽引してきた、ファッション文脈での価値

早速、登壇者は自身にとってのニューバランスの魅力を語り始めた。セッション当日の4人の足元には、もちろんニューバランスを象徴する「N」のマークが輝く。20年以上に渡ってニューバランスを履き続けているという彼らの話は、まさに「ファン心理」の塊だ。
羽村氏「僕は他のブランドのスニーカーもたくさん購入していますが、その中で『いちばん買い続けている』のがニューバランスです。ニューバランスのスニーカーは、他のブランドとは異なり、型番が『996』『1300』といった数字表記、かつ、それらは数十年、基本的には変わっていません。ファンは各々好きな型番があり、こだわりがある。このラインナップも、熱狂させる要因かもしれませんね」
実際、モデレーターを務めた金子氏は990シリーズを愛用。「今日は990v5を履いてきましたが、その前も990v4(一つ前のモデル)を履いてましたね」と語った。

彼らがニューバランスと出会ったのは10代の頃。羽村氏、金子氏はいずれもファッションがきっかけだったと振り返る。
金子氏「僕はファッション誌を読んで育った世代です。雑誌に掲載されたニューバランスのかっこよさに惹かれたのが最初の出会いでしたね。それからは、グレーのニューバランスばかり履いています」
事実、ニューバランスの成長を語る上で「ファッション」の文脈は外せない。
ニューバランスにとって北米に続く2番目の市場である日本は、パフォーマンス(競技用)カテゴリよりも、ライフスタイルカテゴリの方が規模が大きい。ファッション文脈での注目が契機となり、ファンとなった人々が多いといえる。

ヤプリ執行役員 CCO金子洋平氏
「ニューバランスでないと」と思わせる、フィッティングへのこだわり
一方、中の人として登壇した牧嶋氏は、スポーツがきっかけでニューバランスと出会った。
同氏は学生時代、熱心にサッカーに取り組んでいたが、足に合うシューズがなく苦労していた。プレーしやすいシューズを探し回る中、その履き心地に魅了されたのが、他社にはないフィッティングの考え方を持つニューバランスだった。
牧嶋氏「私は足幅が広く、一般的なスポーツブランドの靴が合わず苦労していたんです。その悩みを地元のスポーツショップで相談したところ、勧めてもらったのがニューバランスでした。
ニューバランスは、扁平足向けの矯正靴メーカーとして創業した経緯もあり、他のブランドにはない“幅”のラインナップがあった。初めて足を入れたとき、今までにないフィット感に驚いたことをよく覚えています」

New Balance Japan DTC E-commerce部 Sr.Manager 牧嶋琢実氏
フィッティングは、ニューバランスを語る上で欠かせない要素のひとつだ。ファッションが入り口で興味をもった人も、愛用する理由に「履き心地」を挙げることは少なくない。
同社は、フィッティングに並々ならぬこだわりを持つ。足の長さだけではなく、甲の高低や幅の広狭を含めたサイズを展開。直営店では3Dスキャンを用いて足のサイズを正確に測定し、最適なサイズ提供に力を入れている。
Moonshotで企業やブランドの成長をアドバイスする菅原氏は、他のブランドにはないこの指標が、ニューバランスにとって大きな強みになっているとみる。
菅原氏「ニューバランスは、消費者に対して足の幅という指標を与えている。この独自指標は、ブランドを強くする戦略にもなるんです。『履き心地』を重視する人にとって、この指標を持つニューバランスは、唯一の選択肢になる。『他のブランドではなくニューバランスでなければならない』という意識が生み出されやすくなるんです」
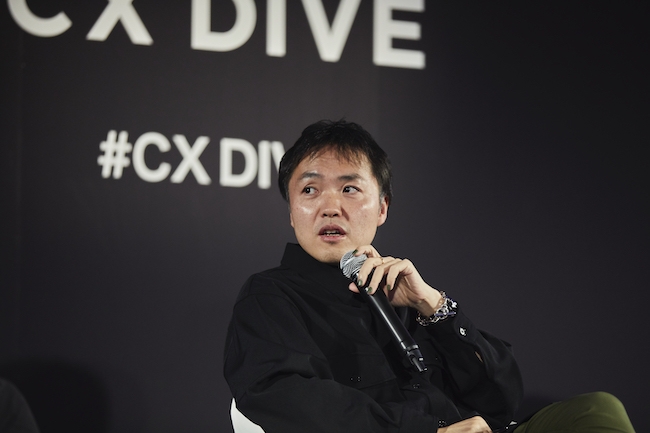
Moonshot代表取締役 CEO 菅原健一氏
フィッティングへのこだわりは、店舗での体験を重視する姿勢にも表れている。EC部門を統括する牧嶋氏は、「決してECだけを使ってほしいとは思わない。店舗に足を運び、良質な体験をしてほしい」と語る。
牧嶋氏「店舗には、ブランドの世界観の共有はもちろん、店舗でしかできない精度の高いフィッティング、という重要な役割があります。ブランドが大切にしているものを伝える上では、ECと店舗の双方の活用が欠かせません。
実際、今年からECと店舗の会員情報を統合し、一連の体験として設計できるように整備を進めています。我々としては、1足目は直営店で足のサイズを測り、自分の足にぴったりフィットするものを選んでほしい。その上で、各々に便利な方法でブランドと関係を築いていただきたいと考えています」
理想的なサイクルを生む、「ファーストシューズ」の評価
このフィッティングへのこだわりが評価されている例として、牧嶋氏は「ファーストシューズ」としてのシェアを挙げた。
牧嶋氏「ニューバランスは、ファーストシューズ、つまり子どもがはじめて履く靴としてのシェアが非常に大きいんです。靴のサイズに真剣に向き合っているブランドだからこそ、子どもの足を正しく成長させたいお母さんに選んでいただけているのだと思います」
このファーストシューズでの出会いは、ブランドとして、中長期に関係を築く土台になっている。

牧嶋氏「ファーストシューズでニューバランスを履いた子どもたちは、成長して他のブランドへ移ることもあります。ただ、ブランド自体の認知や関係性はどこかにあって、また戻ってくる方もいらっしゃる。最初に接点を持つことが、継続的な関係にも寄与していると感じています」
菅原氏は、この「入り口」と「継続」の設計を高く評価する。
菅原氏「ブランドビジネスにおいていちばん難しいのが、『卒業』されないことです。ブランドに『入学』し、トライアルを重ねるも、ロイヤルユーザーになる前に離脱してしまう顧客は少なくありません。
一方ニューバランスは、僕らが20年以上に渡って履き続けているように、ロイヤルユーザーがなかなか卒業しない。かつ、親から子へと受け継がれる入学がある。ニューバランスのファンづくりは、ブランドにとって理想的なサイクルではないでしょうか」
ブランドの「色」を伝える、適切なコミュニケーション
フィッティングへのこだわりを中心に、評価を高めてきたニューバランス。
彼らが継続的に関係を築くことができた理由は、商品の力だけではなく、あらゆる接点における“ニューバランスらしさ”をブレずに体現しているからでもある。セッション後半では、マーケティング・ブランディング領域のプロフェッショナルである面々が、同社のコミュニケーションのあり方にそのヒントがあると分析した。
オウンドメディアをはじめ、企業のプロモーションを手掛ける羽村氏。継続的な顧客との関係性が生まれる背景には、ニューバランスに一貫する「安心感」があるのではないか、と指摘する。

インフォバーン ソリューション部門部門長/執行役員 羽村悠己氏
羽村氏「ニューバランスは履き心地だけではなく、時代に左右されないブランドとしての安心感がありますよね。いつ出会ってもニューバランスらしさは変わっていないからこそ、少し間が空いたとしても安心して戻ってこれるのだと思います」
プロモーションからもそれが伝わる。他の大手スポーツブランドはプロモーションにアスリートやアーティストなど、引きの強いスターを起用することが多い。しかし、ニューバランスはそうした引力の強いプロモーションに積極的ではなく、より堅実な世界観の共有を大切にしている。
菅原氏「スターを起用するプロモーションは、消費者を刺激しやすく、即効性も高い。ただ、“人”に寄ってしまうので、世界観を伝えるには難易度が高くなります。
その点、ニューバランスはサッカー大会を主催するなど、草の根のコミュニケーションを大切にされている。世界観の共有をとても丁寧にしています。そうした堅実さが、『安心感』にもつながっているのではないでしょうか」

一貫した商品へのこだわり、そしてそれを伝えるブレないコミュニケーション。その両方にしっかりと注力するからこそ、ニューバランスの“らしさ”が適切に伝わり、ファンを獲得しているのではないか。
セッション最後、羽村氏はそのニューバランスのあり方を“軸”という言葉を用いて、以下のように表現した。
羽村氏「インターネットやSNSを通し、個人が摂取する情報が増えたことによって、ユーザーはさまざまな角度からブランドを検証できる時代になりました。企業がどんなに美辞麗句を用いても、消費者には『バレて』しまう。
だからこそ、ブランドは一時的、一面的に商品や顧客と向き合うのではなく、しっかりとした『軸』を持たなければならない。小手先ではなく、揺らがない軸のもとトータルのブランド体験を届けていくことこそが、ファンづくりにおいて必要なのではないでしょうか」
信者たちによる「ブランド愛」とその分析を追うことで、ニューバランスというブランドを取り巻く熱狂のつくり方が見えてきた。
特筆すべきは、登壇者4人の「好き」に溢れたディスカッションを聴くうちに、筆者も少なからずニューバランスを履いてみたくなったこと。
専門家の視点から冷静に分析をされても、心には響かなかっただろう。「信者」を自称する登壇者がそれぞれの熱狂をもとに持論を展開していったからこそ、そんな感情が聴衆に湧き起こったのだ。誰かの熱狂がファンを増やすことを、図らずも体験した形となった。

文/萩原 雄太 編集/小山和之 撮影/佐坂和也




