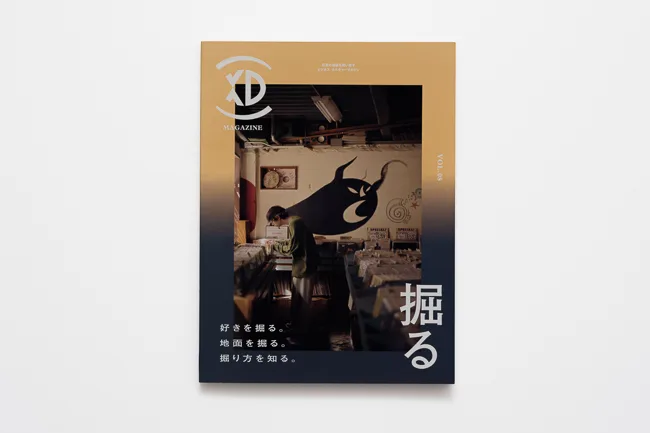ツルハシを片手にあくせくと、色付けされた正方形のブロックを集めていく。そのゲームをプレイしている画面を横から見ても、一体どんなゲームなのか想像がつきづらい。しかし、プレイヤーの顔を覗き込んでみれば、どこか力強い魅力に突き動かされていることを確信する─そんな静かな熱狂を生んでいるタイトルこそ『マインクラフト』だ。“掘る”ゲームの世界的な代表作ともいえるこの作品は、なぜこれほどまでに支持されているのだろうか。
本稿では、これまでにビデオゲームに関する論考を数多く発表し、現在はインディーゲーム存続のためのウェブメディア「Indie Intelligence Network」で共同編集長も務めるJiniさんにその現象を紐解いてもらった。
(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)

Jini
作家、編集者。2019年に有料独立型のウェブメディア「ゲームゼミ」をスタートし、2,000人以上が参加するコミュニティに。2024年には世界中のインディーゲームにまつわる情報を共有するハブとなる「Indie Intelligence Network」の立ち上げに携わり、共同編集長へ。その他にもラジオ、テレビ、書籍と幅広くゲームの魅力を伝えるべく活動中。
X:@J1N1_R

画面中央右側のツルハシを片手にしたキャラクターは「Player」─文字通りプレイヤーが操作するキャラクター。半袖Tシャツにジーンズのようなこの初期設定のスキンは「Steve」と呼ばれ、同作品の象徴としても愛され続けている。その隣で剣を構えるキャラクターは「Alex」。今日に至るまで、いずれのキャラクターも性別は明確にされておらず、その解釈はプレイヤーに委ねられている。
© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
世界で最も売れたゲームですべきことはただ「掘る」こと
皆さんは世界で最も売れたゲームのタイトルを知っているだろうか? 『スーパーマリオブラザーズ』? 『ファイナルファンタジー』? どれも確かに多く売れたゲームだが、こうしたゲームを差し置いて、世界で最も売れたゲームが『マインクラフト』だ。その数なんと約3億本。大ヒットと呼ばれるゲームでも1,000万本、コロナ禍において大流行した『あつまれ どうぶつの森』でさえ4,500万本と考えると、3億本売れた『マインクラフト』がいかに規格外のゲームなのかは察するにあまりある。(なお、『テトリス』はそれ以上に売れたという説もある)

実際のプレイ画面。まるで自分がその世界の中にいるような、主に一人称視点で操作する。また操作も、ジャンプ、ダッシュ、手に持っているものを使う……とシンプルなため、老若男女、また未就学児でも操作を覚えやすいことも特徴のひとつだ。
Googleで「Minecraft」と検索してみると、作品に触れたことがなくてもすぐに同作品のプレイ体験が味わえるインタラクティブな仕掛けと出合える。
© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
さてそんな、『マインクラフト』はどんなゲームなのだろうか。YouTubeなどの動画配信サイトで有名なインフルエンサーがよくプレイしているので、名前ぐらいは知っているという人は多いかもしれない。
『マインクラフト』は「マイン=掘る」+「クラフト=つくる」というタイトルに忠実なゲーム内容となっていて、自動生成される広大な仮想世界の中で土や石などの資源を掘り、それらを組み合わせて道具をつくったり、あるいはブロックとして重ねて家を建てたりする。あえていうなら「ゲームならではの積み木」といえるようなもので、3億本も売れたのは、全世界で遊ばれる「積み木」という遊びをベースにしているからだ。
驚くべきことに、この世界で最も売れた『マインクラフト』を開発したのは、たったひとりのスウェーデン人だった。その名はマルクス・ペルソン。彼は「ノッチ」というハンドルネームでもよく知られており、もともと趣味でゲームをつくり、自らのホームページでそれを販売していたところ、偶然にも世界に注目された一本が『マインクラフト』だった。ペルソンのように企業に所属せずひとりでゲームをつくり、それを販売するというのは当初珍しく、そのゲームは口コミで広がっていった。

© 2025 Mojang AB. All Rights Reserved. Minecraft, the Minecraft logo and the Mojang Studios logo are trademarks of the Microsoft group of companies.
個人の開発者が独力でつくったゲームのため─今では、インディーゲーム文化は認知されているが─公開当初の『マインクラフト』は決して完成度が高くなかった。アイテムや敵キャラクターはほとんど存在せず、ペルソン自身も「α版」として公開していた。しかも、ゲームを知ってもらうための広告すら打ち出すことができず、ペルソン個人が運営するサイトで細々と販売するのにとどまっていた。
しかし、この『マインクラフト』の可能性を見出したのが、世界中のコアなゲームファンである。『マインクラフト』のユニークなゲームデザインに魅了された彼ら彼女らは、広告の出せないペルソンに代わって掲示板やソーシャルメディアで『マインクラフト』の存在を口コミで広めた。さらにゲームの完成度に対しても、ただ不満を並べるのではなく、むしろ次々に改善案や問題点を語り合い、ペルソンが日々そうした意見を汲み取ってゲームをアップデートしていくことで、現在の『マインクラフト』の原型がかたちづくられていった。そしてぺルソンが『マインクラフト』から離れた後も、Mojang Studios がその営みを引き継いでいった。
言い換えれば、後に世界で最も売れるゲームとなる『マインクラフト』を「発掘」したのは、世界中にいるコアなゲームファンたちだった。彼ら彼女らが日夜、興味深いゲームを掘り出し、さらにそのゲームの魅力や欠点さえも掘ることによって、広告にも開発にも十分な予算を用意できない個人クリエイターのゲームが、世界で評価されるに至った。その点では、『マインクラフト』の功労者は当時ゲームを掘り続けていたプレイヤーらといえるかもしれない。
冒頭で『マインクラフト』は「積み木」であると論じたが、そもそも「積み木」と聞いて心の底から遊びたいと思う人は、あまり多くないだろう。なぜなら、積み木は無尽蔵の想像力を求める遊び。彩色されたさまざまな立方体を積み上げ、そこになんらかの価値や意味を見出そうとする、とても高カロリーな遊びだ。「積み木」と聞くと、どうしても幼稚で退屈な遊びにも聞こえてしまうが、その本質はむしろ想像力の枯渇した大人には楽しめない「難しさ」にある。
では『マインクラフト』は一体どのようにして、想像力の足りない大人でも楽しめるゲームになったのか。ここで重要なのが、まず自分の手で「積むための木」を手に入れる、というサイクルである。『マインクラフト』は、その気になれば巨大な城もつくれるバーチャルな積み木だ。しかし、その城を構成するための「木」は、一般的な積み木のように最初から用意されているわけではない。木材や石材、レンガまで、あらゆる建材はプレイヤーが自ら土を掘り、それらからつくり出す必要がある。(サバイバルモードの場合)
例えば、私が初めて『マインクラフト』をプレイしたとき、美しく切り立った崖を発見した。すると、私はあの崖にログハウスを建て、さらにウッドデッキを展望台のようにしたら、きっと素晴らしい眺めになるに違いないと考えた─このように想像が膨らむと、もう夢中になって周囲の木材をかき集め、崖の上へと運ばずにいられない。このように『マインクラフト』は常に「クラフト」するアイデアが生まれる仕組みが存在するために、「大人も楽しめる、ゲームならではの積み木」となっている。

© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
もうひとつ、『マインクラフト』がクレバーなのは「生き残る」ためのルールが用意されていることだ。『マインクラフト』の世界では、夜になると恐ろしいモンスターが現れるし、主人公は負傷すると食事で回復する必要が生まれる。また、地下にはダンジョンと呼ばれる危険なエリアも広がっており、貴重なアイテムや建材が眠っている。一見、草木と動物であふれた牧歌的な世界だが、いざゲームを「掘って」みると殺伐とした世界が広がっている。
しかし、この殺伐さこそ「積み木」の大きなモチベーションになっている。例えば、最初に私がプレイしたとき、恐ろしいゾンビやスケルトンといったモンスターに襲われ、思わず走って逃げ出した。しかし、彼らは夜の間どこまでも私を追撃し、ついに倒されてしまう。一体どのようにしてこの困難に対応するべきか。そうだ。今しがた手に入れた木材を使ってシェルターをつくろう。そうしてシェルターをつくると、次第にせっかくだから作業台を置こうとか、窓を開けて景色を眺められるようにしようとか、屋根をつけて見栄えをよくしよう……なんて想像が浮かぶ。このように、モンスターという脅威から身を守るシェルターが、気づけば自発的な「積み木」へとつながっているのだ。
このように『マインクラフト』は一見すると、とてもバリエーションが豊かな積み木でしかないのだが、そこにはゲームならではの工夫に満ちている。特に、生存という目的のために世界を「掘り」、それによってつくり上げた建物を改築していくうちに、次々に「積み木」のためのアイデアが浮かんでいくというサイクルは、まさにゲームにしかできない「積み木」体験といえるだろう。

© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
さらに掘り下げられる『マインクラフト』の世界
かくして大人気ゲームとなった『マインクラフト』だが、リリースから15年以上経過した今もこのゲームはユーザーの手によって掘り下げられ続けている。
まず、このゲーム自体が発売から現在に至るまで、一貫してアップデートを続けてきたことにより、もはやそのボリュームとポテンシャルはとても「掘り下げきれない」ほど肥大化した。少し世界を歩くだけで次々に未知のバイオーム(地形)と出合い、それぞれに固有の動植物で構成された生態系や建材となる「積み木」が用意されている。少し危険な地に赴けば、危険な強敵や謎に満ちた遺構が広がっており、そこから持ち帰った財宝を組み合わせれば、またしても新たなアイテムをつくれる。全てを遊びつくそうとすれば、100時間遊んでも足りないほどの世界が今も拡がり続けているのだ。
また『マインクラフト』の楽しみ方は、何も自分で直接遊ぶだけではない。YouTubeのような動画配信サイトでは『マインクラフト』が今なお最も人気のゲームとして、数々のインフルエンサーによってプレイされている。そもそも『マインクラフト』はろくに広告も出せない頃、人々の口コミによって広がっていった作品。特に『マインクラフト』は自分で世界を掘り、そこから建物をつくっていく独創性から、「こんなすごい建物をつくった」「こんな新しい発見をした」という趣旨の投稿が今も途絶えない。
中には『マインクラフト』がマルチプレイ、つまり複数人のプレイヤーで同時に遊べる点に着目し、数十人で現実に存在する街を再現するプロジェクトを試みたり、自分たちが『マインクラフト』世界の住人になりきって(ロールプレイをして)遊ぶ動画も存在する。このようにみんなで集まり、いろいろな遊び方を考えられるからこそ『マインクラフト』は今も人気を博しているのだろう。

© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corporation.
さらに『マインクラフト』を教育に用いる試みも増えている。そもそも、本稿でもこのゲームを「積み木」に例えたように、プレイヤーの想像力をどこまでも再現できるのが『マインクラフト』だ。開発側もこうした用途を見越してか「教育版マインクラフト」を通常のものとは別に販売しており、文部科学省はこの「教育版マインクラフト」を教材として認可している。こちらは全国の小中学校で使用実績がある他、学校の入試に『マインクラフト』が用いられたり、『マインクラフト』でつくった建築物を競ったりするコンテストまで開催されている。
また直近でファンを驚かせたニュースといえば、2025年に公開を予定している『マインクラフト/ザ・ムービー』だろう。さまざまな登場人物が『マインクラフト』の世界へ飛び込んでしまう、という内容の映画なようだが、個人的に興味深い点はこの「プレイヤーの視点で映画をつくる」という点だ。
そもそも、『マインクラフト』には具体的なストーリーは何ひとつなく、一貫してプレイヤーは主人公そのものであり、この世界で何をするのも自由だ。だからこそ、『マインクラフト』でプレイヤーが味わった喜怒哀楽は全て、架空の主人公ではなく100%自分自身のものとして記憶されている。それこそが『マインクラフト』の醍醐味なわけで、映画独自の設定はこの点を考慮しているのではないかと、私は推察している。

© 2025 Mojang AB. TM Microsoft Corp.
今や、『マインクラフト』は3億本も売れた。言い換えれば、『マインクラフト』で世界を堀り、つくり、学んできた子どもたちが、世界に3億人近くいるということだ。そんな彼ら彼女らは、5年後、10年後には世界を支える逸材となっている。その点で、あらゆる想像力を掻き立てて「掘る」ことを促してきた『マインクラフト』という共通体験を持つ世界の子どもたちは、一体どのように心を通じ合わせるのか。実のところ、『マインクラフト』で最も注目するべき点とは、ゲームそのものではなく、ゲームを遊んだ子どもたちなのではないかと私は考えている。
編集/梶谷勇介・編集部
――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。