「すみません。昨日は北京で、過去10年で最悪規模の黄砂が発生して。今朝は一転、青空が広がったので、その続報を早いうちに公開しようと思ったんです」。北京、福岡、そして東京の3カ所をつないだオンライン取材の冒頭。突然かかってきた電話に応じた様子に、情報の即時性と正確性を重視する報道機関としての矜持を見るとともに、これから“取材のプロ”に取材するのだと背筋が伸びた。
インターネットによって誰もが容易に情報を得られ、また発信できるようにもなった現代社会。あふれる情報のなかで、その立ち位置が問われているのが「マスメディア」だ。「自分たちにしかできない役割は何か」。マスコミ各社の模索が続くなか、読者の困りごとに応える“基本”に、あえて立ち返った媒体があった——九州・福岡を拠点とするブロック紙、西日本新聞だ。

『あなたの特命取材班』公式サイト
同社が立ち上げた『あなたの特命取材班』(以下、あな特)は、読者の声を起点とし、新聞社が独自の取材で問題を明らかにしていく「オンデマンド調査報道」。地域の疑問を、市民と一緒に解消していく仕組みだ。
あな特は実際、人々の暮らしにどのような影響を与えているのか。「地方紙の強みを生かす」取り組みとして、メディアと人の関係をどう変えたのか。
立ち上げからあな特に携わる西日本新聞社の坂本信博氏、福間慎一氏の二人に話を聞いた。
「読者が知りたい」ニュースから離れてしまっていた
あな特がスタートしたのは、2018年1月。読者は同社の公式LINEアカウントをフォロー(「あな特通信員」に登録)するか、サイトのフォームを通じて、西日本新聞に調査依頼や困りごとの相談ができる。
記者はそれらの疑問や要望をもとに取材や調査を行う。作成された記事は紙面に掲載されるだけでなく、Webサイト『西日本新聞me』のページからも閲覧が可能だ。(一部、有料記事あり)
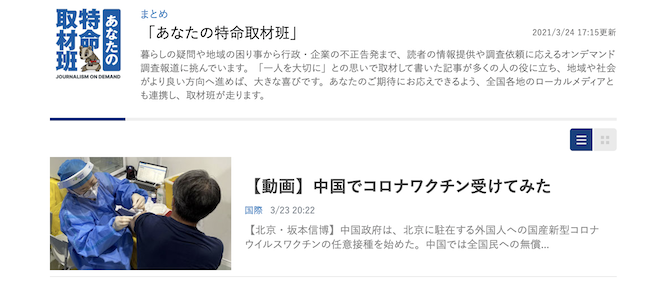
「あなたの特命取材班」(西日本新聞meより)
地域や社会がより良い方向へ進むきっかけになるのであれば、取り扱うテーマはジャンルを問わない。「学校で日焼け止めを塗らせてもらえない」という中学生の声をもとに、医師や教育委員会、文部科学省に取材しその正当性を投げかけ、校則変更につながったこともあれば、郵便局員の内部告発から『かんぽ』の不適切営業の問題に迫った結果、全国紙やテレビ局など報道各社も追随し、郵政グループの3社のトップが辞任する事態に至ったこともある。
そんなあな特は、名前こそ“取材班”とついてはいるものの、社内に独立した班を持たない。事務局運営を担う福間氏は、「ある意味で“すべての記者が取材班”です」と表現する。
福間氏「編集局の記者が、あな特に寄せられる情報に常時アクセスできるようにしています。そのなかで気になる情報があれば、『私が取材します』と社内に宣言できる。いわば手挙げ方式です。
担当したものについては、各記者がそれぞれに相談者とのやり取りや、裏取りなどの取材を進めていきます。事務局はアンケートを取りまとめたり、寄せられている情報の整理をしたり、サポート機能を担いながら、もちろん取材もします」

西日本新聞社 クロスメディア報道部 デスク兼記者 福間慎一氏。『あな特』を立ち上げた記者の一人
あな特は、最初から今のように全社的な取り組みを行なっていたわけではない。もともと「社会部の年次企画」としてスタートし、試験的なプロジェクトの側面もあった。相談がどれだけ来るかは未知数で、全く依頼されない可能性すらゼロではなかった。
だが、発起人である坂本氏は、当初から強い思いを抱いてこの企画に携わっていたと話す。
坂本氏「私が入社した1999年当時、西日本新聞は90万近い発行部数でした。けれどもそれから20年近くが経ち、部数は50万部を切るまでに減少。読者の高齢化も進んでいったんです。
マスメディアそのものへの信用も低下するなかで、『地方紙は“オワコン”』と思われているのではないか、と感じていました。将来を悲観した優秀な記者も次々と全国紙など他のメディアに転職していき、何とかしなければと思っていたんです」

西日本新聞社 中国総局長 坂本信博氏。『あな特』立ち上げ時は、社会部デスク兼遊軍キャップを務めた
地方紙がそうした状況に追い込まれた背景を、坂本氏は「読者が知りたい」ニュースと、実際の報道との乖離にあると感じていた。「市民が知るべき」「市民に知らせたい」と思って取材することも大切だが、そうした報道の主語は読者ではなく、あくまで記者や新聞社だった。
後者への偏りを見直し、前者のニュースを増やす必要がある。読者との距離を縮める方法を探るなかで、坂本氏らが「望み」を託したのがあな特だった。
『社会部110番』から『あな特』への系譜
実はあな特は、かつて西日本新聞にあった企画『社会部110番』が元になっている。坂本氏が入社した当時、社会部の記者が専用回線から読者の相談を受け付けていた。
坂本氏「社会部110番は、すごくやりがいのある仕事だと私自身は思っていました。ただ、同時に負担の大きさも感じていましたね。1回電話を取ると要点を把握するのに30分はかかり、記事にできそうな話は30本取って1本あるかどうか。
いつしか企画そのものがなくなり、読者の悩み相談は、忙しい記者に代わって『お客さまセンター』が購読などの相談と合わせて担うようになったんです。ただ、そうすると今度は記者と読者が直接話す機会が減っていきます。
自分の記事が人々に刺さっているのかどんどん分からなくなる不安もあって、何とか社会部110番を復活させたいと考えていました」
ただ、以前の電話を使った仕組みは有効とは言い難い。そもそも電話相談は、かかる労力が大きいことに加えて、情報共有にも課題があると福間氏らは考えていた。
福間氏「電話の場合、取った記者にその話が刺さらなかったら、そこから記事になることはありません。さらに、その記者がちょっと関心を抱いたとしても、その先のデスクが『おもしろくない』と判断すれば、やはり取材にはつながりません。
でも、記者は本来それぞれが個性を持っています。ある記者が興味を持たなくても、他の記者のアンテナに刺さったり、また別の誰かが関連する知識を持っていたりするかもしれません。寄せられた情報を広く共有する手段が必要だと感じていました」
読者の声を拾うために、彼らが目をつけたのがSNSだった。手始めにハッシュタグを使った企画として、2017年9月の衆議院解散後、選挙や投票行動について『#選挙行きま』キャンペーンを展開。紙面や公式アカウントを通じてTwitterへの投稿を呼びかけるとともに、投稿者まで記者が会いに行く実地取材も行なった。
坂本氏「全く反応がなかったらどうしよう……と思っていたんですが、最後はさばききれないぐらい投稿が来て、大きな手応えを感じました。
また、この企画を通じて『ネットの声も、リアルに生きている人が発信しているんだ』と実感したのも大切な気付きでした。それまではどこか、『ネットは根も葉もない話ばかり』などの思い込みが我々にはあったんです。でも、こちらが勝手に線を引かなければ、十分に報道と生かせるんだと考えるようになりました」

『#選挙行きま』の報道記事(西日本新聞meより)
そこから、あな特の仕組みを構築するプロジェクトが加速した。社内の記者有志に呼びかけるほか、同社のグループ会社でデジタル部門を担う西日本新聞メディアラボを初期から巻き込み、企画を具現化していった。
坂本氏「コンセプト設計からメディアラボと組んだことは、重要なポイントでした。それまでは新聞社が単独で進めた企画について、『こんなサイトをつくってください』などと依頼するような関係だったんですが、今回は『どうすれば読者とつながれるか』『調査報道で社会課題の解決に貢献できるか』といった点を最初から一緒に考えていきました。
あな特におけるLINEの活用は、まさにメディアラボから提案されたものです。スマホ1台に対しアカウントが1つ、しかも家族や友人と使うツールなので、なりすましや煽り目的が少ないのでは、と。さまざまな意見を交わしながら、LINEアカウントの友だち登録者を“通信員”と位置付けること、読者と一緒に報道をつくっていくことを強く打ち出していきました」
読者は大切な「パートナー」
そうしてスタートしたあな特には、想像以上の反応が返ってきた。「見向きもされないかも」といった当初の不安をよそに、問い合わせ件数は着実に増え、毎日10〜20件ほど依頼が届くようになっていく。
坂本氏「困っているのに相談できない、相談したくてもするところのない人が、世の中にこんなにも多くいるんだと痛感しました。
例えば、ある施設に入所する方のご家族から、『夏なのに、夜にエアコンが切られるので死にそうだ』と連絡をいただいたんです。『そりゃしかたないやろ』といった反応をする記者もいたんですが、気になって調べてみると、その年は1日を除いてすべて熱帯夜で、エアコンなしの生活がいかに苦しいかがわかってきた。この記事は1面に載り、施設には行政の指導が入りました」

施設における暑さ対策を問う報道記事(西日本新聞meより)
もちろん「本人が施設や行政に直接相談すればいい」という考え方もある。ただ、日々を過ごす施設に利用者や家族が強く異議を唱えることには、「印象が悪くならないか」などの心配がつきまとう。行政に言うとしても、どの窓口に行けばいいか迷ったり、自治体ごとの温度差が気になったりする人もいるだろう。
そうした市民にとって、頼れる“駆け込み寺”の一つが、実は新聞社だった。
坂本氏「あな特では、取材手法を可視化することを意識しています。誰にどのように聞いていったのか、過程を記事に載せるわけです。すると読者が、『そうやって調べてくれるなら』と自分の困りごとを打ち明けてくれます。
また、“グレーゾーン”に切り込むことも大切にしています。白黒はっきりと結論が出なかったり、一見取り上げるほど大きな問題とは思えなかったりするようなものでも、一人の困りごとが他の人々にも共通しそうだと感じたら、新聞社の取材力を使う。実際に問題を深掘りしていった結果、法律の不備が見つかり、時代を反映した新たな問題提起へと発展する場合もあります」
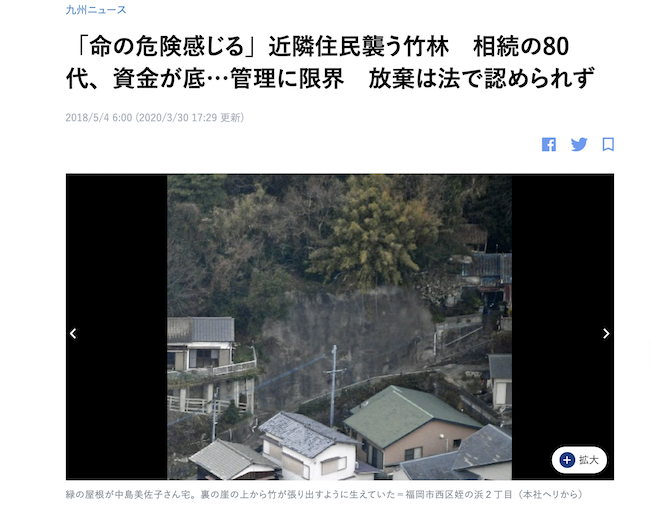
竹林の管理問題を通じ、民法の不備を指摘した2018年の報道記事。これがきっかけとなり、2019年に法制審議会は土地所有権放棄制度を整備する方針を表明、2021年の法案成立を目指している(西日本新聞meより)
こうした報道を積み重ねることで、新聞社と読者の関係性も大きく変わった。記者から見れば、読者は取材力を生かすべき場所を教えてくれる、欠かせないパートナーとして映る。集まる依頼は具体性が高く、半数以上は「取材すれば記事になりそうな問題」だという。
福間氏「相談を電話の音声からテキストに、つまりあらかじめ言語化と情報の整理がなされる伝達手段にしたことが、結果的に精度を上げているのかなとも感じます。
また、クローズドな相談環境を用意したことも良かったですね。誰かの目に触れる話ではないため、個人的な悩みも書きやすいようです。小さなことであっても『これは新聞社にちゃんと相談してみよう』と、真剣に検討いただいたものばかりだという実感を持っています」

取材は西日本新聞社本社のある福岡と中国総局のある北京とをZoomでつないで行なった。
坂本氏「読者から見た西日本新聞も、少しずつ信頼できる存在になってきているのかなと感じます。実は最近、妻が営んでいる店舗で、お客さま同士が困りごとを相談していたらしいんです。そのとき、会話のなかで『じゃあ、あな特に相談してみたら?』という言葉が出てきたらしくて。
その方はもちろん、店の関係者に西日本新聞社の記者がいるなんてことは知りません。ごく自然に、頼れる存在としてあな特の名前が挙がったんですね。そうやって市民の方々に定着し始めていることは、私たちにとってもすごくうれしいですし、大きなモチベーションになっています」
地方紙はむしろ「各地域における最強のメディア」
あな特によって、西日本新聞全体の姿勢にも変化が表れ始めている。生活者の相談の背景に「社会や地域全体に通じる課題」が垣間見えれば、最初から記事として大きく取り上げるようになった。
最近だと、コロナ禍での子どもの健康と校則を取り上げた事例がある。常時換気が奨励される一方で、「防寒着を着てはいけない」というルールに未だ縛られているとの指摘が、秋の終わりに数件続いた。同社は文部科学省や自治体、専門家を取材し、学校一律の服装規定のあり方を問い直す記事を作成。1面トップに掲載され、ネットニュースでもSNSなどで広く話題となった。
坂本氏「従来の新聞社の考え方では、暮らしに関わるこうした記事が、朝刊の1面トップに来ることはまずありませんでした。できるようになったのは、読者から寄せられる課題の数々に対して、新聞社にしかできないことがあると気付けたからです。防寒着の記事も、『自分たちこそが報じるべきだ』という自信の表れの一つと言えるかもしれません」
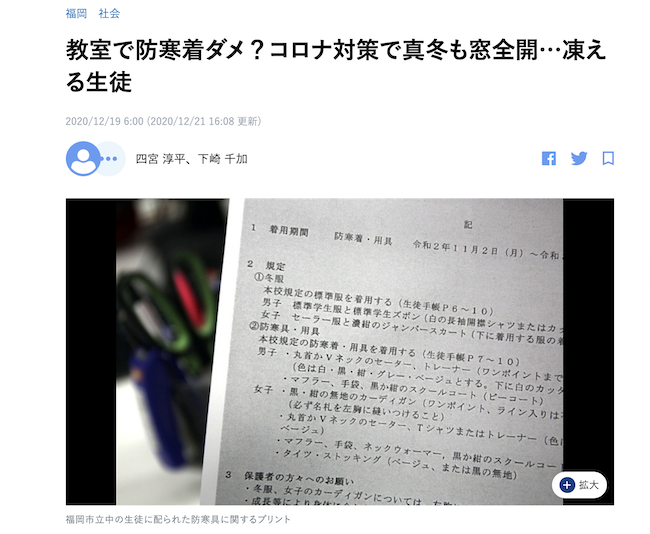
コロナ禍における校則の問題を問い直した報道記事(西日本新聞meより)
こうした考えに福間氏も同意する。ヤフーへの出向経験もある同氏は、よく言われる“読者離れ”という言葉に対し「離れていったのは新聞社のほうではないか?」と疑問を抱いていた。
福間氏「ネットニュースの現場に一度身を置くと、従来の視点で『これが大事だ』と言ってきた報道の多くが、ユーザーに届いていないことを数字で突きつけられます。例えば、すでに内容の固まっていた法案を『きょう成立』と報じたところで、読者は見向きもしてくれない。
かと言って、芸能やスポーツのようなニュースばかりでは報道機関の役割を果たせません。合間を埋めるものはないかと悩んでいましたが、『多くの読者にとっての疑問や困りごと』に重点を置いた報道こそが一つの答えなんだと、あな特を通じて少しずつ見えてきました」
記事の価値判断を大きく読者の側へ委ねたことは、結果的に社会における新聞社の存在感を高めることにもなったという。西日本新聞が取材に行くと、相手から「もしかして、あな特ですか?」という言葉が出るようになった。
坂本氏はそれを「決して私たちが偉くなったわけではない」と前置きしたうえで、地域の新聞社が有権者や市民、消費者の存在とともにいることの重要性を認識したと語る。
坂本氏「地域に根ざした報道から、行政が動いたり企業が変わったりする瞬間をはっきり感じるようになり、ローカルメディアとしての自信も少しずつ取り戻せているように感じます。
全国紙の記者さんからも、『地方紙のほうがおもしろいことができるんじゃないか?』と言われることが増えてきましたね。社会に役立つ余地がまだまだあると分かり、記者の離職も減ってきました」
福間氏「それぞれの地域の困りごとに、熱意を持って応えていく。これは多くの地方紙の記者が、本来やりたかったことでもあります。
そして実際、あな特のようなオンデマンド報道は、私たちにしかできないことかもしれないと感じています。なぜなら、ほとんどの都道府県内において、もっとも多く記者が所属しているメディアが地方紙だからです。
『地方紙は弱い、古い』と感じる方もまだまだいらっしゃるとは思います。でも、私たちはむしろ『地方紙こそが各エリアにおける最強のメディア』ではないかと考えている。そこの要素を今後さらに突き詰めたいと思っています」
仲間と一緒に「暮らしを良くする」
あな特から見えてきた、ローカルメディアとしての強みと存在意義。これを拡大させるべく、西日本新聞は2018年夏から新たな取り組みを進めている。
あな特の仕組みをベースに、各エリアの地方紙と読者からの情報をリアルタイムで共有したり、互いに記事を転載したりできる『JOD(ジャーナリズム・オン・デマンド)パートナーシップ』だ。

JODパートナーの一覧(『あな特』公式サイトより)
JODのパートナー同士が手を組み、時には一緒に取材を進めることもある。ラグビーW杯の商標を巡る問題では、北海道新聞の報道を受け岩手日報が、その報道を受けさらに西日本新聞が、リレーのように取材をつないだ記事も公開された。
こうした取り組みの背景には、「自分たちが抱いていた課題感は、他の地方紙にも通ずるのではないか」という仮説に加え、坂本氏や福間氏らが「1社だけでのオンデマンド調査報道には限界がある」と感じていたことがある。実際、ネットを通じた依頼は西日本新聞の拠点となる九州を離れ、全国から寄せられるようになっていた。
坂本氏「あな特で一番やってはいけないのは、途中で止めることだと考えていました。『課題を解決します』と言っておきながら、手が足りなくなって放置したり、楽して特ダネを集める窓口のように、新聞社にとって都合のいいネタだけを選ぶようになったりしたら、せっかく取り戻した読者の信頼を失ってしまう。
すでに西日本新聞としては『あな特をずっと続けていく』という方針を編集局全体で共有していますが、現状はすべての相談にお応えしきれていないのも事実です。自分たちの手に負えないテーマに関しては各地の記者さんと一緒に取り組むことで、より多くの課題を解決していけたらと考えています」
また、“記事化”にこだわらない解決手法も模索している。西日本新聞では2021年2月にあな特の記事ページをリニューアルし、寄せられた投稿のうち、許可が得られたものを匿名化して公開するようにした。

「あなたの特命取材班」調査依頼(西日本新聞meより)
福間氏「寄せられる意見のなかには、すぐには取材が難しいテーマであっても、貴重な気付きや知見が含まれているものがたくさんあります。それに対してコメントをつけられるようにしているので、新たな発見が加わり、記事化できるものがでてくるかもしれない。あるいは、サイト内のやり取りのなかで解決まで至るケースもあるかもしれません。
『新聞記者の仕事=紙面に記事を載せる』といった概念にこだわらず、柔軟なアウトプットをたくさんつくっていくことが、私たちに必要な姿勢ではないかと考えています」
こうした施策が打てるのは、あな特が当初から依頼者を“通信員”――取材をするための大切なパートナーとして関係を構築してきたからでもある。ただの情報提供者ではなく、ともに社会課題を解決する仲間であるという意識は、読者の側にも根付きつつあった。
坂本氏「以前に一度、アンケートで『あな特通信員でいてくださる理由は何ですか?』と聞いたことがあります。困ったときに相談したいから、という声ももちろん多かったんですが、私が印象的だったのは『通信員になることで、社会に参加していると思える』という方がとても多かったこと。
一人ひとりが社会とつながる意味で、あえて通信員になってくださっている。私たちはそのことをきちんと受け止めて、自分たちのあり方を探っていかなくてはなりません」
あな特が切り開いた新しいメディアの姿勢が、関わる人々をつなぎあわせ、世の課題を一つひとつ解きほぐしていく。坂本氏の発言を受けた福間氏も、さらなる展開と「目指すゴール」への決意を言葉にしてくれた。
福間氏「西日本新聞にとっては、あな特を継続させることがとても大事だと考えています。その過程で、新聞社に限らずメディア同士が連携することもあるかもしれませんし、あるいは今の通信員の方々から、さらにコアな通信員が生まれてくるかもしれません。
しかし同時に、続けることそのものは決して“目的”ではないことも、強く意識する必要があります。あな特はあくまで、“手段”なんですね。
大切なのは、あな特を続けることによって、地域の暮らしがより良くなること。そこに貢献できる新聞であることを、これからも目指していきたいと考えています」
執筆/佐々木将史 編集/大矢幸世




