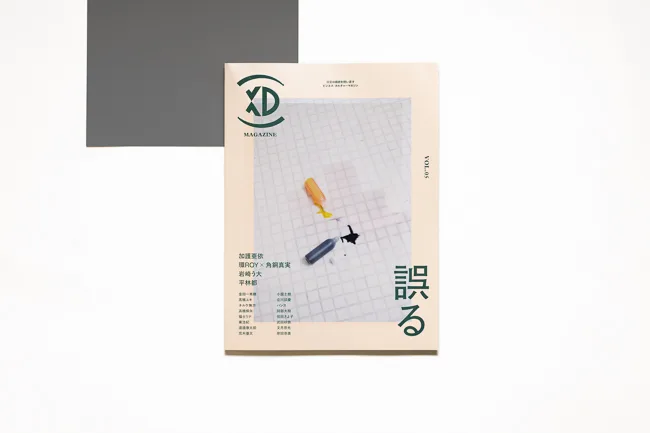ビジネスの打ち合わせや採用面接、冠婚葬祭。様々な場面で「マナー」はあるものだ。するとそこに、メディアでもよく見かける「鬼のマナー講師」がいる。激しい関西弁で社員をどなりつけるその姿は、一見すると社会規範の堅苦しさを象徴するかのようだ。しかしその多彩な横顔を見ていると、どこか甘んじてそんな役割を引き受けているようにも感じられる。そもそも、数々の企業で多大な実績を積み重ねている人物でもある。その秘訣は、なんなのだろう。それにマナーって、誤りから身を守る手段なのではないだろうか? 渋谷の一角でお話を伺った。
(この記事は2022年8月に発行された『XD MAGAZINE VOL.05』より転載しています)

相手が動く前にもてなすのが、 「接遇」
取材前、私たちは戦々恐々としていた。自分たちでオファーしてなんだが、テレビで観てきたあの平林都さんを相手に、失礼の塊のようななまくら者の私たちが、粗相なくインタビューをこなせるのか。甚だ心許なかった。姿勢や言葉遣いのだらしなさを一喝され、身動きも取れず、時間だけが過ぎていく……。そんな想像すらよぎった。
しかし我々の前に現れた平林さんは終始にこやかで、聞いたことになんでも答えてくれた。今回は指導ではなく取材をお願いしたのだから、それは当然なのだ。私たちはときに、役者の演技に、役者自身の人間性を重ねて観てしまう。それと同じことを、平林さんに対して行っていたのだなと反省した。
平林さんは、マナー講師として全国各地の企業で年間200~300回も研修を行う敏腕として知られる。その一方で、社員を激しく叱りながらマナーを叩き込んでいくスタイルは、メディアでもたびたびセンセーショナルに取り上げられてきた。そして平林さん自身も、ある程度厳格なマナー講師としてのイメージを意識的に演じてきたのだと思う。私たちはメディアが切り取る彼女しか知らないため、平林さんがいつも誰かを叱りつけていると思いがちだ。
そんな彼女が企業の引く手数多なのは、実績を出しているからだろう。では、平林さんの教えるマナーとは企業にどんな利益をもたらすのか。平林さんの提唱するマナーは“接遇”という。辞書を引くと「もてなすこと。応接すること」と出る。本人にもっと噛み砕いてもらおう。
平林さん「まず、接客と接遇は違います。接客はもてなしの準備です。お客様にお茶やお料理、座布団を用意したりすること。それはあくまでも、もてなしのファーストステップであり、ゴールではありません。一方、接遇は利益を得るために行うおもてなしです。いざやって来たお客様を、いかにもてなして楽しませるかということなんです。楽しんでくれたお客様が『ありがとう』というお礼として、ご褒美をくれる。それが私の考えている接遇の目的なんです」

“上手な嘘”ならついていい?
もちろん平林さんは接客的なマナーも軽視はしない。ある型を学ぶことで、失礼を避ける。防御としてのマナーも重要だからだ。しかし、平林さんの提唱する接遇は、褒められるうえに利益をもたらす“攻めの姿勢”だ。
平林さん「たとえば、上手な噓なんていうのは接遇ですよね。お世辞なんてその最たるもの。化粧品売り場で働いているなら、お客様に似合う色味を見つけて『すごくお似合いです!』と言いますよね。そう言われて、嫌な思いをするお客さんはいません。『私にはまだ知らない美しさがあるのかしら』なんて思ったところに『この色味が似合う方は少ないんですよ!』って言われたら、ついその化粧品を買うわけでしょう。それが接遇。楽しいことを提供する噓はなんぼでもついていいんです。お世辞という上手な嘘によって商品を買ってもらうのが接遇です。もちろん人を騙して悪儲けするような噓は絶対ダメですよ。でも、自分を騙す噓は大事ですね。どんなに忙しいときも、へっちゃらな表情で余裕ぶった方が良いことも多くある。そうしないと、お客様も先輩も上司もいい仕事をくれないじゃないですか。私はね、噓はついちゃいけないって言葉自体が、誤ってると思います」
「噓をついてもいい」というのも接遇のあり方。世にいう「嘘をついてはいけません」という道徳観と相反する思想に、まず面食らう。平林さんとはこんなにもラディカルなのか。平林さんはさらに常識を覆していく。「仕事に真心を込めるなんて無意味」とまで言うのだ。
平林さん「心を込めて仕事するのはよろしくないですよ。心を込め出すと、周りが見えなくなって、業務に平等性がなくなりますから。目の前のお客様だけに真心込めて手厚くサービスすると、その間他のお客様がほったらかしになる。それじゃトータルでいい仕事はできないでしょ?
それに、仕事は真心だっていう人に限って『頑張ります』とか『努力します』って口ばっかりなんです。でも、そんなことはどうでもいいんですよね。数字さえ上げてくれたら、あとはもう手抜いたっていいんだから。まだ私がマナー講師になる前のことですけど、上司を見ていたら、業務時間でもゴルフしたり映画観に行ったりずっと遊んでいるんです。なのに、その人は成績トップだから誰も何も言わないのね。今の時代、社会がどんどん苦しくなっているのに、ますます努力一辺倒の人が増えているでしょ? 本当に大事な利益を見失いがちです。もちろん、心そのものは大切。だから、守っておかないといけない。どうやって自分を守りながら、最大限利益を上げるか考えるべきだと思うんです。そこで形が重要。接遇はそのために必要なんです」

“心を込めない”ことが求められている
平林さんの考え方は現代の成果主義にとてもマッチしている。私たちがメディアで目にしてきた彼女の怒気を孕んだ指導風景とは異なり、その思考はとてもクールだ。どうしてこんなにもスマートな思考に至ったのだろうか。
平林さん「私が『いい人だな』って思ってきた人はみんな早くにリタイアしていくんです。なんでだろう、と考えたときに、私は『この人たちは仕事に心を込めすぎて、後先見えなくなってしまったんだ』と気づきました。心を入れるから、悔しくなるし、悲しくなる。いい人ほどストレスを溜めて、心を病んだり、胃を患って亡くなる。そんなの残念じゃないですか。仕事はまず利益を上げればいい。心を入れるのは、プライベートだけで十分。
でも、私が『上手に噓をつきましょう』『仕事に心を込めてはいけません』と言うと、社長とかお偉いさんは反対する。お年寄りは『気持ちがなければ、いい仕事はできないよ』とおっしゃいます。むしろ若い人たちの方が『そうだよね、人間にテレパシーや霊感は存在しない。心なんか見えへんもんね』と言うんですね」
一般的にマナーといえば、年長者から教えられるものというイメージがないだろうか。国立民族学博物館名誉教授の熊倉功夫氏は、『文化としてのマナー』 (岩波書店)の冒頭で、マナーは「社会の権力を握っている老人の側に属している」と端的に指摘している。「社会の秩序を維持するためのシステムである」と。
マナーを押しつけてくるスパルタの人というイメージがあるから、平林さんも「権力を握っている老人の側」と誤解され、反発を受けるのかもしれない。しかし、現在の平林さんは決して「老人の側」に属しているわけではない。むしろ若者に受け入れられているのだ。
実際、取材当日、おなじみの真っ白のスーツに身を包み、ひとり渋谷の街を歩いていた平林さんは、ものの5分ほどで3組もの若者に写真撮影を頼まれ応じていた。今、彼女は若年層に人気だ。
YouTube で「平林都」と検索すると、様々な人気YouTuberとのコラボ動画が出てくる。パーカーを着てドッキリの仕掛け人になったり、楽しくチーズフォンデュを食べたり、昔の恋の話をしたりする平林さんは、テレビで見せる“鬼軍曹”感は薄く、親しみやすさが全面に出ている。60組以上の有名YouTuberのチャンネルに出演し、合計再生回数は、4,000万回にも上るという。なぜ彼女は今、YouTuberたちと共演するのか。
平林さん「最初はコロナ禍で仕事も制限されている時期でしたし、お誘いを受けたのでどんなもんだろうってやってみたんです。そしたら若い人たちがみんな自由に楽しくやってるでしょう。だから好きだなぁと思って出続けてるんです。逆にテレビって今すこし窮屈なのかもしれない。台本通りにやらないといけなくて、ちょっとでも間違えたらカットがかかってやり直し。それに比べて、YouTubeはほとんどが即興でしょ。アクシデントも面白がってそのまま見せちゃう。私に言わせれば、あるべき型を仕上げるテレビは接客で、リアルタイムに視聴者を楽しませていくYouTubeが接遇なんです。YouTuberの方々って面白ければなんでもありっていう考え方で、上手に噓をつくし、心も込めずにうまくやっていらっしゃると思いますよ。それが面白いし、いい刺激をたくさん受けています」
平林さんが長く提唱してきた“接遇”のスタイルが、時代にフィットしたともいえるかもしれない。では、どうやって彼女はその境地にたどり着いたのか。彼女の過去からその理由を探ってみた。

平林都(ひらばやし・みやこ)
エレガント・マナースクール学院長。鳥取県出身。高校卒業後、兵庫県の信用金庫に就職。数々のお稽古ごとの経験を経て、27歳で同マナースクールを設立。「形なくしては心は伝わらない」という信念のもと「接遇」を広める。病院、銀行、自動車販売店、美容院、洋菓子店などの現場で数多くの接客研修を担当。現在では年間で200~300件以上の研修をこなしている。
接遇はストイックな処世術
鳥取県に生まれた平林さんは、幼い頃から母がおらず、父も家を空けがちで、高校卒業まで親戚の家を転々として暮らしていた。その経験が、平林さんに「接遇」の原体験を与えることになる。
平林さん「母はいないし、父は帰ってこない。だからといって、泣いて目を腫らしても、両親は戻ってこない。世話になってるおばさんは鼻歌を歌いながら生活してるのに、私はなんでこんな不幸なのって思ってましたけど、もう開き直ることにしたんです。この生活で、やっていくにはどうしようって考えてね。おばさんが新しいお洋服を着て姿見を見ていたら『とっても似合うね。モデルさんみたいに綺麗』と言う。そしたら彼女がご機嫌になっちゃって、夕食が一品増えたりしたのね。ひもじい思いはしたくないから、お世辞を言って、上手な噓をつきました。それが今の接遇につながっています」
そうして無事高校を卒業した平林さんは、信用金庫に勤める。その頃、“お稽古ごと”をいくつも並行して習いはじめた。満足にしつけを受けなかった自分は常識を知らないと思っていたからだ。
平林さん「恥をかかないように、マナーを勉強しようと思ってお稽古をいっぱいしました。でも、茶道や華道、着つけ、お料理教室といろんな流派や先生によって、言うことが全然違うのが面白いなと感じて。それから、それぞれのいいところを全部吸収し、自分だけのマナーをつくれないかなと思うようになりました」
多いときには18もの稽古をかけもちし、退勤後に3、4つをはしごする毎日。27歳で独立した平林さんは、エレガント・マナースクールを設立した。企業での研修を通して、地道に接遇を伝えていた平林さんは、『エチカの鏡~ココロにキクTV~』 (フジテレビ、2008~2010年)に出演。その指導ぶりと実績によって、“伝説の女講師”として紹介され、一躍有名となった。
それにしても、なぜ平林さんはあんなにも厳しく指導をするのか。「褒めて伸ばす」が良しとされる時代において、あの激しい叱咤ぶりは、批判に晒されがちだと思うのだが……。
平林さん「誰しも上辺のおべんちゃらが好きですよ。でも、それで人は伸びますか? 現状維持しかできないと思います。本を読んでわかったとか、テレビを見て知ったではなく、生身で行う指導なのです。身体に染み込むまでやり通す。子どものおねしょを早くなくすための、母親役と同じかもしれません。やっぱり誰かが厳しく叱って指導しないといけない。
会社で言えば、今は社内で接遇し合ってるのかもしれませんね。でも、その接遇はいりません。上司が部下にお世辞なんか言ってたら、若手は育ちませんよ。叱られたときにこそ人は『見返してやる』と思う。自分を追い込むことで成長できるという意味ではスポーツと同じかもしれません。今はそういう厳しさが良くないと言われるけど、私みたいな人間もやっぱり必要なんじゃないかと思いますね」

誤ったら、成果でお返ししよう
ここで気になるのはやはり記憶に新しいあの「炎上」のことだ。人気番組『チコちゃんに叱られる!』 (NHK)に出演した平林さんは、番組スタッフを叱責。するとスタッフは泣き出してしまった。これを受けて視聴者から批判が殺到した。この件をどう受け止めたのか。
平林さん「『チコちゃん』のことでは、大変お騒がせ致しております。NHKという企業の空気を読み足らなかったので、同社の方に頭を下げさせたことにつきましては、申し訳ないと存じます。しかしながら、平林のスタイルを望んで依頼され、台本に従い撮影したので、行き過ぎとお思いになれば録画ですのでカットすればよいわけです。でも、あれを流す決断をしたわけですから、私も批判は甘んじて受け入れるべきかと存じます。
私自身は炎上したこと自体はさほど気にしていません。批判されることで、自分が今誤っているということにも気づけますから。むしろ、批判やアクシデントによって、私の心はますます鍛えられるので、ありがたく受け止めています」
平林さんが「大変お騒がせ致しております」と言った。普通だったら「お騒がせして、誠に申し訳ありません」と思わず口走りそうなところだけれど、意識して言わないようにしているのだろうか。
平林さん「もちろんです。私、その場しのぎの謝罪なんて必要ないと思ってますから。たとえばクレーム対応でも謝ってもしょうがない。相手は私たちに謝ってほしいんじゃなくて、自分を納得させてほしいんですよ。だから傾聴して思いを受け止め、要求を理解してあげるんです。そのうえで私は、そのクレームをくれたお客さんから、また別の新しいお客さんを紹介してもらうところまでもっていきたいと考えます。お客さんと10分も20分も喋る機会なんて、クレームでもない限りなかなかないでしょ? ピンチはチャンスとよく言いますけど、まさにそれです。相手の気持ちを受け止めて、満足してもらったらお礼をもらう。これが接遇なんです。間違えたときに謝ってはいけません。謝らずに、成果で倍返しするんです」
平林さんが伝える接遇マナーは、クールな利益追求の姿勢だ。そのエッセンスは自身の人生観と密接にリンクしていた。平林さん自身が、生き延びるサバイブ術として磨いてきたマナーだからこそ、“失われた30年”しか知らない現実主義な若者たちが、シンパシーを抱いているのかもしれない。
さらに近頃業務のオンライン化が一気に進み、仕事上でのコミュニケーションはますます簡素化している。だからこそ接遇が大事なのだと平林さんはいう。
平林さん「デジタル化は進んでいますが、なんだかんだいっても仕事とは人と人との関わり合いだし、アナログな人間関係がものをいう。言葉においても、この10年ほど、パソコンや検索サイトのせいで型にはまった言葉ばかりが目立ってきました。ですが、自ら考え抜いた言葉こそが相手の胸を打つもの。そこで接遇が大切になると思っています」
簡素化しているからこそ、差をつけるために求められるのが、これからの接遇なのかもしれない。ますますシビアになるであろうビジネス環境を生き抜ける人材を増やすべく、今日も平林さんは日本のどこかで、心を鬼にして接遇マナーを伝えている。

取材・文/安里和哲 写真/枦木功(nomadica)
――XD MAGAZINE VOL.05 特集『誤る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。