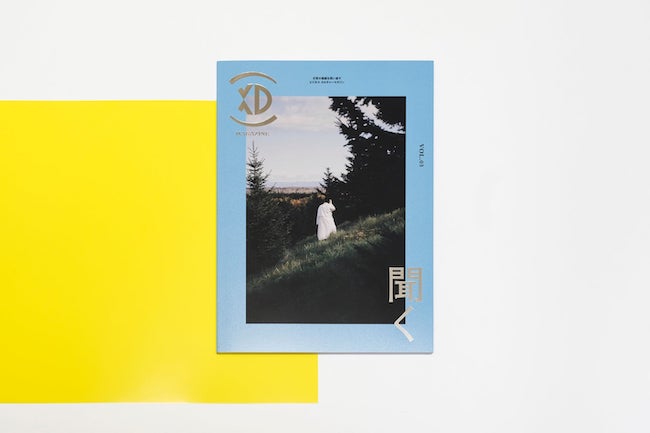写真集『intimacy』で若手写真家の最たる賞である木村伊兵衛賞を受賞し、セクシャリティやジェンダーなどをテーマに作品を制作し、常に新しい風を感じさせる現代美術家、森栄喜さん。近年は写真、視覚表現にとどまらず、より人の感覚全般を意識した試みを続けている。自身初のサウンドインスタレーション作品で、現実社会に拾われることの少ない「小さな声」を音声収録した『シボレス│破れたカーディガンの穴から海原を覗く』で公になったのは、様々なバックグラウンドをもつ人の生命感であった。そこにかすかに響く「小さな声」が鑑賞者の心にほんの少しの愛しさを残す。
新宿御苑と新宿三丁目、二丁目の境い目あたり。戦後から立ち続けているという不思議なビルがある。小さな飲み屋が集まるそのビルの四階に佇むギャラリー・KEN NAKAHASHI。近年様々なシーンで注目を集める現代美術作家を扱い、森さんの展覧会も数回行われたその場所で、窓外にそびえる路上の大樹を眺めながら、インタビューは行われた。
(この記事は2021年12月8日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.03』より転載しています)

森栄喜(もり・えいき)
1976 年、石川県金沢市生まれ。パーソンズ美術大学写真学科卒業。写真集『intimacy』(ナナロク社、201 3 年)で第39 回木村伊兵衛写真賞を受賞。近年の展覧会に個展「シボレス|破れたカーディガンの穴から海原を覗く」(KENNAKAHASHI、2020 年)、グループ展「フェミニズムズ / FEMINISMS」(金沢21世紀美術館、2021-22年)、美男におわす」(埼玉県立近代美術館、2021 年)など。
言葉を無化する
「“聞く”という特集なのに少し言いにくいですが(笑)、普段作品をつくる過程では、あえて“聞かないように”しています。言葉の影響ってとても大きくて、何気なく放たれた一言でもずっと頭に残ってしまい、混乱して変にバランスを取ろうとしてしまう。なので作品の核となっている自分のなかから発せられる声に集中するようにしています。
そのなかでできた作品も、すんなりと人に聞かせる状況になり得ないような作品になっています。語感的に親しみがないような言語を使っていたり、物理的に雑音や騒音があってわざと聞こえなくしていたり。声や音を“発する”ということに近くて、一方的に演説するような“聞かせる”ではなく、究極的に言葉の意味を“無化”して届けたいといつも作品をつくるうえで考えています」
存在だけ残して、風のように耳をすり抜けていく言葉たち。言葉の意味を最大限「無化」するなど、通常のコミュニケーションでは想像できない。しかし「無化」することによってその声の「存在」があるということに、ぐっと視線を向かせることになるのかもしれないと思うと自然と納得がいく。
2018年に行われたフェスティバル/トーキョーでのパフォーマンス『A Poet: WeSee a Rainbow』では白い服を身にまとい、自身の詩を朗読した森さん。自分の声を意図的に無化してみたことで、気づいたことがあったという。

《A Poet: We See a Rainbow》2018 © Eiki Mori, Courtesy of KEN NAKAHASHI, Photo:Kazuma Hata
国際的な舞台芸術祭、「フェスティバル/トーキョー」のまちなかパフォーマンスシリーズでの作品。多様な価値が新しい可能性を拓くことを目的とした同芸術祭で、森は自らの体験、感情を交えた詩の朗読を、公園や路地の一角など、あえて街の喧騒のなかで行った。自ら朗読を聞こえなくすることで、耳を傾けることでしか成立しない、自分と他者の「問い」を表出させるパフォーマンス。
「このパフォーマンスでは、スピーカーを通して本来なら十分伝わる音量で自作の詩を公共の場で朗読しているんですが、同時に騒音を流すことでわざと声が聞こえづらい環境をつくりました。まとっている真っ白なケープのような服も、衣装を担当してくれたwrittenafterwardsの山縣良和さんと話し合って、性別や年齢、人種などを判別しづらくしたり、一見普通の布に見えるけど実は紙からつくられている生地を使用したりしています。
実際やってみて面白かったのは、聞こえないようにするための“騒音”に導かれるように人々が集まってきたことでした。『なんだなんだ?』って感じで。それって全然想像してなかったことだったんです。“聞こえなくするために”つくった音が、人に“聞きたい”と思わせ、向かってこさせた。
僕がこのとき朗読した詩は日記のようなとても個人的な内容のものだったんですが、“聞こえてない”と思ったらすごく堂々と読めたんです(笑)。でも同時にちゃんと聞いてほしいっていう思いも溢れてきて、言葉のもっている意味や力、欲望ってとても強いんだなと感じました。このパフォーマンスは困難な状況下で声を発する人が“いる”ということが一番重要なことで、その存在を可視化させて、パフォーマンスを目撃するということを通して場所や時間を共有してもらうという試みでした。
これは、様々なマイノリティーを取り巻く現状の話にも通じると思います。何かを話すとき、何の心配もなく話せて人々に声が届く人と、自分の声を届かせるために、まずその環境を整え機会をつくって、いろんなリスクや負担を背負いながら叫ばなきゃ届かない人も“いる”。その状況を伝えていきたいです」
「聞く」というと自動的に「話を聞く」に方向に意識が傾いてしまう。私たちが何気なくしてしまう意識の単調さが、このパフォーマンスでは浮き彫りになる。言葉の意味や外見にとらわれずに、まず相手が「いる」ということに対して耳を傾けるということを我々はどのくらいできているだろうか。五感を介した、言葉に頼らないリアルな体験が、「いる」ということを我々に真に認知させる。
「ズレと合言葉」

《シボレス|鼓動に合わせて目を瞬く》2020 © Eiki Mori, Courtesy of KEN NAKAHASHI
サウンドインスタレーション初作品「シボレス│破れたカーディガンの穴から海原を覗く」に続く、緊急事態宣言下の東京で、人のいなくなった街を背景に撮影した映像作品。15のキーワードの言葉を、声を出さずに影を使った動きとして映し出した。KEN NAKAHASHIと、大阪のCalo Galleryにて発表された。
Calo Galleryでの『シボレス│鼓動に合わせて目を瞬く』は、言葉に宿った感情や記憶が、身体言語として影となり、街の壁に刻まれていくのが映像で表現されている。
「暮らしのなかで出会うささやかな美しさや愛おしさを書き留めて、それを作品のなかの重要な要素として“合言葉”にして、それを身体的な動きに置き換え、街角でパフォーマンスをしました。夕日によって壁に照らし出されたパフォーマンスをする僕自身の影を記録した作品なんですが、この作品も言葉の意味をできるだけ消そうとしています。
言葉ってもちろん自分の記憶もそうですし、たくさんの人の記憶や歴史が受け継がれているものですよね。自分だけのものじゃない言葉の存在感のようなものを影に託して壁に刻みたいという思いがあって。壁は街や領土など、ときに冷酷に区切るものでありつつ、暮らしのなかで愛着のある風景でもあります。ふと立ち止まった目の前の壁に夕日によって影が生まれたり消えたりする。その偶然さも、とても“対話”的だと思うんです」

街の数十年、数百年の流れと、その日の夕日が差す数分間。その時間軸上のズレが一瞬だけ交差する偶然性とそこに発生する合言葉。「お互いの立ち位置のズレ」がある人間の対話も「交差しないわけではない」のかもしれない。「以前、アーティストの遠藤麻衣さんと『二人だけの婚姻届をつくる』というプロジェクトを一緒にやりました。例えばお互いへの弔いを生前に共有するために、月に一度、サプライズで花を贈り合う、とか。そういう決めごとを、食事をつくったりおしゃべりしながら決めていきました。結論に向かって突き進んだり結果だけを見せるんじゃなくて、過程そのものが主題になる作品なんですが、遠藤さんと僕では結婚(婚姻制度)において立ち位置が全然違う。二人のズレがあることでプロジェクトが成り立たないんじゃないかと不安もすごくあったんです。でも『お互い同じだよね』ではなくて『違うよね』という前提からはじまる対話は、言葉を交わすたびに新しい問いや発見が次から次へ放たれるような感じで、とても楽しかったんです。
ずっと写真をやってきたからか、視覚や言葉の依存を超えた、触覚とか聴覚とか、よりリアルな手触りを僕自身最近とても新鮮に感じます。撮影ではうまく“切り取りたい”という意識がどうしても生まれてしまいます。それに対して声や音は周りの会話や街の音など、いろんな環境音と一緒に混成しあって、明確なフレームに収まらないし収めることができない、ある種の曖昧さや自由な広がりがある。流動する、着地しない定まらなさが心地いいと感じるようになりました」言葉で伝えていくのではなく、感覚的にズレをあらわにすることによって作品をつくる森さん。そうした手法の根には、自らの願いがある。
「一人ひとり立っているところが違うし、もっているものや経験してきたことも違う。わかり合うということがとても難しいし、簡単に代弁できることなんてないという前提があって。でも声が作品になることで、人のなかにいろんな声が蓄積していって、ゆっくりかもしれないけど当たり前というか自分ごとになっていく。そうすればズレや違いが気にならなくなるというか、ズレがあること自体を楽しく感じられるようになるのかなと思います。社会や自分のなかの小さな声に耳を澄ませて、その声とじっくり対話しながら作品にしていきたいです」

《雷電Dialogue》2021 © Eiki Mori, Courtesy of KEN NAKAHASHI, Photo : Eiki Mori
指先の触覚をマイクによって音に翻訳・拡張しながら森自身が拾い集め、その場の環境音、フィールド・レコーディングのサウンドを中心に、カメラが捉えた定点映像作品。森は、そこにはいない不在の誰かの輪郭をなぞるかのようにマイクを動かしながら、音を集めた。KEN NAKAHASHIの開廊8周年記念グループ展での特別展示として発表された。
「ズレ」があることをお互いに受け止め、認め合うことでほんの一瞬だけその場に出現する「合言葉」。個人的なこと、簡単には聞きにくいことであればあるほど、この静かで強い意識をもつことで、まずその相手の「存在」を身を以て感じることができ、ズレがこすれ、生の温度が人間関係に与えられる。
それはコミュニケーションにおける、日常で触れることがない、別の視点からのアプローチと言えるのではないか。そんなコミュニケーションのふるまいを、独自の方法で提示する森さんの作品は、今後も私たちの記憶の襞(ひだ)をまたいで、独特の存在感を残し続けるだろう。そうした手法は一見非現実的に見えて、現実的な手触りを私たちに残し、意識の面から、「聞く」ことの本質をつかませてくれる。そしてその「存在を聞く」ということができたときはじめて、耳障りだったズレが「合言葉」になるのだ。

森栄喜「Moonbow Flags」

東京・新宿にあるギャラリー「KEN NAKAHASHI」で、森栄喜の個展が10月10日(金)から12月20日(土)の期間、開催される。本展では、森が描いた白い図形とポートレートを組み合わせた新しい写真シリーズ「Moonbow Flags」を発表する。
本作では、1968年5月にフランスで起きた「五月革命」のスローガン「敷石の下はビーチ!」という言葉が着想の一つとなった。抑圧の下に広がる自由の可能性を示唆するこの言葉を起点に、森は国家や権力の象徴としての「旗」と、日常の中で見られるキッチンのタイル模様や壁紙の幾何学模様とを組み合わせ、固定されたシンボルの意味を再解釈する試みを行う。
タイトルにある「Moonbow(ムーンボウ)」とは、月光によって生じる虹を指し、通常の虹とは異なり、目を凝らさないと見えないほど微かに浮かび上がる現象のこと。「Moonbow Flags」というタイトルには、既存の旗が持つ権威や象徴性を解体し、偶然性や遊び心を取り入れることで、固定観念にとらわれない新たな視点を提示する森の意図が込められている。
本シリーズでは、過去10年間に撮影した未発表のポートレートと、旗や日常的な幾何学的構成を参照して描いた白い図形をフォトグラム技法によって重ね合わせ、約20点の作品を制作。
森栄喜のこれまでの作品が、個人の親密な記憶や社会的な規範との関係を探求してきたように、「Moonbow Flags」もまた、社会と個人、歴史と日常、権威と遊びの間に生まれる曖昧な領域を可視化する試みとなるだろう。
・会期:2025年10月10日(金)– 12月20日(土)
・開廊日時:火曜–土曜 13:00-20:00
*「アートウィーク東京」期間中の11月5日(水)– 9日(日)は、10:00-20:00まで開廊
・休廊:日曜・月曜
・オープニング: 10月10日(金)18:00-20:00 *作家も在廊予定
取材・文/豊田名帆 写真/野田祐一郎
撮影協力/KEN NAKAHASHI