その小さな書店には、1冊しか本がない。東京、銀座1丁目にある『森岡書店』のことだ。2006年に神保町の老舗古書店から独立した森岡督行氏は、茅場町に古書店を創業。その後、2015年から今の銀座の5坪の店に移り、1冊だけを取り扱う風変わりなスタイルの店としてリスタートさせた。
「無謀な試み」。そう思われたが、国内外から多くの来店客を集め、この形になってもう10年の節目を迎えている。書店や出版業界の厳しさばかりが聞こえる中、なぜ森岡書店は支持されるのか? 森岡氏が形づくる、本と人との幸せな関係とは?
この10年を振り返りながら、手探りしてみた。

取材日は、森岡書店にて「髙地二郎 写真集 刊行記念展」が開催されていた。来場客同士で会話がなされ、賑わいを見せる
しぼった結果、広がったつながり
「1冊の本を売る書店」を着想したのは、2007年だという。まだ『森岡書店』が茅場町に店を構える古書店だった頃だ。
そもそも店主の森岡氏は、大学を出てすこし経った後、神保町『一誠堂書店』へ入社した。古本の街の老舗古書店で修行を積んだ後、2006年に独立。自身の名を冠した店を営んでいた。
森岡氏「一誠堂書店から独立した書店には、苗字プラス書店という名前が多く、自分もそれに倣いました。店を出した翌年には、すでに『1冊だけを扱う店があっても成り立つんじゃないか?』と夢想しはじめていた。早い段階で、頭の片隅にずっとあったんですよね」

森岡書店店主 森岡督行氏
書店といえば、書籍や文庫が並んだ書棚をのぞきながら、あれこれ物色するのが楽しみのひとつだろう。しかし、森岡氏は、そんな書店の当たり前を捨てたわけだ。
なぜか? 理由のひとつは長年書店業界にいて「このような書店は、これまでにないと思った」から。もうひとつは「1冊にしぼったほうが本と人のしあわせな出会いが生まれるのではないか」と考えたからだという。
茅場町の店は、運河沿いに昭和2年に建てられたビルの中にあり、ロケーションも店の雰囲気もよかった。そこで古書を置きながらも半分はギャラリーのように活用。出版記念イベントでも使ってもらい、写真展示と写真集販売などをよく実施していた。

取材は、銀座で歴史的な建造物として知られる奥野ビルにある森岡書店別室「a long time ago」にて行われた。この空間は朗読会やピアノのコンサートなど、よりクローズドなイベントの開催で使用されている
森岡氏「すると、その1冊だけを求めて、多くのお客様がいらっしゃった。さらに著者や編集者、本のデザインを手掛けた方などと会話や交流がうまれる。こうしたつながりを、皆がよろこんでくれたのです。むしろその1冊を通して幸福なつながりができるというか」
ファンが集う瞬間が、小さな書店の中に何度も生まれたわけだ。さらに独立して10年目を迎える直前の2015年、銀座一丁目の物件と出会ったことが、後押しになる。
昭和4年建造の鈴木ビル。東京都の歴史的建造物に指定されていて、かつて日本の対外宣伝誌をつくっていた会社『日本工房』の後進の『国際報道工藝』が入っていた場だった。日本の出版の礎を築いた会社であり、また森岡氏自身、対外宣伝誌を『一誠堂書店』時代からのめりこんで集めていた縁もあった。
こうして半ば運命的なものも感じて、森岡氏は、1冊だけを売る書店を銀座にあらためて起ち上げた。
森岡氏「この頃に、スマイルズの遠山(正道・スープストックトーキョーなどの創業者)さんとイベントで出会い、『1冊だけしか扱わない書店』のアイデアを伝えたら『おもしろい!』と喜んでくれ、壁打ち相手になっていただけた。結果として株主のひとりにもなっていただけたことは大きな後押しになりました」
そして想像以上の「つながり」が生まれる。

出版は、東京の地場産業
販売する1冊の本は、当初、自ら出版社に「この本を売りたい」と直談判して仕入れた。週替りで売るのを考え、事前に年間50冊ほどのリストをつくり、あたっていくつもりだったが、このときに意外なことが起きた。
森岡氏「割と早い時期から、弊店に興味をもってくれる編集者や著者の方が現れたのです」
著者や編集者、場合によってはデザイナーが誇りをもってつくった1冊の本を展覧会のように置かれ、丁寧に売ってもらえる。そのユニークさは多くの作り手たちの心の琴線に触れたに違いない。
Amazonなどのネット経由で本を購入するのがスタンダードになった時代、むしろ作り手の顔と思いを直接読者にゆっくり伝えられるのは、ことさら価値が高いと感じた面もあった。
結果、すぐに森岡書店の在り方に共感が広がり、森岡氏が「選ばれる」側に早くから変わったわけだ。
森岡氏「出版業は“東京の地場産業”といえるほど、東京は出版業界にかかわる方が多い。世界でも稀なのではないでしょうか。そうした方々とつながりやすかった地の利もあったと思います」
こうして写真集、デザインブック、画集、小説、童話などなど、多彩なジャンルの“1冊”が森岡書店には並んだ。トークイベントや関連した展示などは、出版社や編集者、ときには著者と一緒に考えてつくりあげるという。
たとえば、取材時は横尾忠則氏がY字路を撮った写真集『僕とY字路Photograph』(トゥーヴァージンズ、2025年)の展示販売の準備中。出版社の担当者とは「どうしたら忙しい横尾さんが面白がって店を覗きにきてくれるか」をあれこれ思案した。
森岡氏「銀座にもY字路がいくつかあるので、『そこで昔の駅弁のように立ち売りしてみたらどうか?』とか。実際はそこまでできませんでしたが、1冊の本をどのように届けたらおもしろいことができるか、どんな体験を提供できるか。1冊を通して、まったく予期せぬアイデアが浮かんで、場合によっては実現する。そうした偶然の広がりが生まれて、予期せぬ未来につながるのが、醍醐味でもありますね」

それは、そのまま来店客の醍醐味にもなっている。
「おもしろい書店がある」「どうやって1冊をプレゼンテーションしているのか」「今度はどんな本をどのように売るのか?」――。ふつうの書店とは違うモチベ―ションで引き寄せられた多くの人たちが銀座一丁目の鈴木ビルを訪れるようになった。展示する1冊を求めてくる人はもちろん、こうした店と森岡氏そのものに魅せられて遠方からあえて訪れる人が多いのも、『森岡書店』ならではの特徴だ。
インバウンド客も多い。1冊の本を売るスタイルは、日本のみならず海外からみても稀でユニークなものだった。欧米の雑誌やウェブメディアからの取材記事、そこからさらに海外のインフルエンサーなどが『森岡書店』を興味津々でとりあげてくれた。
森岡氏「最近は店で『スパシーバ(ありがとう)』とか『ダスヴィダーニャ(さようなら)』と聞こえてくるので聞いてみたら、ロシアのメディアで店が紹介されたためでした」
「1冊の本を売る書店」と絞ったことで、国境を超えて本と人、店と人をつなげるようにまでなっているわけだ。森岡氏自身も、1冊を通して思いがけない縁が生まれ、予想外の場所に連れて行かれることがあるらしい。
昨年夏、インド出身の建築家ビジョン・ジェイン氏の著書『Recollections』(GALLERY MAGAZINE、2025年)を販売。アートディレクターの佐藤卓氏とのトークイベントも開催した。その縁で、後日、森岡氏はジェイン氏の誘いでインドに招待され、彼の地でイベントに参加。そこでイタリアのキュレーターと知り合い、彼女が自身のギャラリーの20年間を振り返る本を出したと聞き、その本を森岡書店で展示することになった。
まさに、偶然の出会いが、予期せぬ未来につながったわけだ。
森岡氏「そもそも書店には、本を通してなにかあたらしい知識や観点と出会い、新しい扉が開かれる“接点”のような役割がある」
1冊の本にしぼることで、接点としての役割はより際立ち、濃厚さも増した。そんな体験設計こそが、『森岡書店』の妙味かもしれない。

「世界の明るいほうに、目を向けていたい」
とはいえ、だ。
日本の書店事情は暗い話題のほうが目立つ。2003年には、書店は全国で2万880軒ほどあったが、20年後の2023年には1万918軒にまで減少している(※1)。デジタルメディアの隆盛などで、紙の本も激減。その売上は1996年のピーク時には2.6兆円あったが、2024年は1兆円にまで落ち込んだ(※2)。1.6兆円が消えてなくなったわけだ。
※1 出典:『出版指標 年報 2025年度版』
※2 日本出版インフラセンター 書店マスタ管理センター調べ
この出版不況、書店の苦境は、森岡氏にはどう映っているのか? 率直に聞くと「良い面もあると思っているんです、私は」と意外なこたえが返ってきた。
森岡氏「哲学者のバートランド・ラッセルは本の序章で『世界は2つの要因からできている』と書いています。陰と陽、善と悪、美と醜、右と左……。何事も決してどちらかひとつではない。だとしたら、どちらを見るか、捉えるかによって、ものごとは変わるということです。
だから、私は世界の豊かなほう、しあわせなほう、明るいほうに目を向けて生きていこうと決めているんです。書店や出版をとりまく状況でも、同じです」
確かに、書店の絶対数は減ったにも関わらず、『森岡書店』のようなチャレンジングな店には、国内外から人が集まる。まだ本を好きな人は多い証拠だ。出会い方のやりようを変えれば、いまだのびしろはあるといえる。デジタルの隆盛で紙の本が読まれる機会は確かに減ったかもしれないが、SNSやネット販売を通じて、届くべき人に本を届けられる機会は格段に増えた。『森岡書店』もネットコンテンツやSNSがあったからこそ、世界にその名を知られるようになった。
森岡氏「そもそも『1冊の本を売る書店』を思いついた頃も、『売り上げが立たない』『体力がもたない』という声もありました。けれど、私はできるだけ明るいほうを、ポジティブなほうを見ていた。
銀座のこのあたりは、街全体が一つのものを売り続ける専門店の集積地ですからね。『空也』は主に、“もなか”を売る店だし、銀座8丁目の『たちばな』は、かりんとうだけで創業100年を超えていますからね。弊店にいらっしゃる方は、そのあたりを含めた銀座の街をそぞろ歩きする体験もぜひ味わってほしい」
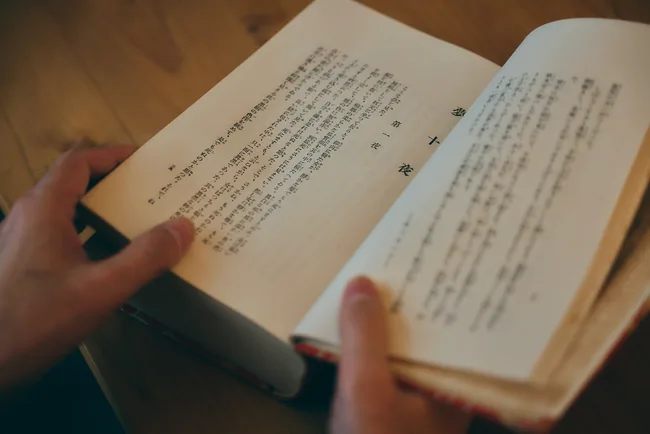
『森岡書店』のつながりは、まだまだどこまでも伸び続けている。今はいち書店の枠組みを超えて、プロデュースや地元・山形で新しいかたちの「百貨店」づくりの企画なども手掛けている。
「百年の果実」と題して、100年前のカメラで100年前の果実をとる写真展も開催したばかりだ。
森岡氏「連載の調べ物をしていたら、かつて、銀座通りにあるカメラ屋にはライカⅠ型が置いてあって、そのモデルは1925年、ちょうど100年前に発売されたんです。さらに調べてみると、桃の白鳳やぶどうのネオマスカットなども1925年にできていた。それらを100年前のライカで撮ったら、100年前の人のような感覚が味わえるんじゃないかって」
妄想は尽きず、すべて楽しげな試みにつながっていく。また個人的な読書体験の挑戦として、夏目漱石の『夢十夜』を1年かけて読むことを試みたいと画策中だという。
さらには、読書市場を活性化させるため「成人式で荒れているような、いわゆる“ヤンキー”と若者たちに本を読むことを推すのがいいのではないか」と冗談ぽい妄想までしていた。
森岡氏「一見、読書とかけ離れた場所にいそうな彼らですが、きっと仲間同士の絆は硬い。カリスマ的なリーダーが『今、本、読むの最高だぜ!』なんて熱く言ってくれたら、フォロワーである後輩たちも一気に読むんじゃないかな思うんです」
いや。もしかして結構、本気でうまくいくのではないか?
明るいほうに目を向けたほうが、きっとうまくいくだろうから。

取材・文/箱田高樹 写真/タケシタトモヒロ 編集/鶴本浩平(BAKERU)




