モノからコトへと消費の軸が移っていると言われ、マスマーケティングから1:1で顧客に向き合い、顧客体験(CX)を高める重要性が日本でも浸透しつつある。
2019年4月と10月にはCXに関する知見を共有し、体験できるカンファレンス『CX DIVE』を開催。計2,000名以上の来場者が訪れた。この先、CXはさらに注目の概念となっていくだろう。
しかし、CXの重要性はなんとなく理解したものの、まだはっきりとした輪郭が掴めず、どのように取り組んでいくべきかを悩んでいる担当者も多いのではないだろうか。
日本ではCXという概念はまだ馴染みが薄く、日本語での書籍も少ないのが現状だ。本記事ではXD編集部がセレクトした、CX理解の手助けとなる本を紹介する。
Harvard business review 「顧客体験」はプロダクトに勝る

CXを高める上で、「商品管理」から「カスタマージャーニーの管理」への意識変革は欠かせない。「Harvard business review 『顧客体験』はプロダクトに勝る」はCX理解の入門書として最適だ。カスタマージャーニーの構築方法と運用するための組織体制について図解付きで紹介されており、これからCX施策に取り組む組織にとって、大枠理解の手助けとなるだろう。
顧客との常時接続が可能になり、APIエコノミーが進展している今、領域を横断したカスタマージャーニーの作成が可能となってきている点なども同書で触れられている。CXにおいて、顧客が自社のサービスを手に入れた瞬間だけではなく、買う前の期待値調整から、買った後の体験をデザインする重要性を理解する上のとっかかりとしてオススメしたい。
CX戦略

「CX戦略」は「そもそもCXとは何か」を理解するのに最適な一冊だ。
各章を通し言及されているのは、「心理的・感情的な価値」の大切さ。機能や性能などの物理的価値はやがてコモディティ化し、ブランド間での差別化が難しくなってきている。「心理的・感情的な価値」を高めるには、顧客の潜在ニーズを汲み取る必要があり、そのためには顧客一人ひとりと向き合い、行動を観察することが求められる。
「CX施策の具体例」、「CSとCXは何が違うのか」、「CXと売上の関係性」など、複数の切り口から「CXとは何か」を解き明かしている書籍だ。
「『CXってなんだ。わからん』と言うような経営トップや経営陣にCX戦略への取り組みを意思決定させるのは至難の業である」と書かれているように、日本でのCXの浸透はこれからだ。本書は、CXについての理解を促すだけでなく、CXという考えを組織に浸透させる上でも役立つだろう。
顧客体験の教科書
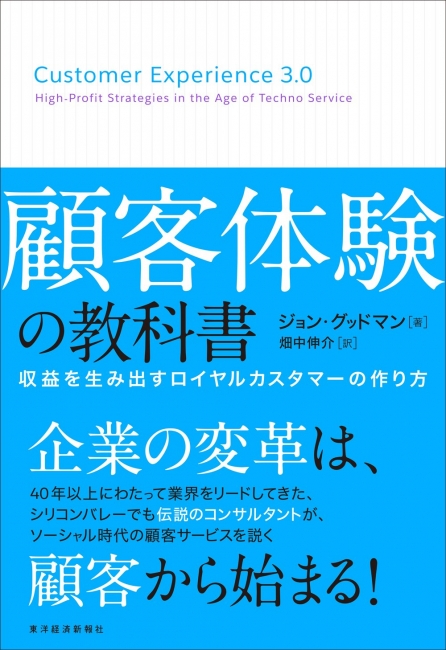
「CX戦略」が「CXとは何か」を網羅的にカバーしたものだとすれば、「顧客体験の教科書」は企業が顧客と良質で長期的な関係を築くための具体的な方法を紹介している。その方法は3段階に分けて紹介されている。
1つ目は顧客を正しく理解すること。2つ目は顧客とサービスのあらゆる接点をデザインし施策に落とし込むこと。3つ目はCX施策を実行に移すために、テクノロジーを導入したり、組織をマネジメントすること。
本書には、CXの財務的な効果を定量的に判断する手段や、CX施策の失敗例も記されている。組織全体でCX施策に取り組むためには、ビジネスの成長にどれくらい貢献するのか示す必要があるし、大きな失敗はできるだけ避けなければならない。
店舗やコールセンター、ECサイトなどブランドとのあらゆる接点が顧客体験につながる。つまり、組織を横断してCX施策に取り組まなければ、顧客の期待に応え続けることは難しい。本書には組織全体にCX施策を浸透させるための手段が細かく記されているので、「CX戦略」と合わせてぜひ参考にしてほしい。
ジョブ理論

顧客が抱えている潜在ニーズを推し量り、適切に期待に応えることは、CXを高める上で大切だ。「ジョブ理論」には顧客が本当に望んでいるものは何かを知る方法が書かれている。顧客が求めているのはプロダクトではなく、今の状況をより良くすることだ。プロダクトを通じて、どんな状況を生み出し、どんな感情を抱かせるかを考えなければならない。
例えば、アパレルブランドの「ALL YOURS」は、現代のワークスタイルに合わせ、服のデザインではなく機能性に着目することで、顧客が解決したい課題を解消するデニムやパーカーを生み出した。
目の前の顧客が言語化できていないけど、抱えている課題はなんなのか。「ジョブ理論」は顧客の持つ潜在ニーズをを見つけるためのヒントを与えてくれる。
アフターデジタル

顧客とブランドのあらゆる接点だけでなく、IoTやセンサーがあちこちに設置され、常に顧客の行動が可視化されるようになると、顧客は常時デジタルに接続されている状態になる。日本にいるとまだ現実味がない世界だが、インターネット人口8億人を超える中国の都市部では、スマートフォン保有者の98%がモバイル決済を行なっている。
「アフターデジタル」では、オフラインがオンラインに内包された世界で、顧客の体験がどう変わっていくのかを中国の事例をベースに紹介している。顧客の行動を常時把握できるようになると、過去のデータから顧客の現在の状況に最適なコミュニケーションを取ることが可能になる。著者の一人である、藤井 保文氏の所属するビービットは、エクスペリエンス企業への変革を支援する企業だ。
CXを高める要素の一つとして、従来のようにマスマーケティングをするのではなく、顧客一人ひとりに向き合うことが求められる。本書では、データを元にして顧客の潜在ニーズをより正確に汲み取ることができるようになった世界が描かれている。本書の最後には、今後日本企業が取るべき変革についての示唆もある。オンラインとオフラインの境目がなくなり、融合していく社会において、どのような顧客体験を提供していくべきか。CXを高めるためのテクノロジーとの向き合い方を本書から学ぶことができるだろう。
イノベーション・スキルセット~世界が求めるBTC型人材とその手引き

破壊的変化の時代においてイノベーションを生む人材(BTC型人材)に必要なスキルセットが語られた『イノベーション・スキルセット〜世界が求めるBTC型人材とその手引き』。なぜ、いま顧客体験に注目が集まっているかがデザイン観点から言及されており、CXを考える際の参考になる。
インターネットの普及以降、作り手と消費者とのつながり方は変化し、企業はエクスペリエンス(体験)を通して顧客と向き合う必要性が出てきた。その時代には、従来のマーケティングの4Pに加えて、Customer Experience(顧客体験)を加えた、5Pが大事であるという考えが紹介されている。
加えて、CXが向き合う対象も変化している。企業は体験と向き合うようになったが、当初その多くはオンラインの話だけだった。それも「アフターデジタル」でも紹介されているように、近年ではオンライン/オフラインの境目がなくなり、双方を横断した視点での体験作りが求められてきている。
アフターデジタル時代のCX視点を把握する上で、必読の一冊だ。
小売再生 ―リアル店舗はメディアになる

店舗はメディアになる——この言葉を掲げ、リアル店舗の役割が「買う場所」から「ブランドへの愛情や信頼を強力に刺激する場所」へと移り変わっていると語るのが、ダグ・スティーブンス氏だ。
世界的に活躍する小売コンサルタントである同氏の著書『小売再生 ―リアル店舗はメディアになる』には、リアル店舗の役割が変化する背景から、メディアからする店舗の実例、メディア化していく術が記されている。
彼の考える、未来のリアル店舗の在り方は、文字通り“顧客体験”自体が価値となる場所だ。モノ消費からコト消費へと消費の思考が移っていると言われるが、スティーブンス氏が考える小売の変化はその限りではない。ブランドそのものを体験する場所へと変化していくのだ。
XDでも来日時にインタビューしたが、小売の未来と体験のあり方を考える上で、非常に興味深い切り口が示されている。
文化人類学の思考法

CXとは、企業と顧客の新しい関係の在り方を歓迎し、その多様性を肯定する思考と実践であるといえる。この、とても複雑で確固たる正解のない問いと向き合うための、文化人類学という学問を提案したい。
『文化人類学の思考法』は13のテーマからで文化人類学を紐解いている。CXを考えるのであれば、経済を研究した文化人類学者たちの足跡をたどる「贈り物と負債」がまずは参考になる。本項では、商品交換(お金でモノを買う行為)を理解するために、贈与交換(贈り物をもらいお返しをする行為)と比較し開設している。
一見別物に見える商品交換と贈与交換は実は同一線上にあり、その位置によってモノの意味や価値は変化するという。つまり、モノのやりとりを通して、人と人との意味や関係を変化させるのだ。
家族同士なのか、買う手と売り手なのかといった関係性に応じて交換形態が選択されるのではない。むしろ、商品交換なのか贈与交換なのかというモノを介したコミュニケーションの形態の差異こそが人々の関係の在り方をつくりだし、交換の形態に応じて変化するのだ。
本書には、時空を越えた人類の生活文化をもとに、私たちがCXと呼ぶ営みを考える上で優れた道具が満ちあふれている。
たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング

「マーケティングにおいて最も大切にしているのは、一人の名前を持つ具体的な顧客、“N=1”を徹底的に理解すること。一人のロイヤル顧客が、なぜそうなったのか、どういうきっかけがあったのかを深く理解できれば、そのきっかけをまだロイヤル化していない顧客に提示することで、高い確率でロイヤル化を促すことができる」
『たった一人の分析から事業は成長する 実践 顧客起点マーケティング』は、P&Gジャパン、ロート製薬、スマートニュースでマーケティング業務に携わってきた西口一希氏による著書だ。ロート製薬では、代表的な商品となっている「肌ラボ」の売り上げを、年間20億円から160億円まで拡大し、販売本数ベースで日本No.1に到達させた。ロクシタングループでは過去最高利益達成に貢献、スマートニュースのアプリランキングを1年で100位圏外からiOS、Androidとも一位を獲得するなどの経歴を持つ。
西口氏が一貫して語るのは、名前を持つ具体的な一人の顧客“N=1”を徹底的に理解すること。名前の見えない想像上の誰かではなく、実在する1人の顧客と会い、ブランドとの出会いからこれまでの経験に耳を傾ければ、購買行動とその行動を左右する深層心理の関係が有機的につながるとしている。そうしたメッセージを踏まえて、本著ではマーケティング戦略を考えるうえでの重要な考え方、同氏が確立した「顧客ピラミッド」「9セグマップ」という2つのフレームワーク、スマートニュースで実際に行った分析の事例などが紹介されている。
CXを向上するためには、顧客一人ひとり(“N=1”)と向き合い、サービス・商品に対するニーズや感情を知ることが必要不可欠だ。その方法論が、本著に詰まっている。
僕らはSNSでモノを買う

コミュニケーションから情報収集へ。SNSの役割が変化する中、企業は従来の媒体や自社サイトだけでなく、SNSを通した購買体験や顧客との接点をいかに設計できるかが求められている。
Webマーケティング・メディア事業を手掛けるベーシックで、マーケティングメディア『ferret』の創刊編集長や執行役員を歴任する中、この変化を強く感じたのが『僕らはSNSでモノを買う』著者の飯髙悠太氏だ。
同氏は、この変化を読み解き、SNSデータの解析ツールを軸にSNSマーケティング支援をおこなうホットリンクの取締役へと転職。著書内でも語られている、SNSをはじめオンライン上での口コミやユーザー投稿「UGC(User Generated Contents)」と、このUGCを起点とした消費行動プロセス「ULSSAS(ウルサス)」の重要性を提唱している。
会話形式のポップなトーンで話を展開していく同書だが、SNS上で企業が顧客とどのように向き合うべきかの要諦が詰まっている。飯高氏に取材した記事と合わせて是非読み込んでみてほしい。
CXを高める方法やCX施策を企業に浸透させるのに役立つ本を紹介したが、方法論だけでなく、目の前の顧客に徹底的に向き合う情熱や、サービスを通じて成し遂げたい世界観を持つこともノウハウと同じくらい大切なことを忘れてはいけない。
これらの本が、CXを高めるための一助となれば幸いだ。もちろん、まだまだCXを理解する上でヒントとなる書籍もあるだろう。そうした書籍に心あたりのある人は、ぜひとも教えてほしい。




