2024年4月、原宿の神宮前交差点に「まちの銭湯」が誕生した。『小杉湯原宿』だ。
東急不動産の商業施設「ハラカド」の地下1階。流行りのサウナは置かず、名物は牛乳風呂と温冷交代。SNSでバズらないように注意をはらい、インバウンド客であふれる界隈とは時空が違うかのように、近隣の馴染み客が気取らず集う場になっている。
なぜ、小杉湯原宿はこの地で銭湯をはじめたのか。トレンドが行き交う商業地で、息の抜ける場を生み出す意義とは? 株式会社小杉湯の副社長で、小杉湯原宿の番頭でもある関根江里子氏を、訪ねた。

なぜ縮小する市場のなかで、『小杉湯』が求められているのか。
550円を番台で渡して、「男湯」と入った白抜きで書かれた暖簾をくぐる。こぢんまりした脱衣所で脱ぎ、ふわっと湯気のあがる浴場へ。かけ湯をしたなら、いよいよだ。
壁の富士山を眺めながら、ミルク色の湯船にどぷんと浸かる。身体と心が湯でほぐれ、「あ~…」なんて声が思わず漏れる――

途中、完全に忘れていた。ここは東京・原宿の商業施設、東急プラザ原宿『ハラカド』の地下1階だった。『小杉湯原宿』は、2024年4月にオープンした銭湯だ。運営しているのは株式会社小杉湯。昭和8年創業の東京・杉並区高円寺の老舗銭湯「小杉湯」の運営母体である。
高円寺の小杉湯といえば、ベンチャー企業にいた3代目の平松佑介氏が2016年に父親から経営を引き継ぎ。伝統的な銭湯の心地よさを日々、丁寧にブラッシュアップ。くわえてSNS活用や各種イベント、さらに隣接する3階建てシェアスペース『小杉湯となり』などの取り組みで、若い世代まで魅了して休日となれば1,000人近い利用客が訪れる人気銭湯として知られている。そのノウハウを活かしてつくった2号店が小杉湯原宿というわけだ。
実のところ、銭湯全体でいうと市場は縮小するばかりだ。1970年代、全国の銭湯は1万6,000軒あったが、右肩下がりで数を減らし2023年度には2,847軒しかない。利用者の減少はもちろん、施設の老朽化、後継者不足などが主な原因だ。
にもかかわらず、なぜ小杉湯は活況なのか? 原宿の商業施設から声がかかるほどの人気を博しているのか?
「小杉湯が人気な理由ですか? それまでは『シェアリングエコノミーが支持されているからです』なんて、それっぽい解説をしていたんですけど……」と小杉湯原宿の番頭である関根江里子氏は言う。
関根氏「最近は『大きなお風呂って、気持ちいいですからね』と言っています(笑)。欧米の人たちより基礎体温が低い日本人って、温かくて大きな湯船に入るのがあっているのがひとつ。あとやっぱり、銭湯って心地よくて、優しい空気があるじゃないですか。それってすごいことだと思っているんです」

株式会社小杉湯 副社長 関根江里子 氏
原宿に住み、探した結果、「わからなかった」
心地よく優しい空気がある。関根氏は幼少期から、銭湯にそんな思いを抱いていたという。
関根氏「もっと言うと、『怒りがない場所』だった」
関根氏は父親が還暦のときに生まれた子で、父は子どもたちを養うため70歳を過ぎてもずっと清掃の仕事をしながら家計を支えていた。そんな父親を誇りにしていたが、社会ではきれいな格好をして、大きな会社に勤め、社内外での政治的な動きに長けた人がチヤホヤされがちで、汗水垂らして働くエッセンシャルワークを小さく見がちだった。そうした価値観にいつもイラ立ちがあったという。
関根氏「ただし、銭湯だけは違ったんです。忙しい父は銭湯が好きで、私が子どもの頃、よく近所の銭湯に連れていってくれました。そこでは大企業のビジネスパーソンも、役所の職員も、清掃工場の社員もない。服も肩書も脱ぎ捨てて、『何者でもない人』として振る舞える。誰も彼も同じ湯船に浸かって、イライラすることなく、心地よくてやわらかなひとときを過ごせたんです」
そんな幸せを、あらためて思い出したのは4年前だ。大学卒業後、関根氏はフィンテック系スタートアップでCOOを務めていた。資金調達のため、懸命にプレゼンシートをつくり、ビジネスモデルの優位性を大仰に語る日々。「社会課題の解決」も当たり前のようにミッションに含まれていた。
しかし実のところ、株主へのリターンのために命を削っている違和感がちくりと、あった。
関根氏「スタートアップのエコシステムのなかにいるうち、毛嫌いしていた人間になっていた。父と真逆の生き方をしていたんです」

転機は、湯船の中で迎える。ベンチャーキャピタルへのプレゼンを終えたあと、リフレッシュのため初台の銭湯へ。株主もビジネスモデルも売上予測も、ストレスも肩書も湯船の中で、ほぐされて消えていくのを感じた。“何者でもなくなっている自分”にあらためて気づいた。
関根氏「『私がしたいのはコレだ』と天から降ってきた。銭湯の経営をしようと決めちゃったんですよ。多くの人に銭湯のこの優しさと心地よさを提供することで『社会課題を解決する』と決意しました」
そして小杉湯にジョインする。2022年4月。この頃、小杉湯は東急不動産から声をかけられ、2024年にオープンするハラカドの地下1階に銭湯ができないか、と打診されていた。
当時は、まだコロナ禍の終わり頃。そのタイミングで新たな商業施設に積極的に出店するのはリスクが高かった。外出もままならず、「非日常の経験を味わうために出かける」なんて空気がほとんどない時だったからだ。
ならば、高円寺小杉湯にあるような、ゆったりと大きなお風呂に浸かる「日常の風景」を原宿で生み出せないか、と東急不動産からのアイデアだった。
このプロジェクトに、小杉湯の平松代表が、関根氏を指名。高円寺の運営を手伝いつつ、小杉湯原宿の立ち上げ準備を手掛けるようになった。
すごいのが、そのタイミングで関根氏が原宿に住み始めて、町内会などに積極的に参加しはじめたことだ。原宿の地元の人たちの目線で、ニーズを丁寧に掘り起こした。
関根氏「東急さんを通じて町内会を紹介いただいたのですが、『原宿の街で銭湯をやりたい若者』として見ていただいて、みなさん応援してくだったんですね。『どんな銭湯なら、原宿らしいでしょうか?』『原宿らしさ、って何でしょう?』と事あるごとに聞き続けました」
聞き続けた結果、辿り着いた答えはこれだった。『原宿らしさは、わからない』。
関根氏「地元の方々がよく『原宿はどんな文化も閉じずに受け入れてきた』と話されていたんです。戦後まもなく原宿あたりは米軍の駐屯地になって、同時にアメリカの最新カルチャーがどんどん入ってきた。そのとき閉じずに受け入れ、またその後もあらゆる流行が入ってきても受け入れ続けてきた街なんです。つまり、原宿を原宿たらしめているのは、そんなオープンな心意気をもった“人がいること”だと気づいた」
だから小杉湯原宿は、地元の人たちがとにかく大勢来る日常の場にすることが正解だと考えた。地元の人たちの日常の場になれば、自ずと原宿らしい銭湯がそこに生まれるからだ。

ターゲティングされた場所に行きたいか?
日常使いされる「銭湯」になるため、小杉湯原宿が力を入れたのは、内装デザインだ。1933年と戦前に建てられた古い木造建築を持つ高円寺小杉湯とは違い、商業施設の地下に新たにつくる銭湯には「ココは銭湯である」と伝える説得力が必要だった。
関根氏「しかも『ハラカド』の地下に大量のお湯を引き込むのは設備上、限界があって大きな湯船や浴場がつくれない。“銭湯らしさ”を巧みに設計する必要があったんです」
もっとも、手本はやはり高円寺小杉湯に求めた。何をもって人は銭湯を銭湯とみなすかをアンケート調査すると「富士山の絵」「固定のシャワー」「押しカラン(蛇口)」 など、すべて高円寺小杉湯にあるものがあがったからだ。
関根氏「たとえば浴槽の深さを60cmにして、そこに張る湯の高さを57cmにしたのも高円寺と同じにした結果です。するとちょうど平均的な女性が入ったときに、口につかないくらいの高さになって、名物のミルク湯の香りが鼻先に心地よく届くんです」

当初の予定から削ぎ落としたものもある。サウナだ。
クリエイターを中心にしたビジネスパーソンも多い原宿の街。「そこに銭湯をつくるならば……」と当初は、彼らに人気のサウナを置く予定もあったが、関根氏は「必要ないのでは?」と却下した。
関根氏「サウナは今、『整うため』に使われることが多いじゃないですか。サウナを置くと、そんな目的をもって訪れる方が多くなる。そうじゃなくて浴槽を介して心が柔らかくなって『何者でもないあなた』になれる、『何もしなくていい場所』にしたかったから」
「チカイチ」と名付けられた、銭湯の外から道でつながった地下1階フロアも小杉湯がプロデュースした場所だ。そこには誰しも座れる椅子とベンチ、さらにゴロンと寝っ転がって、読書やゲーム、PC作業ができる畳とカーペットのオープンスペースもつくった。

「すべてイベントスペースにしてもいいのではないか」とアイデアが出てしまった時もあったが、イベント時も自由に使えるスペースとして機能するよう死守した。イベントごとにコロコロと変わるような場所は銭湯的じゃない、つまり日常の開かれた場所じゃなくなるからだ。
関根氏「原宿のような商業地って『何もしないでいられる場所』が少ない。買い物や食事といった目的があって訪れる場所になりすぎている。カフェにいっても、コーヒーは飲まなくちゃいけないじゃないですか。でも『チカイチ』は何もしなくていい場所なんです。逆にいえば『何をしてもいい』んです」
そのため『チカイチ』は、平日の午前中から満員に人が埋まる。原宿では稀有な、「何もしなくていい場所」だからこそ、間口が広い。結果として月間10万人もの人が集う、集客スペースになっているのだ。

高い集客力は、また銭湯らしさにもつながっている。冒頭で触れたように、小杉湯原宿の入浴料は大人で550円だ。
実はこの料金は、「物価統制令」によって都道府県ごとに決まっている価格。まちの銭湯はスーパー銭湯やサウナと異なり、公共インフラ的な意味があるため、助成金や固定資産税の軽減措置などが用意されている。そのぶん、価格を自由に設定できず、利用しやすい料金での提供が義務づけられていて、それが東京だと今は550円なのだ。
関根氏「本当は、小杉湯原宿は自然光が届かない地下にあるため、法律上は街の銭湯にならず、物価統制のワクに入りません。しかし、あえて550円を踏襲し、入りやすさにつなげました」
そうなると、利益をどう出しているのか? と思うが、ここでオープンな集客力が活きる。
実は花王、サッポロビール、アンダーアーマーなどがパートナー企業として参画している。小杉湯の姿勢、チカイチの空気に共感した企業が、このスペースにフィットした、石鹸やビール、ランニングウェアといった商品を提案、販売しているのだ。

ターゲットを絞らない老若男女がリラックスして集う場にふさわしい、自社や製品の自然なPRにつながる。加えて、入浴料以外のプラスアルファの売上・利益としても機能している。またそれが550円での低料金にもぐるりと回って還元されていくわけだ。
関根氏「そもそも『20代の女性向けの場所』とか『40代の男性ビジネスパーソン』とか。ターゲティングされ過ぎた場所やサービスって、作為的過ぎてもう行きたくないし、使いたくないと考えている人が増えていると思うのです。銭湯という日常的に誰しも訪れられる場所、カルチャーが先にあるから、多様な方々に来ていただいている。この場所を『この世代に向けて』『こうした嗜好の方に』と企業やビジネスの都合で変えていくのは違う。カルチャーが先で、経済はあとからついてくるものであってほしいので」
そして、運営スタイルでも「日常を守る」工夫を施す。

4ヶ月だけ、一部「お断り」にしていたワケ。
原宿の新たなランドマークとしてハラカドは4月17日にオープンした。地下1階の小杉湯原宿ももちろん同じ日にオープンしたが、当初は、原宿に住む人と働く人のみに制限し、しかも正午から18時までの時間はまるまる営業休止にした。
2024年8月からは制限を無くしたフルオープンとしたが、最初の4ヶ月弱は売上減を承知のうえで、入店と時間制限を設けたのだ。
なぜか? 理由のひとつは、地元・原宿の人たちのための銭湯であることをしっかりと伝えたかったから。加えてもうひとつの理由も、持続的な経営のためだ。
関根氏「オペレーションがままならないまま、大勢のお客様を受け入れると現場が混乱することが目に見えていたからです。商業施設は、オープンから3ヶ月間は人が殺到するとよく言われます。けれど、現場のスタッフがまだ慣れていないからうまくまわせず、疲弊する。サービスの質に落胆したお客さんは、もう2度と来なくなる。売上も右肩下がりになる――。それだけは避けたかったんです。銭湯カルチャーをブームとして気軽に消費されるのだけは、絶対にイヤでした」
結果として3ヶ月経ったあと、1年経った今もハラカドのなかで最も人が集まる施設のひとつが小杉湯原宿になっている。
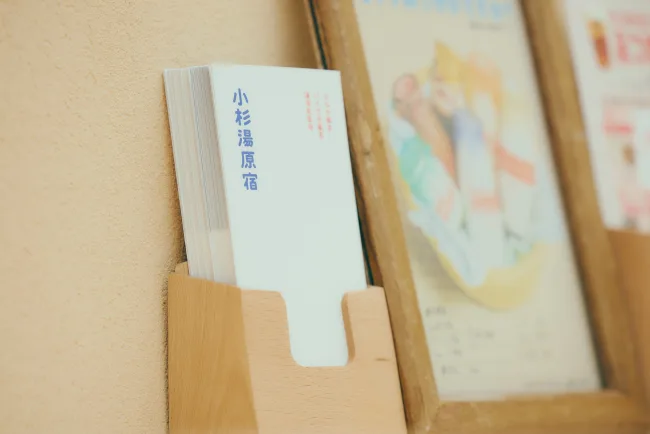
カルチャーをブームとされないように、動画SNSでバズったり、「話題のスポット紹介」のようなメディアへの取り上げはお断りしてきた。一方で、経済やビジネス系のメディアには比較的、登場した。
関根氏「原宿に銭湯をつくった意味や、銭湯カルチャーへの思いが伝わりやすいと考えたからです。そうすると、お客様にも理解や共感を得たうえで来ていただけます」
原宿にもかかわらず、インバウンド客がほとんど見当たらないのも運営の妙からだ。実は英語や中国語など外国語表記をほとんど用意していない。日本語を読解できない人にはややハードルの高い場所になっているからだ。
関根氏「もちろん、海外の方もウェルカムです。ただ興味本位で覗くのではなく、銭湯カルチャーに興味をもち、日本の日常を味わいたくていらっしゃるような方に来ていただきたかった。また日本の街の銭湯にわざわざ来るような方って、本当は観光地化されていない、そうした日常を覗き見したいと思っているでしょうしね」
いずれにしても、1階の表にはインバウンド客があふれかえるが、地下1階には随分と少ない。オーバーツーリズムに辟易して、近隣の生活者が避けるような雰囲気がない。普段使いするにふさわしい日常の場が、ちゃんとあるのだ。
しかも、2025年2月には、1日の平均入場者数が約500人となり、銭湯単体の売上だけで黒字化を果たした。
オープンから1年ですばらしい成果を出しているが、関根氏はその数字よりも、番台から眺めた2つの光景が「わすられない」という。
1つはオープン初日のふとした時間。原宿で顔見知りになった人もふくめて大勢訪れ、肩寄せ合いながらも、ぶつからないよう着替えて湯船へ。満足げに湯気をあげながら浴室から出てきたあと、脱衣所が濡れていたら拭く方がいて、誰しもにこやかに、そしておだやかにアイスやビールを口にして涼んでいた。
関根氏「高円寺の小杉湯で当たり前にある光景が、もう初日から原宿でも見られた。ようはみんな幸せそうな顔なんですよ。私自身が『こんな幸せな仕事って、ないな』と噛み締めました」

もう1つの光景は、数ヶ月前。近所に住む知的障害を持つ常連さんがいる。その方が小杉湯原宿に来ると、ニコニコと楽しそうに畳のうえで本を読んだり、スタッフみんなと話したり、ぐるぐるとチカイチを歩き回る。
夕方、迎えにきたお母さんが、ふと「息子が唯一ひとりで遊びにいっていい場所がココなんです。おかげで私もその間だけはゆっくりできる。ありがとう」と感謝の言葉を伝えてくれたという。
関根氏「こうしたお客さん一人ひとりの日常の居場所をつくれたこと。笑顔をつくれていること。小さいけれど、どんな企業やビジネスよりも深く、意義のあることができていると信じているんですよ」
関根氏と小杉湯は、銭湯という形で、深く優しい愛情のような豊かな何かを、原宿の真ん中に確かにつくった。それは数値化やエビデンスや、KPIやスケールが求められる世の中で、アンチテーゼのように定性的な価値の大切さを訴えかけているようにも感じた。
まあ、そんないちいち堅苦しく捉えないほうが、銭湯らしいな。
取材・文/箱田高樹 写真/タケシタトモヒロ 編集/鶴本浩平(BAKERU)




