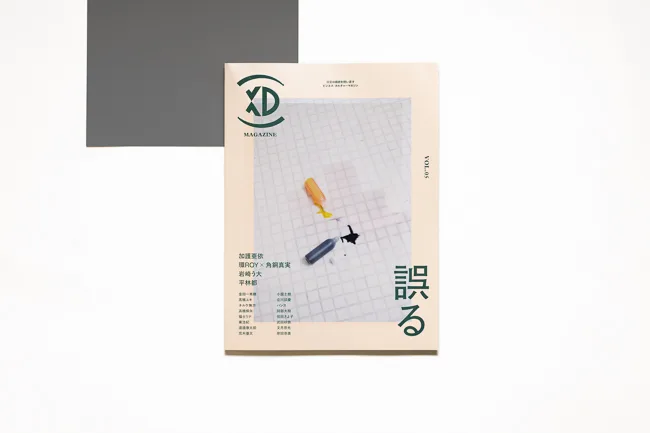言葉を紡ぐ。そう書くとすこし仰々しく感じるものの、これは日々誰しもが当然のように行っている日常的な行為でもある。仕事のメールで、暇つぶしのTwitterで、友人とのLINEで、毎時間、もしくは毎分のようにテキストを介してコミュニケーションをとるのが現代におけるスタンダードだ。
たとえばインターネットがなかった頃と比べると、一日で紡ぐ言葉の量は膨大なものになった。そこだけ切り取ってみれば文化的に発展したといえるのかもしれないが、はたしてそうだろうか。その輪郭を少しでも明らかなものにするべく、書くことを職にする三名の鼎談を実施した。フリーライター、詩人、そして作家。それぞれ活躍の場は違っていても、書くことを通して社会とつながりをもつ三名に「誤り」の今とこれからを聞いた。
(この記事は2022年8月に発行された『XD MAGAZINE VOL.05』より転載しています)
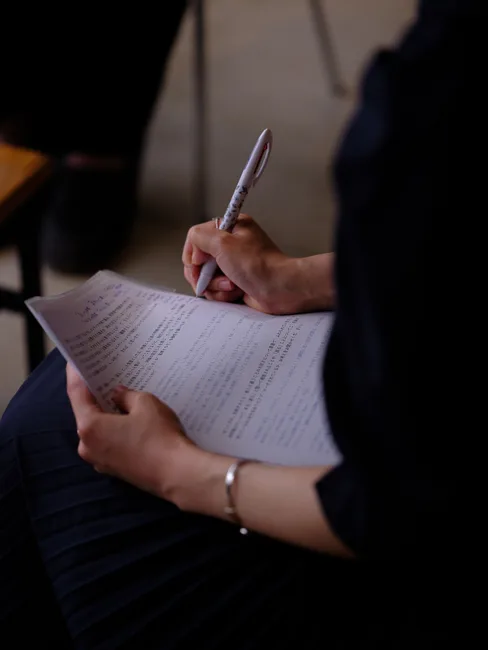
人と、すこし違う景色から
今回の鼎談は、“物書き”である三名に集まっていただいた。フリーライターとして活躍する武田砂鉄さんと、メディアプラットフォーム『note』を中心に執筆を続ける岸田奈美さん、詩を中心とした作品をつくり続ける文月悠光さんという近いようで遠い三名の話は、どのような歩みを辿るのだろうか。まずは、執筆活動をはじめた原体験を振り返ってもらった。
武田さん「僕の場合、はじまりを遡れば小学生くらいの頃でしょうか。たとえば、算数の問題で「○○くんが街を何時に出て、弟が5分遅れて街を出た…」と出題されたときに「なんで5分遅れてくるんだろうな……。一緒に出れば算数の問題もやらなくて済むのに」と思っていました。そうやって疑ってみるのが好きで。」
一同 「(笑)」
武田さん「でも、そう思ったことを友達に話すと「こいつ面白いな」って思ってくれる、ある意味“普通ではない”ポジションでいられる。それが心地よかったんですね。そうした振る舞いの精度に磨きをかけていって……今もその延長という感じですね。文月さんは高校生の頃に詩人としてデビューされていますよね。そういう意味では、“普通ではないポジション”だった?」
文月さん「どうでしょう、私が10代のときは人の表情や空気を読むのがすごく苦手で……その場にそぐわない発言をしては後悔していました。だから場に馴染もうとして、どちらかというと普通であることに執着していたように思います。岸田さんはいかがですか?」

加害者として振る舞うように、強い言葉を投げかけてくる人はきっとなにか強い怒りや悲しみを抱えている。なぜそれを言うような境遇になったのかを強く想像するんです。
―岸田奈美
岸田さん「私は小さい頃から両親に「大物になるぞ」「お前は俺の子どもだから!」と自信をもてるような言葉ばかりかけられていたんです。でも、いざ小学校に入ると私より勉強ができて、足が早くて、モテる子もいて、家のなかとはまったく世界が違ったんです。
父がそんな私を見かねて、7歳のときにiMacを買ってくれました。「お前の友達なんて、このなかになんぼでもおる」って。実際に触ってみたら、インターネットは誰も私の話を遮らない。話を聞いてもらうのは友達よりも主にインターネットのなかでした。
お父さんが亡くなったり、お母さんが病気になったりしたことは友達にはちょっと話しづらいけど、インターネットなら見ず知らずの人に聞いてもらえるので、その距離感が心地よかったというか。自分と同じような画面の向こうにいる一人ぼっちと出会う経験はすごく幸せだったのを覚えています。」

武田砂鉄(たけだ・さてつ)
1982年、東京都生まれ。大学卒業後、出版社で主に時事問題・ノンフィクション本の編集に携わり、2014年秋よりフリーへ。インタビュー・書籍構成も手がける他、TBSラジオ『アシタノカレッジ』ではラジオパーソナリティーも務める。。近年の著作は、『偉い人ほどすぐ逃げる』(文藝春秋、2021年)、『マチズモを削り取れ』(集英社、2021 年)、『べつに怒ってない』(筑摩書房、2022年)など。
http://www.t-satetsu.com
書くことで生まれ得るもの
岸田さん「そんな流れで文章を書きはじめたので、むしろ実際に話すよりもキーボードを打つ方が喋っている感じに近い。執筆するときもじっくり文章と向き合うみたいな姿とは少し違うかもしれません。文章を書こうとするときは怒ったり悲しい出来事が起きたときで、その気持ちをもっておきたくないというか、早く笑い話にしてすっきりさせたくって。お二人はどんなことを考えながら執筆されるのですか?」
武田さん「僕は文章を書くときはだいたい「書きたくねえな」「なにも書くことねえな」みたいな気持ちで向き合っていることが多いので、ちょっと違いますね (笑) 。言葉としては矛盾しますが、嫌だなと思いながら書くのが好きというか、「めんどくさいな」と思いながらも手を動かしていくと、自分のお腹のなかにあった見たことのない光景に出くわすことがあって。自分に対して「お前はそんなこと考えているのか」みたいな発見をするというか。」
文月さん「そうですよね。書いているうちに「最初はここが気になっていると思っていたけど、実はもっと奥に大事な真相があった」と気づく瞬間があって。その瞬間がやっぱり、文章が鏡になって、自分も知らない自分を見せてもらっている感じがしてすごく面白い。
書き方の話をすると、私は詩をつくるうえでもエッセイを書くうえでも、最初にプロットのような、設計図をつくるんです。このエピソードを書いて、次にこう書いて、と一応全体を決めて書きはじめるんですが、その通りにいったことは実際にはあまりなくて。」
武田さん「最初に設計して、最終的には崩すんですね。」

自分の誤りに気づける瞬間は、人生のなかでいつでもある。自分の誤ったことを反芻し続ける姿勢が重要なのかな。
―文月悠光
文月さん「崩すというか、その通りにいかない (笑) 。意図的な操作ではなく、振り回されている。でもそこが面白いですね。手のなかで粘土をこねくり回しているような時間が結構好きで、ああでもないこうでもないと動かしているうちに、このアングルで、このかたちだ!と決まる瞬間があるので、そこを目がけてあるべきかたちへ言葉をならしていくような感覚でしょうか。
私の場合、詩にしてもエッセイにしても、なにか言葉にしたいな、と思うときは違和感から出発しています。書くこと自体が、自分の本音や引っかかっている部分に気づき、思考を深めていくプロセスなので、考えたことがそのまま原稿に直結しているとはいえないですね。」
武田さん「思わずずれてしまったときの景色が重要だと。でもたしかに、文章を書くことを続けていると、いつの間にか4、5ルートくらいに思考の流れが定まってしまうんですよね。なので、意図的にどうやって外すか、みたいなことはよく考えます。執筆作業はある意味で「自分SM」的に、自分でムチを引っ叩いて、自分で気持ちいい、と思いながらやるしか変化をつける方法がない。僕の場合、仕事部屋の隣が小学校なのですが、たとえば校庭から聞こえてくる子どもたちのやりとりを強制移植するんです。「俺もっと胃が大きく生まれたかったな」と言っているのが聞こえたら、それをどうやって目の前の原稿に入れてやろうか、と試行錯誤する。変な作業ですけど、そうやってややこしくすることで原稿を揺さぶってみよう、みたいな。」
岸田さん「面白いですね。お二人の話を聞いて、私は喋るように書くからこそ設計なんてできないので、あくまでも自分のブログのような場で好きなときに好きなように書く、というのが合っているのかもしれないなと再認識しました (笑) 。」

文月悠光(ふづき・ゆみ)
詩人。一九九一年生まれ。十六歳で現代詩手帖賞を受賞。第一詩集『適切な世界の適切ならざる私』(ちくま文庫)で、中原中也賞、丸山豊記念現代詩賞を最年少十八歳で受賞。詩集に『わたしたちの猫』(ナナロク社)、富田砕花賞を受賞した『パラレルワールドのようなもの』(思潮社)。高校の国語教科書『高等学校 新編現代の国語』(第一学習社)に、エッセイ集『臆病な詩人、街へ出る。』の一部が教材として掲載。二〇二五年二月、新詩集『大人をお休みする日』を角川春樹事務所から刊行予定。
http://fuzukiyumi.com/
言葉と読み手の間で
目指した場所から違う場所に着地する、という意味では誤りに寛容な書き方をされているともいえるが、三名はたとえば読者からネガティブな反応が起こったとき、そのことをどう捉えているのだろうか。
岸田さん「私がダウン症の弟について書きはじめたとき、9割くらいがネガティブな反応だったんです。「私と似たような境遇の生活が明るく描かれていて、岸田さんの文章を読むと傷つく」みたいな。それ以来、私の幸せは誰かにとって嫉みの材料のひとつになると知って、書き方は注意していますが、基本的に反応はあまり気にしないようにしています。実体験をエピソードとして書いているから反応もしやすいのかなと思いますが、文月さんが書かれている詩にも嫌だなと思う反応はありますか?」
文月さん「書いたものより、背景を邪推されてなにか言われることの方が多かったです。デビュー当時は「女子高生だから賞を取ったんだ」と言われることもありましたし、明らかに作品を読まずに批判しているコメントが著作レビューに書かれていることもありました。ですが、詩は読み方も読者に委ねられている余地が大きいこともあり、あまり怒りのコメントがついたりすることはないですね。
新型コロナが流行しはじめた頃、まだ「コロナ禍」という言葉さえあったか不確かな時期に、コロナ禍をテーマに詩を依頼されたんです。雑誌の巻頭に掲載される詩なので、なにか希望がもてる内容にしたかったのですが、その頃は「いずれ落ち着くよ」なんて無責任なことは書けない。
なので最終的には、苦しい状況に置かれても人は希望を探す、人の営みを信じるといったところに思いを込めて「誰もいない街」という詩を書きました (『週刊文春WOMAN vol.5』2020春号に掲載) 。この詩を先日イベントで朗読した際に、あらためて、これは詩だからこそ書けたことだと感じました。同じような内容を、私はエッセイでは書けないし、読み手としても詩だからこそ受け入れられる内容だと思います。その違いはもしかしたら、読者と詩が描くビジョンとの距離感にあるのかもしれません。この三人だと、SNSでの発信が多い岸田さんが最も読者と距離が近いのかな、と思うのですがいかがですか?」
岸田さん「攻撃的なコメントは少なくないのですが、それに対して反応することも基本的にはありません。なかには殺害をほのめかすようなコメントがくることもあるので、本来であれば、開示請求をして誹謗中傷する人をつまみ出していく態度を取らなければいけないのでは、と思うのですが、同時に、それで本当に解決するのかな、とも思うんです。
過去に私が弟の写真をTwitterにアップしたとき、死に直結するような意味合いのコメントをしてきた人がいました。さすがにこれはまずいな、と思い「通報します」と反応したんです。その翌日に、本人から謝罪のDMがきて。すこし背景が気になったので、「過去になにか障害のある人に嫌なことをされたんですか?」と聞いたら、アカウントを消して逃亡されました。
すると、さらにその翌日、その人のお母さんからDMで謝罪がきたんです。通報されると慌てた本人から事情を聞いて、連絡してくれたようで。そのDMのなかで、「こんなことを言って許されることではないと思いますが」と前置きされたうえで、「息子は障害があり、中学生の頃から学校に行けていないんです。岸田さんに向けた言葉は、息子がずっと言われてきた言葉なんです」と。」
文月さん「自分がされてきたことを弟さんにされていたんですね。」
岸田さん「その件では結果的に加害者として振る舞ってしまった彼も、被害者意識からそう言ってしまったんだと知ることができたんです。それから、なにか強い言葉を投げかけてくる人はきっとなにか強い怒りや悲しみを抱えていて、なぜそれを言うような境遇になったのかと強く想像するようになりました。
だからこそ、どれだけ法律が正しくてその人を罰せたとしても、その刃はまた別の人に向けるんじゃないか、もしくはSNSの外の世界に向けるんじゃないか、と思って。とにかく逮捕すればいいとは思えないですね。」

武田さん「対応すれば減るものでもないというか、今はなにを言っても、なにか言われますよね。「りんごが好きです」と言えば、「子どもの頃、りんごを食べて吐いたことがあります」とコメントがくるかもしれない。それ自体は致し方ないことなので、気にしながらも、あまり気にしないようにしないといけないのかなと。
職業上、これ書いても大丈夫かなと立ち止まるときもありますが、自分がこう思っている以上、その思いを優先すべきでしょう。社会的にどうかと考えて緩めて書くということを繰り返していると、自分自身どう思っているのかが曖昧になってしまう。
そんなときによく思い出すのが、ある「ママタレント」と呼ばれる人のブログ。子どもの弁当の写真を毎日のように載せているんですが、コメントを見ると、豪華すぎても、質素でも怒っている人がいるんですよ。でも写真は上げ続けていて、その姿を見ていると、自分はなんて自由なんだろうと思う。なのでそうした嫌な反応も恐れすぎないようにはしていますね。」

岸田奈美(きしだ・なみ)
1991年生まれ、兵庫県神戸市出身。関西学院大学人間福祉学部社会起業学科在学中に株式会社ミライロの創業メンバーとして加入、10年に渡り広報部長を務めたのち、作家として独立。Forbes 「30 UNDER 30 Asia 2021」選出やテレビ出演など活躍の場を広げている。著書に『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった』(小学館)、『もうあかんわ日記』(ライツ社)、『飽きっぽいから、愛っぽい』(講談社)など。
正しさと誤りのありか
SNSの登場以降、読者は著者にアプローチしやすくなった。それにより、議論が行われる機会も増えたが、過度の“正しさ”によって出る杭を打つように非難する場面も増えた。あらためて、三人に誤りとの付き合い方について考えてもらった。
武田さん「「正論で潰される」というのは最近よく耳にするフレーズですが、その言い方には慎重になりたいです。正論はその都度変わるもので、自分が正しいと思っていることも時間が経てば変わるもので、コンプライアンスなどといった覚えたての言葉で潰していくことにも危うさがあります。
重要なのは、“正論”がもち出されている場において、その正論はどういうものなのか、といった議論ではないでしょうか。それが法律の場合もあれば、しきたりの場合もあるし、個人のこだわりの場合もあって、それを一緒くたに正論として議論を片づけてしまうのはよくないかな、と思います。ひとつのできごとに対して議論をすることは、時間も文字数も必要なものだからこそ、まずはその場における正しさがなんなのかを突き詰めて考えた方がいい。」
文月さん「武田さんが仰った話は、私もすごく大事だと思います。正しさを振りかざす、とよく言われますが、そんなにみんな正しさに固執しているようにも思えない。この出来事は有名な人が非難していたから自分も非難してOKなどと、厳しい目を向ける対象とそうでない対象を都度選んでいるだけではないかと。
SNSの言論空間自体は、私自身はそれほど不快なものだと感じていなくて。どんな意見にも非難が寄せられることはありますが、でも賛同や応援の声も可視化されるので、孤独にはなりづらい。小学生の岸田さんがインターネットに居場所を見つけたように、SNSが人々の救いになっている部分もあるのかなと思います。
今回の特集のテーマは「誤り」と事前に伺ってそれぞれの「誤り」との向き合い方について、私自身知りたいなと思って今日はきました。武田さんは政治や社会のなかでの誤りについてつぶさに調べ、ときに厳しく書かれていると思うのですが、どのような思いで書かれていますか?」

「正論で潰される」とよく耳にするけれども、重要なのは、その正論がどういうものなのか、といった議論ではないでしょうか。まずはその場における正しさがなんなのかを突き詰めて考えた方がいい。
―武田砂鉄
武田さん「ロシアの大統領を見ていればわかりますが、権力をもっている人は、あらゆる人の営みであるとか、すべてを破壊する力をもっていますよね。なので、僕が「誤り」に対して厳しく文章を書くときには、もちろん、弱い存在じゃなくて、力をもっている存在について書こう、と思っています。
権力者はときに個々人がどういうことを考えているのか、ということを無視したうえで、権力を行使しようとする。そういう人たちに対しては、厳しい言葉を向けていかなくちゃいけないな、と。
ついこの間まで、4,630万円を誤って振り込まれた人が毎日ワイドショーやテレビを賑わせていましたが、もし日本に「責任を問うべき悪い人ランキング」があったとしたら、あの人は3,500位くらいだと思うんです。それをさも1位かのように扱って叩くことは、やっぱりおかしなことだと思うので、その矛先を1〜3位あたりの人に向けるべきではないでしょうか。」
文月さん「そうですね。またなにか誤ったことをしたときは、相手に「謝る」ものですが、適切な謝罪が行われている場面ってどれほどあるだろうと。ただ終わらせたい、取り消したい思いで謝罪している光景をよく目にしますが、かえって、身勝手な印象を受けて腹立たしく思うこともあります。
実は中学生のときに、自分の失言で友達の女の子にすごく怒られたことがあったんです。彼女は普段から自閉症のクラスメイトの手助けをしていて、私はそんな彼女とクラスメイトに失礼な言動をとってしまった。以来大人になってからも、あのとき自分はどうしてあんなことを言ったのか、と度々後悔が襲ってきました。今回の鼎談に際して岸田さんのエッセイを拝読しているときも、当時の「誤り」がずっと頭を巡っていました。でも、岸田さんの本を読むことで「あのときは私が無自覚な偏見をもったまま彼女に言葉を投げかけてしまった。だから彼女は怒りを示したんだ」とすこし整理できて。もしあのときに彼女に怒られてさえいなかったら、私はまた別の場所でぶしつけな、身勝手な発言をしていたかもしれない。後悔し続けていたことではあるのですが、30歳になってようやく、あのときに誤ってよかった、と思えました。」
岸田さん「きっかけになれて嬉しいです。誤りについて、ある編集者の方に言われたすごく印象的な言葉があって。本の制作中に「あなたはなにかを間違ったりしても、それを償って生きていける人間だから、もうなにも迷わなくていい」と言ってくれたんです。自分の誤りに気づけて、そこからまた新しい自分を積み上げていける、と。
今の文月さんのお話もそうですが、本 人からすれば、なにか過ちを犯したときは「ああしていれば」と過去の分かれ道を想像して悔やんでしまうものですが、それは気のせいというか (笑) 。そのときはそれしか選べなくて、振り返って選択肢があったかのように見ているだけのように思いますね。誤りはあるようでない、というか。」
文月さん「そうかもしれませんね。彼女に言ってしまった言葉は取り消せないから、あの瞬間に自分の一生も決まってしまったように感じていたのですが、実は全くそうではない。自分の誤りに気づける瞬間って、人生のなかでいつでもあるから。誤りに気づくためのアンテナを張りながら、自分への戒めとして誤りの記憶を反芻し続ける姿勢が重要なのかなと思い直しました。」

取材・文/梶谷勇介 写真/東海林広太
――XD MAGAZINE VOL.05 特集『誤る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。