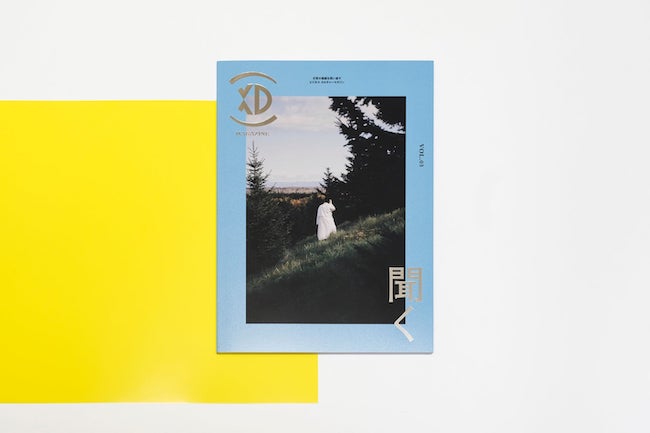アイコニックなデザインを求められる建築家もいる一方で、いちから何をつくるかを一緒に考えてほしいとリクエストを受ける建築家も増えている。建築家・金野千恵さんはそんな依頼を数多く受け、住宅から公共施設まで手がける若手ホープ。敷地を取り巻く音だけでなく、人と向き合いコミュニケーションを取ることで聞こえてくる声がある。多機能で複合的、余白が必要とされるプロジェクトをどのようにデザインしていくのか、 「聞きとる」姿勢を取材した。
(この記事は2021年12月8日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.03』より転載しています)

金野千恵(こんの・ちえ)
建築家。1981 年、神奈川県生まれ。2005年東京工業大学工学部建築学科卒業。同大学院在学中05~06年スイス連邦工科大学に奨学生として留学。2011 年東京工業大学大学院博士課程修了、博士(工学)。2011年KONNO設立。2015年t e c o共同設立。2021年より京都工芸繊維大学特任准教授。作品「向陽ロッジアハウス」は、平成24年東京建築士会住宅建築賞金賞、日本建築学会新人賞ほか受賞。第15回ヴェネチアビエンナーレ国際建築展2016 日本館 会場デザインで、審査員特別表彰 受賞。
プロセスからデザインする
―金野千恵さんは、10年以上「屋根付き半屋外空間」のリサーチを行い、2015年に建築設計事務所「teco」を立ち上げましたが、最近はどのようなプロジェクトを手がけていますか。
金野さん「現在、神奈川県愛川町の『春日台センターセンター』 (2022年竣工予定)が建設真っ只中です。クライアントは福祉を起点として地域コミュニティの再構築を図る社会福祉法人・愛川舜寿会(しゅんじゅかい)の馬場拓也さんで、地域のコミュニティセンターのような複合施設をつくっています。馬場さんからの依頼は『春日台センターセンター』が最初でしたが、このプロジェクトを手がける間に3件のプロジェクトでご一緒しました。そのうちのひとつは、同じく愛川町にある『ミノワ座ガーデン』(2016)という特別養護老人ホームの外構の改修です。まちと建物の境目となる庭を施設の利用者だけのものではなく、まちの一部でもあると考えて、庭をまちに開く仕掛けをデザインしました。
その後、このホームの内部を改修したり、保育園の新築などのプロジェクトも行いました。高齢者や障害者、外国人、一人親家庭など、なんらかの生きづらさを抱えた人が地域社会と分断されないような環境づくりを協働してきて、この『春日台センターセンター』がひとつの集大成と言えます。足掛け6年、tecoがこれまで手がけた作品のなかで最も長く時間をともにしてきたプロジェクトです。」

「春日台センターセンター」の上棟式と餅投げの様子
設計/teco(金野千恵・泊絢香・照井飛翔・村部塁)
施工/栄港建設 竣工/2022.1.予定
神奈川県愛川町の多世代の人々が集う拠点施設の計画。かつて賑わった商店街のスーパー「春日台センター」の跡地に建つ。高齢者の住まいや通いのデイサービス拠点、障がいのある方々の就業支援、言語の壁で教育格差を抱える子どもの通う寺子屋などの機能を備えた複合施設。木造の庇を商店街の遊歩道や散歩道に延ばし、カウンターやベンチ、小上がりなど開かれた居場所が連続する。住宅地へと続く南側の敷地には、静かな個室群が並ぶなど、開放の度合いが変化する構造が特徴。
写真/teco
―どのようにプロジェクトははじまりましたか。
金野さん「愛川町を初めて訪れたのは2015年でした。その頃、商店街の賑わいの中心だったスーパー『春日台センター』の閉店が決まりました。自販機が撤去され、防犯カメラが設置され、まちがどんどん様変わりしていくのを目の当たりにしました。
愛川町は神奈川県の中北部に位置し、なかでも春日台地区は桑畑だった土地が1960年代に開発された、近くの工業団地のベッドタウンです。最初に移り住んだ世代は引退後も愛川町に住み続け、まちの高齢化率は30%を超えていますが、同時に、南米からの出稼ぎ労働者が多く住むようになって、県内2位の外国人居住率となっています。
急速にまちが変容するなか、当初考えていたように長屋の一角のみをリノベーションして介護事業所をつくったところで、必ずしも地域に貢献できるわけじゃないとクライアントと話しました。」
―すぐに設計には、着手しなかったのですね。
金野さん「設計は2017年頃からはじめました。言ってみれば、敷地も、事業も規模も予算もプログラムも確定していないなか、地域に潜入していき、まず、『あいかわ暮らすラボ』、略して『あいラボ』というワークショップをお施主さんと立ち上げました。
メンバーは、0歳児から80歳後半くらいの方々まで。『今日は何々さんが喋ります~』みたいな感じで、教える人、教わる人が日によって入れ替ります。この土地に必要なものを見極めようと集まりを繰り返し、地域の課題やまちの長所をみんなで共有し、実感しました。そのうちに、少しでもそれらが定着する環境をつくっていきたいと思うようになりました。」
自分の五感で客観的に聞く
―クライアントと一緒に、想定するユーザーの声を聞きながらつくり始めたということですね。
金野さん「はい。ケアのプロジェクトは他に比べて、クライアントの声を聞く時間が圧倒的に長いと思います。幼稚園や福祉施設の場合、利用者が直接語れない場合が多いので、クライアント側も手探りです。みんなで想像を働かせるため、多くの施設を訪れて観察もします。私自身、施設に泊まって、サービスを受ける側の環境で過ごしたこともあります。驚いたのは、とあるサービス付きの高齢者住宅の音環境でした。」
―音環境の何に驚いたのですか?
金野さん「各部屋からテレビの音が漏れ、廊下に響いていて、普段すぐに寝入る私もなかなか寝つけませんでした。間仕切り壁の遮音性能が低かったんですね。『なぜこういうつくりなんですか?』と尋ねると、『耳が遠い方が多いから』といった回答をもらいましたが、全員が全員、耳が遠いわけではないので、尊厳が損なわれていると感じました。この頃から、音や匂いといった環境を快適に保つことは、建築の根本的で取り組むべき必須な課題だと感じています。
直接の声が聞けないならば、代わりに感じ取っていくしかありません。自分で体験し、五感をフル稼働して、積極的に聞きにいく必要があります。」
暮らしのなかで繰り返される「確からしさ」を発見する
―設計の過程で、ワークショップを取り入れるのはなぜですか。
金野さん「形骸化したワークショップならば、やる必要はないと思います。でも、もしその活動自体がコミュニティづくりの一環になるならば、『確からしさ』につながっていくでしょう。私が考える『確からしさ』とは、そのコミュニティや場所で日常的に繰り返され、暮らしを循環する活動のパターンのようなものです。仮に、中心人物が退いても、その活動を欲する要因が持続しそうだったり、中心人物の周りの誰かが必要性を共有しているときは、活動自体は続いていく。すでにある活動が十数年続いていたとしたら、この先も同じくらい継続する可能性はあるし、その活動を建築が支えることで、建築の役割も確からしくなると言えるんじゃないでしょうか。
長期的なプロジェクトになりましたが、その間に地域の声をひたすら聞き、活動を観察する間に仲間が増えました。今も、上棟式の餅投げや小学生の建設現場見学会には多くの人が参加してくれ、竣工前からすでに『春日台センターセンター』にはファンがいると感じます。」
―「あいラボ」のワークショップは具体的にプロジェクトにどう活かされたのですか。
金野さん「みんなの話のなかで繰り返し出てくるものは、ある種の強度があります。例えば、若い子たちの居場所になっていたコインランドリー。コインランドリーは明るく、清潔で、無料で座れ、Wi-Fiが使える。冬は暖かい場所で、実はベーシックに必要なものが揃っている。だから、若い子たちの居場所なのだとわかりました。こういう強度のある居場所をいかに新しい事業所に組み込むか、議論を重ねました。
最終的には、共働き世帯の手助けになるように洗濯代行とコインランドリーを設け、それを同時に障害者の働く場所とすることで、事業が組み立てられました。
それから、スーパーの閉店時に『あの春日台コロッケが食べられなくなるなんて!』と、訴えてくる子どもたちもいて、話を聞いていくと小学生からお年寄りまで口を揃えてコロッケを語るんです。それで、コロッケスタンドも計画に含めることになりました。
こうして、暮らしのなかで繰り返されるストーリーにある『確からしさ』を掴み、場所のDNAを引き継いで、新しい事業に組み込むことを試みたのです。」
―住宅の依頼でしたら、「住宅を建ててください」で済みそうですが、こうした特徴的な依頼はどのように舞い込んでくるのでしょうか。
金野さん「私たちが設計した『地域ケア よしかわ』 (2014)は様々な縁を運んでくれました。品川区にある『幼・老・食の堂』(2017)や、『春日台センターセンター』のお施主さんも『地域ケア よしかわ』を見てくださり、そのお施主さんがつないでくれたんです。また、複数のプロジェクトで声をかけてくださるお施主さんが増えていて、春日台、よしかわ、品川のお施主さんの他に、北海道の法人とも『わたなべストア』 (2018)と『PatisserieRuelle』 (2019)に続く3つ目のプロジェクトが動いています。対話を重ねるほど設計者とクライアントの関係が深まり、信頼の基盤が築かれて、また協働したいと思っていただけるのかもしれません。」
多様な社会の、余白を育む
―きっかけとなった「地域ケア よしかわ」はどんなプロジェクトですか。
金野さん「『地域ケア よしかわ』はtecoが最初に手がけた福祉施設で、埼玉県吉川市にある団地の一室の改修です。4席あれば良いという訪問介護の事業所に対して、『地域をケアするのであれば、物理的に思い切り開いた空間をつくりませんか』と提案しました。延床面積は56㎡ほどで小規模ですが、図面を更新するごとにコミュニティスペースとオフィスの境界線をじりじり変更し、最終的に3分の2ほどが地域に開くスペースになりました。
最初からは予期していませんでしたが、小学生や先入観のない若い世代が『地域ケア よしかわ』に飛び着き、居場所とするようになりました。特に共働き家庭の子どもたちが『地域ケア よしかわ』でご飯を食べているのを見て、地域のおばちゃんたちが腕まくりしてくださり、みんなの食堂『ころあい』が始まりました。」

地域ケア よしかわ
設計/KONNO 施工/アトリエポンテ 竣工/2014.3.
埼玉県吉川市にあるコミュニティスペースを兼ねた訪問介護の事業所。1970年代に建てられた吉川団地の名店街における一室を訪問介護事業所へと改装し、地域の人が集う空間をつくった。大きな引き戸型の窓と入口に備えつけられたベンチで外部空間と内部空間を接続させる仕掛け。地域の多様な人に食事を提供するみんなの食堂「ころあい」もオープンし、話題を呼んだ。
写真/teco
―高齢者のための事務所が、地域の子どもの溜まり場になるのは面白いですね。
金野さん「小学生以外にも、ジャージの中学生、子育てママ、美空ひばりのYouTubeを毎日見にくるおばあちゃんや、障害デイサービスの利用者の方、視察に来るスーツ姿の人、あらゆる人が集まってきます。
『多様性の共生社会をどうつくるか』みたいなカギかっこに入れた優等生的なものではない、まさにグチャグチャな状態です。それをどうしたらつくれるか、守れるか。みんなそういう場所を欲していたのではないでしょうか。結果的に、スタッフがちょっと外へ出なきゃいけない間、代わりに見てあげるよ、とか、もちつもたれつつ、助け合いの関係も自然と生まれてきています。」
誰もが、外側をもつ意義
―なぜ訪問介護の事業所がまちとつながることができたのでしょうか? 地域に根差したサービスを展開しているからこそ、半パブリックのスペースが根づきやすかったのでしょうか?
金野さん「ケアの業界の先進的な取り組みをしている方々の傾向として、地域とつながることに手間はかかるが、前向きな結果をもたらすという気持ちを共有しています。根本的に人手不足の問題を抱えているので、既存のシステムはいつか持続しなくなることを見据えていますから、いざというときのためにサービスだけで閉じない、緩やかな紐帯を、今からつくっていこうと考えているのです。」

地域ケア よしかわ
設計/KONNO 施工/アトリエポンテ 竣工/2014.3.
写真/teco
―金野さんのデビュー作「向陽ロッジアハウス」は、住み手が外部とつながる考慮がされていましたね。
金野さん「『向陽ロッジアハウス』 (2011)は神奈川県にある私の実家で、高齢の母も外で庭いじりをしていれば地域の方が声をかけてくださって、自然と互いの見守りになります。加えて、庭の樹木や鳥など、ケアする対象があると内省化されすぎず、自分自身も開かれる感じがあるのでは、と思います。
自分の世界だけでない、外とのつながりがあると、エネルギーをもらえている感じがするのは、家のなかで多くの時間を過ごす人も、外で働いている人でも同じですよね。オフィスのデスク周りだけに座り続けると、見えなくなるものや思考が閉じてしまうことがあると思います。」

向陽ロッジアハウス
設計/KONNO 施工/(有)工藤工務店 竣工/2011.12.
屋根付きの半屋外スペースで、イタリアの建築要素「ロッジア」を大胆に取り入れた住宅。庭側の境界にあるロッジアは3.5 ×7mほどのガラスのない巨大なアーチ窓を形成し、草花の香り、鳥や動物、光や影など絶えず変化する外部の環境を取り込む。ロッジアは庭の植物たちを育て、隣人と交流をはかる場として機能する。
写真/teco
―開くことによってリスクが増すこともありますが、建築が開くことで社会にアプローチすることができるのでしょうか。
金野さん「私たちの取り組むプロジェクトでは、基本的に開くと地域から見えやすくなり、今まで関わりのなかった人たちが見守り要員になる、というケースばかりです。しかし、昨今、『開く』とか『つながる』を重視し、『守る』ことが疎かになっている傾向も強いと思います。何でも開けばいいわけではなく、両方を調整することが専門家に求められているはずです。
『ミノワ座ガーデン』は先にお話した通り、庭をまちに開くというプロジェクトでしたが、開くことと並行して、同じ施設内でプライバシーを尊重する『ミノワセパレイ戸』 (2018)にも着手しました。庭を開きつつ、プライバシーはちゃんと守る。この両輪のバランスを取らないと、最終的にそこで暮らし続けることは難しいです。どんな設計をするときも、『自分がそこに身を置いてちゃんと過ごすことができるか』という感覚は大事にしたいです。」
まちに開いたオフィスをつくる
―今日インタビューをさせていただいている場所、tecoと畝森泰行建築設計事務所が入居する「BASE」は、1964年竣工の一棟ビルを2社の共同設計で改修した建築で、浅草橋にあります。なぜ浅草橋を選ばれたのですか。
金野さん「私は学生の頃から人の営みが現れるまちの風景に興味があったんです。なので大学の卒業設計では多摩ニュータウンの雛壇造成地を崩してつくった新しい丘の斜面に、斜めに登る楽しい街路とまちを計画しました。生活の営みが現れる素地をどうつくれるか、この頃から今まで、ずっと考えている気がします。つくるだけでなく、自分たちが『働く』という活動を街につなげたかったので路面店に憧れていて、通りに面したビルを探していました。

浅草橋は革や装飾資材の問屋が多く、まちを歩いていると1階で作業する職人さんを見かけます。皮をなめしているおじいちゃんの前を通ると、作業の音が聞こえ、音がしないと『あれどうしたのかな』と、気になります。私たちのビルの朝の掃除時間も、地域の方が話しかけてくださったりします。路面に人々の生活が漏れることの楽しさを感じますし、関わりがつくられていくのも楽しんでいます。」
―1階は完全に街に開いていますね。
金野さん「1階は街の開けた角地に該当する場所で、『SQUARE』と呼んでいます。鳥越神社の祭や街のイベントにも参加可能な、フルオープンとなる仕組みにしました。大きなキッチンも設け、食のイベントや日常的な調理の場として使っています。
少なくともひとりは1階に常駐するよう当番制を取り入れています。良い時季には、扉を開け放していると、通りがかりの人が乱入してきます。打ち合わせ中も、小学生が入ってきて勉強しはじめたり。近所を散歩しているおじいちゃんがお施主さんの家の屋根の色に助言したり。外側の人や光、風などがふっと入ってくると、咄嗟に余裕やユーモアみたいなものが生まれますよね。」

写真/yurika kono
―オフィスをまちに開く狙いは?
金野さん「私は自分たちの場所を、自分たちの時間を豊かにすることや、視野を開くために使っていきたい、その実験を常に行う場にしたいです。
クライアントに『開く』と提案するのは簡単ですが、その大変さを肌感覚を掴むことはとても大事です。実際、最初は『地域ケア よしかわ』も子どもが仕事中にちょっかいを出してきて大変という話もあり、まちに開くことで運営に負荷もかかります。私たちの事務所も1階は打ち合わせで使いますが、先ほどのような楽しい乱入や、ギャラリーの利用時はお客さんが入ってきて急に質問されることもあります。でも、そうやって自分たちが関わる社会を感じる瞬間をもっていなければ、みんなのための空間なんてつくれないんじゃないでしょうか。自分たちでも体験しながら諦めずに提案したいなと思っています。」
―閉じている空間はありますか。
金野さん「5階は書棚で囲まれ、スペースが仕切られた図書室なので、一番こもれる空間です。屋上もだいたい人がいないので、ひとりになりたいときは屋上に行くといいです。特定の機能や目的のために部屋を設計し、一対一で役目を考えてしまうと息苦しくなるので、お互いの距離を各々が調整できる環境がとても重要だと考えています。」

BASEの構成は以下となっている。
1階『SQUARE』:街路に面するファサードを大きく改修し、街の開けた角地として機能。フルオープンな出入り口とし、内部には展示壁と大きなキッチンを設け、日常的な調理の場としてはもちろん、イベントの開催も行う。

2階『GARDEN』:この街区には緑地やゆったりした歩道が少ないので、ビルのなかに植栽を多く設けた。外部建具を外し半屋外として設え、窓には透明ビニールカーテンを引いて緩く外部を仕切る。開口部の反対側にはステンレスシートを貼り、収納とトイレを格納する。

3階『teco』
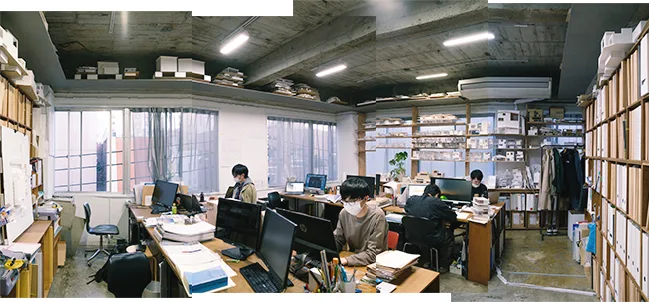
4階『UNEMORIArchitects』:tecoと畝森泰行建築設計事務所、それぞれの執務空間。開口上部に模型棚を設け、フロアを最大化した執務スペースとしている。

5階『LIBRARY』:雑誌のバックナンバーや専門書籍を集めた図書室。

6 階『SKY』:塔屋を利用したスペースで屋上の床から連続して屋外用デッキを敷き、テント張りのトイレと水回りを設けた。
設計で、生活の営みをチューニングする
―何でもできる部屋は意外と何もできなかったり、多目的な部屋は計画が難しいとも思いますが、どのように曖昧さを保ちながら有用性も担保するのでしょうか。
金野さん「難しいけれど、良い課題だと思って向き合っています。最低限、何を設えると、どのような意味が浮上するのか。プロジェクトによって、そのチューニングを試みています。
この事務所で言えば3、4階をオフィスにし、オフィスには水回りをつくらないと最初に決めました。トイレや手洗いには絶対行くので、水回りを共用部であるフリースペースの階に散らすと、みんながビルのなかを上下に動きます。動く途中に目にするもので、気が紛れたり、他に意見したくなったり、自分の仕事を客観視できたり。そういう余白を残しつつ、それぞれの階で異なる特徴が生まれるようビルを改修しました。」
―金野さんにとって音は空間にどのような意味を与えるのでしょうか。
金野さん「なんでしょう。私は常に少しの雑音が聞こえる状況の方が居心地良いと感じます。電車内で原稿を執筆するのも好きで、逆に無音や完全なノイズキャンセルなど自分で音をコントロールできてしまう環境は不安になります。常に、営みや息づくものを感じていると、リラックスできるのかもしれません。
例えば、地中海のまちはいくつも私の大好きな地域がありますが、青い海と潮の匂い、波の音、陽気な音楽、少しべたっとした風、オマール貝といった、音だけでなく五感を刺激する日常のリズムから、『ここにいて幸せだな』という感覚が生まれます。こうした生活の営みがつくる全体性のなかで、建築家として携われるのはそのごく一部かもしれませんが、風景をつくり、持続していくことに関わっていきたいなと思っています。」

取材・文/服部真吏 写真/田巻海