クラフトビールやクラフトコーヒー、クラフトチョコレートなど、近年「クラフト」という言葉を耳にすることが増えた。原料の調達や製造工程、ネーミングやデザイン──商品だけでないあらゆる接点において、一貫した作り手の哲学を貫く姿勢は、人の心を捉えて離さない。
2020年2月17日から20日にかけて福岡で開催された、Industry Co-Creation(ICC)サミットFUKUOKA2020。セッション「顧客に愛されるクラフト・ブランドをいかに作り上げるか?」には、「クラフト」を突き詰める面々が顔を揃えた。
登壇者はコエドブルワリーの朝霧重治氏とヤッホーブルーイングの井手直行氏、リストランテKubotsuの窪津朋生氏、住吉酒販の庄島健泰氏、白糸酒造の田中克典氏。モデレーターは、コーポレイトディレクションの占部伸一郎氏が務めた。
賛否両論あれど、理想の味を追い求める
──「乾杯!」
セッションは、クラフトビールの乾杯で幕を開けた。和やかな雰囲気の中、冒頭では各社がブランド作りにおいて大切にしている信念が語られた。
朝霧氏が代表を務めるコエドブルワリーは、埼玉・川越発のクラフトビールブランド「COEDO」を展開。地元産のさつま芋を使った「紅赤」など6種類のビールを製造し、国内はもちろん、アメリカや中国、ヨーロッパにも進出している。欧州最大のビール品評会ヨーロピアンビアスターアワードや、ビールのオリンピックと言われるワールドビアカップで入賞するなど、その実力は折り紙つきだ。

COEDO
COEDOを展開する上で、同社がコンセプトに据えるのが「Beer Beautiful(ビールはすばらしい)」。ビールのすばらしさを伝えるために、素材の良さを丁寧に引き出すことを心がけている。
朝霧氏「実はビールの個性を出すのは簡単なんです。インパクトのある香りを打ち出せば、それだけでオリジナリティのある仕上がりになる。でも私たちは、あえてそうしません。海外へ視野を広げる中で、日本の食は世界でもっともうす味で、素材の味を大切にしていると気づきました。日本人として、この思いを引き継いでいきたい。
そこで、ビールの色合いや香り、味わい、喉を通る刺激、鼻から抜ける余韻など、飲んだ人が、五感でビールの素材を感じられるように、いかにして最適なバランスを取るか――。日々、試行錯誤しながら取り組んでいます」
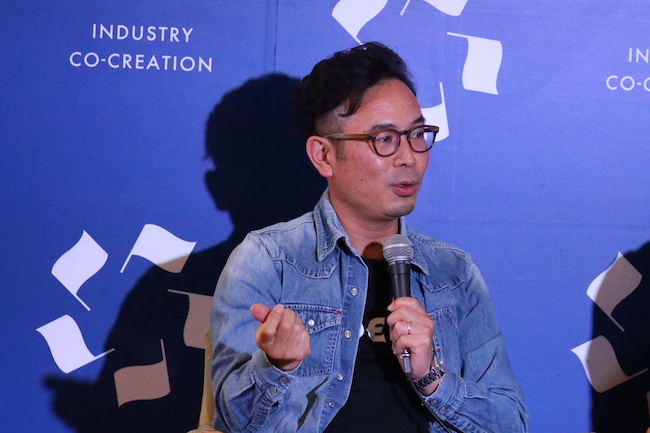
協同商事 コエドブルワリー 代表取締役兼CEO 朝霧重治氏
井手氏が社長を務めるヤッホーブルーイングは、クラフトビール「よなよなエール」をはじめ、様々なブランドを展開する。1997年の創業以来、自分たちが理想とする味の実現に向けて、小さな改善を積み重ねてきた。20年以上にわたってファンが違和感を感じて離れてしまうことがないよう、慎重に少しずつ味を進化させてきたのだ。

よなよなエール
しかし、ある時改善を重ねる中で作った試作品が、理想にかなり近い味を体現できたのだ。ただ、その味は従来の商品とは明らかに違いが分かる味わいであった。クラフトビールへの注目度も高まり、同社のファンも増えてきた時期。ビールの味が大きく変わると、従来の顧客が離れるリスクもある。同社は難しい判断に直面した。
井手氏「社内も賛否両論、私もだいぶ悩みましたね。でも、明らかに試作品の方が理想の味に近かったんです。考えた末に、お客様に告知をした上で味を大幅にリニューアルすることにしました。自分たちが理想に近いと思える味を、徐々にではなく、いち早くお客様にお届けしたかったんです」
結果、リニューアルが功を奏し、売上も大きく拡大した。自分たちのこだわりと、味を追求する姿勢を示したことが顧客からの評価につながっている。
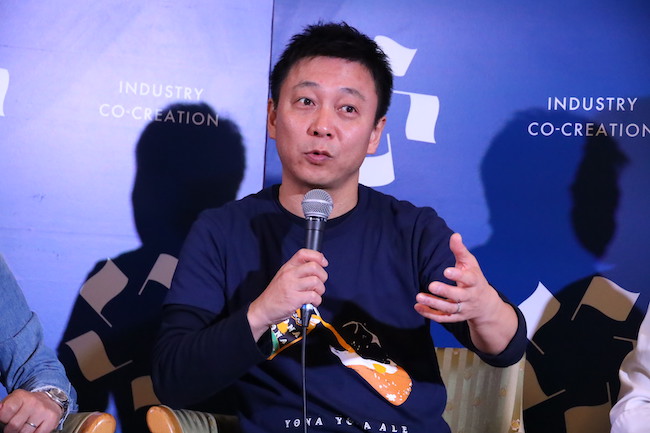
ヤッホーブルーイング 代表取締役社長 井手直行氏
地の利を最大限に生かしたモノづくりの魂
続いてマイクを握ったのは、リストランテKubotsuの窪津氏だ。同店は、全国に32のレストランを展開するひらまつが運営。「“今、九州で一番美味しい食材”に出会えるイタリア料理店」をコンセプトに掲げる。

リストランテKubotsu 料理長 窪津朋生氏
窪津氏は、ひらまつが運営する東京・代官山の「リストランテASO」を経て、天神店のオープンに合わせて異動。2018年には自らの名前を冠した「リストランテKubotsu」に改名し、「地産地消」をコンセプトにリニューアルした。
窪津氏 「福岡に来て、意外と地元の食材や伝統工芸を知らない人が多いことに気づいたんです。ですから、リニューアルを決めた時あらゆる面で“九州”を感じられる場を作り、この土地だからこそ味わえる伝統を新しい形で届けようと考えました」
その言葉を体現すべく、料理には窪津氏自らが訪ね歩いて調達した九州産の食材を、食器には佐賀の唐津焼を使用。店内の装飾やメニュー表にも、大川組子や博多織など九州の伝統工芸品があしらわれている。

リストランテKubotsu
同じく福岡に店舗を構えるのが、庄島氏が代表を務める住吉酒販だ。住吉酒販は、大正3年に卸問屋として創業。近年は全国の地酒を中心に飲食店への販売をメインとしていたが、2010年頃より小売にも注力。現在は博多本店、博多駅前店、六本松店、東京ミッドタウン日比谷店の4店舗を運営する。

住吉酒販 東京ミッドタウン日比谷店
同社は地酒の「届け方」に力を注ぐ。その姿勢は、店舗ごとに異なる顧客像にも現れている。
庄島氏「博多本店は飲食店さんやヘビーユザーの方々、博多店は観光客とライトユーザー、蔦屋書店の中にある六本松店のお客様はお酒に詳しくなくとも文化的な背景を楽んで下さります。日比谷店は豊かなライフスタイルにいかにお酒を取り込んでもらうかがテーマです。酒販店の役割は、ただお酒を仕入れて並べることだけではありません。造り手が届けたい層に適切に届けることと考えて、取り組んでいます」

住吉酒販 代表取締役 庄島健泰氏
最後は福岡の糸島市にある白糸酒造だ。創業165年を迎え、田中氏は8代目にあたる。10年前に、糸島産の山田錦のみを使った「田中六五」を庄島氏とともに開発した。

田中六五
白糸酒造の酒は、江戸時代から伝わる手法「ハネ木搾り」で造られる。酒米を発酵させた醪を手作業で搾る。多くの酒蔵が機械を導入する中で、昔ながらの手法にこだわっているという。
田中氏「石の重みを使うハネ木搾りは、非常に重労働です。しかし、あえてクラシックな要素を残すことで、味わいを作り、それが個性になっています」

白糸酒造 専務 田中克典氏
“おいしい”は大前提。主観と客観のバランス
次に語られたのは、それぞれの味のこだわりと顧客の声のバランスだ。ブランドを作る上で、自分たちの哲学は欠かせない。だが、こだわりを主張しすぎても、顧客が受け入れてくれるとは限らない。
朝霧氏は、自己満足に陥らないために、公正かつ客観的に自分たちの味を評価する場が必要だと言う。そのために活用するのが、コンテストだ。
朝霧氏「おいしくない商品をお客様にお出しするなんて、失礼なことはできません。味を磨き続けるためには、『プロの目から見て、どの位置にいるのか』を確認する必要があると私たちは考えています。ですから、チェックの意味も込めて、コンテストへの出品は欠かしません。
受賞がきっかけで認知度が広がり、『COEDOをうちの国にも輸入したい』と、海外からも声をかけてもらえるようになりました。ご縁がつながり、現在は25カ国に展開できています。味の客観性が、結果的にビジネスの拡大にもつながっているんです」

だが、同じお酒でもビールと日本酒ではその受け入れられ方も異なる。田中氏によると、日本酒の場合、コンテストの評価は一般の人の注目度にはそれほどつながらないという。その状況下では、造り手側の「自身の納得感」こそが酒造りのカギを握る。
田中氏「シンプルに言うと、自分が好きか嫌いか、日本酒に対してどんな考えを持っているのかを大切にしなければいけません。僕にとって『商品』は、自分の舌の感覚や考えを体現する場。常に自分にとっての正解を模索し、その解をお客様に示しつづけることが、自分にできる日本酒造りだと考えています」
一方、ビールを扱う場合、井手氏は「自身の納得感や客観的な視点は欠かせない」とした上で、ビジネス感覚の重要性を訴える。ターゲット顧客に応じた観点を重視している。誰の意見を重視するか、製品ブランドと届けたい層に合わせて変えているそうだ。
井手氏「例えば僕と同世代の40〜50代に届けたい製品の場合は、自分=ターゲット顧客として意見をガンガン伝えていきます。でもヤッホーでは、20代や30代の若者や女性に向けたビールも作っている。その場合、僕の意見は参考にならないんですよね。僕の我を通してしまうと、40〜50代のおじさん向けビールになってしまう(笑)。マーケティング的な視点を持って、ターゲット顧客の声を聞きながら製品をつくっています」
作り手の熱を届ける、目利きとしての役割
では、こうした顧客の声と作り手の哲学が込められた商品を「届ける」役割を担う面々は、何を考え顧客と向き合うのか。語られたのは、純粋な“美味しさ”だけにとどまらない顧客が感じる価値や文脈の大切さだ。
九州各地から集めた魅力的な食材を調理し届ける窪津氏は、おいしさを届けていく上で、“舌”で味ってもらうだけでなく“頭”で感じてもらうことも大切にしている。頭で感じるおいしさとは、「食に関する知識や接客、店舗の雰囲気」といった付加価値を指す。
窪津氏「料理に使う野菜を誰が、どのように育て、どこにこだわりがあるのか。それをお客様に伝えられるかどうかで、料理の価値も変わってきます。その付加価値を飲食店や小売店などの人間が理解して初めて、真のおいしさをお客様に届けられると思うんです。
しかし今、適切な届け方ができているのかというと疑問に感じます。誰が作っているのかが分らない食材を使う料理人が少なくない。この状況は変えていきたいですね」

庄島氏は、酒販店の役割を「作り手側から見た“コンテスト”のような存在」であるべきだと語る。商品を右から左に販売するだけでなく、顧客の代わりになって目利きをするという姿勢を貫きたいと考えている。
庄島氏「近年、メーカーやブランドが中間業者や小売店を介さずにお客様と直接つながるようになりました。その背景には、間にいた我々がお客様に迎合しすぎて、『求められるものを置く』ようになったこともあると考えています。だからこそ、僕たちは商品の価値を見極める目を養わなければいけません。僕たちが選んだものは良いものだ、という認識をお客様に持ってもらうことが必要だと思います」
窪津氏と庄島氏の話を受けて、朝霧氏は作り手の立場からも目利きの重要性を語った。
朝霧氏「自分たちが作る商品には自信を持っていますが、最後“頭”で感じてもらう部分としてブランドとしてのこだわりを届けるためには、飲食店や小売店の力が欠かせません。そのような関係性は大切にしていきたいですね」
井手氏もまた、商品のバックグラウンドを伝える重要性を感じていた。
井手氏「もちろん、おいしさなどの機能面が絶対的に良くないといけないですが、機能面だけだと消費者にとって価値がわかりにくい。そこに、デザインやネーミングなどクリエイティブな要素を加えることで、ファンが支持をしてくれるきっかけになります。ただ、それだけでも競争からは抜け出せない。そこでさらに必要になってくるのがストーリー。こだわりや知識といったバックグラウンド。これらが揃って初めて、お客様に愛され続けるクラフトブランドが育まれていくのではないかと思います」
大切なのは、心のあり方。クラフトが届ける顧客体験
商品にこだわるだけでなく、バックグラウンドを伝えることが、顧客に愛され続けるクラフト・ブランドにつながる。セッションの終盤では、それぞれが今後どのようにビジネスを発展させ、顧客とのつながりを生み出していくかが語られた。
窪津氏が考えるのは、顧客と共に市場を作る必要性だ。
窪津氏「僕たちのブレないところは、誰かのために働いているところだと感じました。食もお酒造りも、食べる人や飲む人のためを思っていないとできない。ただ、こうした背景にある思いを自分たちの中にしまっているだけではいけません。お客様にも理解してもらい、みんなで市場を成長させる意識が欠かせないと思います」
井手氏と田中氏は、クラフトだからこそ届けられる作り手のぬくもりに言及する。
井手氏「今の時代は、AIなどのテクノロジーが目まぐるしく発達しています。そんな時代に逆行するかもしれませんが、ものづくりを通じて届けられる想いや、人々の幸せの追求を大事にしつつ、産業を盛り上げていきたいですね。」
田中氏「「アルコールは、生活必需品ではないかもしれません。それでも、『この商品に出会えてよかった』とお客様が思える、人の気持ちを満たすような価値が届けられればと思います」
庄島氏、朝霧氏は自らの信念を中心に据えた上で、時代の流れと顧客の声を柔軟に取り入れる大切さを語った。

庄島氏「僕は普段、モノづくりに携わる人たちと接していますが、彼らの仕事への取り組み方に心から尊敬しています。自分なりの信念を持ちつつも、柔軟な姿勢を忘れない。この魂を取り入れることは、受け手の生活にも彩りが増すことにもつながります。橋渡し役として、そのきっかけを届けていきたいです」
朝霧氏「僕たちは100年、200年続く、地域で愛される酒蔵のような存在になりたいと考えています。作り手もお客様も時代に合わせて変わっていく。Beer Beautiful、ビールは素晴らしいという思いを大切にしながら、時代の変化とお客様の声を捉えて成長し続けたいです」
人々に愛される──。そう聞くと、常に顧客の声を優先する印象を抱く人がいるかもしれない。だが今回、登壇者の面々から感じたのは、いわば「しなやかな信念」のようなものだった。
芯となる「哲学」を大切にしながらも、届ける顧客にも柔軟に寄り添っていく柔軟さ。その絶妙なバランス感覚こそが、愛されるクラフト・ブランドを生み出すことにつながるのだろう。
文/藤原梨香 編集/小山和之 写真/ICCパートナーズ提供




