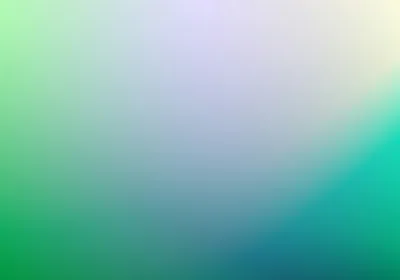“体験”は色々なフィールドでアップデートされている。
それを生み出すのは、時代の空気を吸って新しい表現を試みるクリエイターたちだ。
その中でも、新鮮な試みで話題を呼んだ集団がいる。俳優としての活動の一方、ダンサーとしても数多くの舞台を踏む森山未來と、幅広いコラボレーションで異彩を放つ振付師・ダンサーの辻本知彦。2人を軸にした9人のメンバーからなる「きゅうかくうしお」である。
彼らは2019年12月に、2年半ぶりの公演『素晴らしい偶然をちらして』を終えたばかり。
ここでは森山と、普段は裏方としての技術者でありながら今回はメンバーとして出演した中原楽・松澤聰の2人に、この公演を振り返りながら「体験の届け方」を語ってもらった。

きゅうかくうしお(写真:左から中原楽、森山未來、松澤聰)
2010年、辻本知彦と森山未來により立ち上げられたユニット。現在のメンバーは、踊り子の2人に加え、河内崇(舞台監督)、吉枝康幸(照明)、中原楽、松澤聰、矢野純子(宣伝美術)、村松薫(制作)、石橋穂乃香(制作助手)の9名。コンスタントに築き続ける関係性も表現の一環とし、クリエイションの過程を、HP〈 https://kyukakuushio.com 〉にて随時公開している。
9人の身体と、コミュニケーションが舞台をつくる。
──「きゅうかくうしお」は森山さんとダンサーの辻本知彦さんが起ち上げたユニットですが、最新公演『素晴らしい偶然をちらして』では制作や技術スタッフも含むメンバー9人がフラットな立場からクリエイションに関わる体制となりました。この経緯から伺えますか。
森山氏「もともと知(辻本)さんは身体ひとつで彼自身の世界を完璧に成立させられるダンサーなんです。そんな彼とどう対峙するかというプレッシャーが僕にはあって、『じゃあ、例えば身体のスペシャリストであれば、声だって声帯の振動だよね』といった会話の流れからセリフや芝居のアプローチをしかけてみたり。
そういう対話を重ねる中で、過去2回の公演も単なるダンスパフォーマンスにとどまらないかたちになっていたんですが、今回、メンバー全員がクリエイターとして並列的に名前を連ねることで、さらに立ち方が変わったというか。
そうなると知さんと僕だけの対話で世界を完結させる必要がないんですよね。もっと言えば、僕らの身体も作品全体にとってツールの一つにすぎない、ということが明確になりました」

2019年11月22日から12月1日にかけて、横浜赤レンガ倉庫のホールで開催された、『素晴らしい偶然をちらして』公演写真。(撮影:菅原康太 写真提供:きゅうかくうしお)
──公演では非ダンサーのメンバーたちもステージに上がり、さらにクリエイションに関わるメールのやりとりといったコミュニケーションも観客の前に提示するという試みがされていました。
森山氏「いわゆる『裏方』の人たちを舞台に上げることが目的ではないんです。作品に至るまでのコミュニケーションや、誰がどんなアプローチで関わっているのかを可視化するためのよい方法を探った結果、そのまま舞台に乗せたら、面白く伝わるんじゃないかなって」
──それぞれ中原さんは音響、松澤さんは映像というポジションですが、その役割で観客の前に立つということはあまりない経験ですよね。
中原氏「役割としてなら、音響だけでなく、舞台監督であったり、テクニカルディレクターであったり、公演や作品ごとに様々なポジションを担当することは、これまでもあったんです。ただ、舞台に上がるというのは別ですよね。『それはいったいどういうことなんだろうな』っていうのはちょっと考えました」
森山氏「楽(中原)ちゃんは、『上がりたくない』という意志が身体から滲み出てたよね(笑)」
中原氏「でしたね(笑)。ただ、悩みはしたんですけど、でも、今回の作品には上がる必然性を感じることができたので」

森山氏「そのほうが信用できるんですよ。無理に何かをしようとしてギクシャクする身体よりも、何もしようとしない身体のほうがナチュラルで説得力があったりする。テクニックだけで何かを表現するよりも、自分の中にあるものと向き合ってどう対応するかということのほうが重要だし、結果的にそれがテクニックにも反映されるっていうことを、知さんもずっと言っていましたね」
松澤氏「逆に僕はそこが難しくて。むしろ舞台に上がること自体はまったく抵抗なかったんです。『舞台上でカメラを回せれば、面白い絵が撮れるな』という感じで。でも、その『自分の中にあるものと向き合う』という感覚が掴めずに苦しんだ時期がありましたね」

中原氏「ソウくん(松澤)が辻本さんに言われていたことで印象的だったのが、『ソウはいつもおしゃべりなのに、撮影の時だけ黙るのはどうしてなんだ?」っていう」
松澤氏「どうしても技術的なことを考えてしまうんですよね。『俺がしゃべってたら、後で映像編集しづらいよな』とか、そもそも『俺は被写体じゃないし』とか。そういう『裏方』的な意識のスイッチを入れていることを見抜かれたんでしょうね」
森山氏「けっしてそのスイッチングが悪いわけではないんですよ。ただ、普段のソウくんのあり方のほうが面白いのに、撮影した映像では小さく収まってしまっていて、『それは違うんじゃないの』って」
松澤氏「だからといって『俺にいったい何が出せんねん』と悩んでしまって、映像を撮れなかった日もありました。でも、ある瞬間に、『俺は踊れないけど、俺が動くこともすべて“舞踏”や』と思うことにしたら、吹っ切れたんです。カメラを回すのだって舞踏だと。その気持ちの切り替えができてからは、だいぶ迷いがなくなりましたね」
中原氏「その感覚はわかる。私は普段、自分で音を作ることはしないんです。自分の仕事はあくまで音響だと思っているので。ただ、今回、辻本さんが思いついたメロディを私が音に起こした曲があって、最初打ち込みで作ろうとしていたんですけど、どうにもしっくりこなかった。で、気づいたら自分で歌うはめになっていたんです(笑)。そしたら、なんかしっくりきたんですよね」
“鑑賞”をいかに“体験”にしていくか。
──今回の作品では愛知と香港で滞在制作も行っていますね。
森山氏「関わっている人たちのダイアログ(対話)がそのまま舞台に反映される作品だと思っていたので、それを積み上げる意味でも、普段とは別空間でいわゆる合宿的な稽古ができたのは、非常によかったです。仲がいいだけではなく、ちょっとした軋轢が生まれる瞬間もある。そういう時間すべてを通して、僕らの作品の色みたいなものが見えてくるというか」
中原氏「私、協調性はあまりないタイプなんですけど(笑)、ある時間を一緒に過ごすことで生まれる信頼感ってあるんだなと思いましたね」
松澤氏「メンバー全員、面白かったり、人間的に素晴らしいことはわかっているんですよ。でも、普通に生活する時間を持つことで、その先が拓けてくる。それぞれ作業をする中でポコポコと湧いてくる思いつきがあって、その日の終わりに集まって、『こんなの出てきたよ』って付箋に書いて貼っていくんです。自分たちの過ごした中から出てきたものを、自然と紡いでいく感覚がありました」

この公演は、メンバーによる2年間のコミュニケーションの中でも、特に2回のクリエイションでの出来事を多く題材とした。5月には愛知・幡豆の田んぼで、公演直前の11月には香港で実行。幡豆での様子は、メンバーたちの記録映像と共に「きゅうかくうしお」HPで公開している。(写真提供:きゅうかくうしお)
──そうやって生まれたものを観客に届けるにあたって意識したことはありますか。
森山氏「いわゆるプロセニアム(額縁)形の劇場での公演だと、観客もどうしても『鑑賞する』という感じになってしまう。その構造を崩して、より能動的に観てもらおうという作品自体は、すでに存在しています。観客が『わかりにくいな』と感じた時に、自分の中の想像力で楽しめるか、シャットアウトしてしまうかで分かれる。前者にするためには、『鑑賞』を『体験』に繋げていく必要があると思うんですよね」
松澤氏「自分で掴みにいくと何かが見えてくる、みたいな」
中原氏「なので、『受け身でいるだけでは、あまり面白くないんじゃないですか? どうですか?』という気持ちで私はやっていたかな」
森山氏「特にダンスの場合、言葉もない抽象的な作品をいきなりパッと観るわけじゃないですか。これがいわゆる台本のあるお芝居だったら、少なくとも言葉という情報があることで、ある程度は背景を知る手がかりとなる。でも、ダンスはどんな背景やプロセスがあるのかもわからないまま、最後の完成形を観せられるような感覚だと思うんですよ。そこを一回、解体してみたかったんです」
情報が行き交う時代に、表現していくために。
──今回の公演では、舞台上で飛び交うコミュニケーションはすごく個人的で、かつライブ感に溢れています。しかし一方で、全体から受ける手触りは誰にでも身に覚えのあるような普遍性、つまり「ポップさ」があるのが印象的でした。
森山氏「それで思うことがあって。いま、誰もがとてつもない量の情報の渦に常にさらされているじゃないですか。一昨年(2018年)、中園孔二という2015年に25歳で亡くなった画家の個展を横須賀で観たんです。
彼の作品は背景がとにかく過多なんですよ。彼は絵を描く前に、何日か山や海に篭ります。電波の届かないようなところで過ごしてから、都会に戻ってきて、情報の波に一気にまみれながら描いていたらしくて。ある意味チャネリング(霊媒)のようなやり方ですよね。
それって、自分の自我というものをこの情報溢れる渦の中でどう屹立させるのか、という模索にも感じられました。今回の『きゅうかくうしお』のドキュメンタリーな作り方や、SNSやメディアの使い方にも、それに近いものがあったかもしれない」

──それは、そのままコンテンポラリーダンスから大河ドラマまで遍在する森山未來のイメージにも通じるものがありますね。
森山氏「ははは、メディア過多(笑)。そういうスタンスで自分というものを繋ぎ止めている感じもしますね。いろんな写真を組み合わせて一つの写真に見せるフォトモザイクってあるじゃないですか。あの感じ。今回の『きゅうかくうしお』は、まさにそうですね。各々が個人で動いて完結するぐらいの感覚なんですけど、それを混ぜ込むことによって生まれる化学変化を見せたかった」
松澤氏「ああ、そのイメージあるなぁ。『きゅうかくうしお』をやることで、結局自分は、違う自分にはなれないけど、いまの自分をもっと信頼して、どんどんクリエイションしていこうと思えましたね」
中原氏「結局、自分のできることをやるだけなんですよ。でもその組み合わせ方や混ぜ方で何かが変化する。私にも確実に訪れた変化が一つあって、それは、普段はたとえ共同作業でも、現場でオペレートしている時に孤独を感じるんです。でも今回は、それを感じなかった。果たしてそれがいいことなのかどうかはまだわからないですけど」
森山氏「孤独を感じている時のほうが、外界に対してセンシティブではあるからね」
中原氏「そうなんです。常にクールに俯瞰することを意識しているんですけど、今回そういうポジションをとることができなかった。自分も舞台上の体験のただ中に身を置いていましたね。私にとっては新しい感覚で、勉強になりましたね」
──「きゅうかくうしお」の今後は?
森山氏「知さんは『10年はやらなあかん』と言ってますね。厳密に10年かどうかは別として、彼は続けていくことに意味を見出しているんだと思います。僕もまったく同じ考えですね。また、かならずやりたいと思います」

PROFILE
森山未來│Mirai Moriyama
1984年、兵庫県出身。幼少時より様々なスタイルのダンスを学ぶ。99年に舞台デビューの後、映画、テレビドラマ等、俳優としてのキャリアを積む。2013年秋には文化庁文化交流使として1年間イスラエルに滞在しダンスカンパニーに所属し、ヨーロッパ諸国にて活動。ジャンルレスな表現者としての在り方を模索中。自身の最近の体験としては、書籍『サピエンス全史』(ユヴァル・ノア・ハラリ著・16年河出書房新社刊)に感銘を受けた。
中原楽│Raku Nakahara
千葉県出身。音楽、ダンス、パフォーミングアーツの分野で音響や技術統括を軸に活動。フジロックなど夏フェスでのサウンドデザインも手がける。最近心を動かされた体験は、ドバイの名物噴水ショー「ドバイ・ファウンテン」。予想外のスケールに、恥ずかしながらはしゃいでしまった。
松澤聰│Sou Matsuzawa
大阪市出身、映像作家。2015年エルサレム、ベツァレル美術デザイン学院卒。愛知・幡豆(西尾市)と東京を拠点にビデオアート、ビデオダンス、ドキュメンタリー、MVなどを制作している。銭湯好きで、特に電気風呂と相性がよい。神楽坂の「第三玉の湯」で入った電気風呂があまりに激しく一瞬で身体の凝りが整ったのが、最近のホットな体験。
聞き手・構成:九龍ジョー 撮影:上樂博之 編集:BAKERU