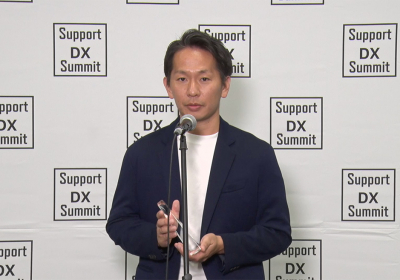“モノ消費からコト消費”の時代、企業とユーザー、ユーザーとユーザーが相互交流する「コミュニティ」が、ビジネスに活かされている。そこで気になるのは、コミュニティの熱量を高め、継続的に盛り上げていく方法だ。
「ICCサミットKYOTO 2019」の「高い熱量を持つコミュニティはどのようにして生み出されるのか?」には、B.LEAGUE葦原一正氏、ヤッホーブルーイング井手直行氏、コルク佐渡島庸平氏、(有)柴田陽子事務所/BORDERSatBALCONY㈱ 等(2019年11月現在)長瀬次英氏、モデレーターのリンクアンドモチベーション麻野耕司氏と、多様な分野で熱量の高いコミュニティを主宰する登壇者が集った。
コミュニティの作り方や、拡大させるために大切なこと、そしてコミュニティの温度の上げ方などについて登壇者が熱く語り、満員の観客からも多くの質問が飛ぶなど、インタラクティブに繰り広げられた当セッション。その内容を紹介する。
ビジネスに活きるのは「どんなコミュニティにしたいか」を決めるておくこと
「コミュニティが重要」とはよく言われるが、いざ立ち上げようとするとき、具体的に何から始めればいいのだろうか。先人たちがコミュニティづくりの出発点を振り返る。
長瀬氏「私はこれまで、インスタグラム・ジャパン、日本ロレアルなど様々な企業さんにて、デジタル領域のコミュニティーづくりに関わってきました。すでに事業はあるが、コミュニティがない場合、自分たちがつくりたいコミュニティと親和性のあるコミュニティを巻き込むことが有効です。
インスタグラムでは、それまではメンバー内でアナログないしPC画面等で写真を見せ合っていたカメラメーカーの写真クラブに『皆さんそれぞれのスマホに入ったアートギャラリーを皆に見てもらいたくないですか?』『世界中の人に輪を広げませんか』『そのほうが面白くないですか、写真の撮りがいがありませんか?』と提案しました。インスタグラムのコミュニティを大きくするために、プラットフォームと親和性の高い既存のカメラのコミュニティを巻き込んだのです」

(有)柴田陽子事務所 CSO、BORDERS at BALCONY㈱ CEO、Visionary Solutions㈱ CEO、PENCIL&PAPER.COM㈱ CEO(2019年11月現在)長瀬次英氏
井手氏「うちの会社では、ファンイベント『よなよなエールの超宴』を開催しています。昨年は5,000人が、この秋には1万人規模のイベントを開催する予定です(編集部注:秋のイベントは台風により中止)。ありたがいことに、『ヤッホーのファンイベントをまねしたい』と代理店に相談している企業がある、なんて噂話を聞いたことがあります。しかし、似たようなイベントを開催しても、本質的には全く違うものになるだろうと思っています。
私たちのファンイベントは、スタッフみんなで企画・運営しているんです。この『自分たちでやる』のがとても大事。もし、代理店に丸投げしていたら、自分たちの熱量がコミュニティに伝わらないと思います。目の前でファンが喜ぶ顔が見えるので、結果としてスタッフのモチベーションアップにもつながります」
スタートさせたコミュニティを拡大させるためには、どのような施策が必要だろうか。キーワードになったのは「誘い合う」ことだ。
佐渡島氏「ヤッホーブルーイングさんのコミュニティ拡大を見て思ったのは、そもそも『コミュニティ』と『ファン』は違うということ。コンテンツを楽しんでいるだけの人はファン。ファン同士が交流しているのがコミュニティ。初めは小さくても、コミュニティに属する人たちが、マイクロインフルエンサーのように、どんどん誘い合って大きくなるんです。
これをプロモーションという目線で見ると、マスメディアを使わなくても、顔の見える人同士の情報交換で、事業が広がるということになります。僕の会社では200名ほどが所属する “コミュニティ運営を学べるコミュニティ”『コルクラボ』を運営していますが、例えば新人漫画家の作品を広めていく過程で、コミュニティの力に助けてもらっています」

コルク 代表取締役 佐渡島庸平氏
葦原氏「確かに『誘い合う』はキーワードだと思います。コミュニティを考えるとき、量はもちろん、質も非常に重要。B.LEAGUEには、熱心なチケット会員、ファンクラブ会員がいますが、ファンをよく観察すると大きく分けて2タイプがいます。好きなものを人に教えるタイプと、自分だけのものにしたいタイプです。
好きなミュージシャンが急に売れはじめると、気持ちが離れていくファン心理もありますよね。ビジネス視点で考えると、そんな人ばかりが集まったコミュニティにはメリットが少ない。そうならないために『応援・拡散してくれる文化』を育てなければならない。
コミュニティをビジネスに活かすには、運営者が『どんな文化を形成したいか』をはっきり示さなきゃいけないと思います。周囲に積極的に勧めてくれるようにメッセージを伝えるなど、カルチャーを醸成する必要があります」
運営者の熱を直接コミュニティに届ける
こうして育ちゆくコミュニティを次のステップに進めるには、コミュニティの「温度」を上げる必要がある。そのアイデアの一つが、運営者も含めたコミュニティ内の交流の活性化だ。
井手氏「私たちのファンイベントでは、初対面同士が仲良くなれるように、いろいろな仕掛けを用意しています。例えば、名札を用意して全員がニックネームで呼び合う。共同作業が必要なコンテンツでスタッフもファンも一緒になって楽しむ。こうした施策を続けていると、ファン同士で自主的に二次会を企画したり、イベントで仲良くなった人同士で後日集まったり、更にはイベントで知り合ったカップルが結婚したり、ということも起きました。イベントのアンケート結果からも非常に高いお客様満足度をいただいています。
良いコミュニティが築けると、お客さまが助けてくれることもあります。イベント規模が1,000人から4,000人に増えたときに、トイレが足りない、フードに大行列……など、多くの課題が浮き彫りになりました。4,000人に対応できるスキルを私たちが持っていなかったのです。このとき『どのトイレが何分待ち、向こうのトイレの方が空いているよ!』と情報を他のお客様へ共有・整理してくださるファンが現れました。アンケートでも『未完成だからこそ、応援しがいがある』とありがたい声をたくさんいただきました」
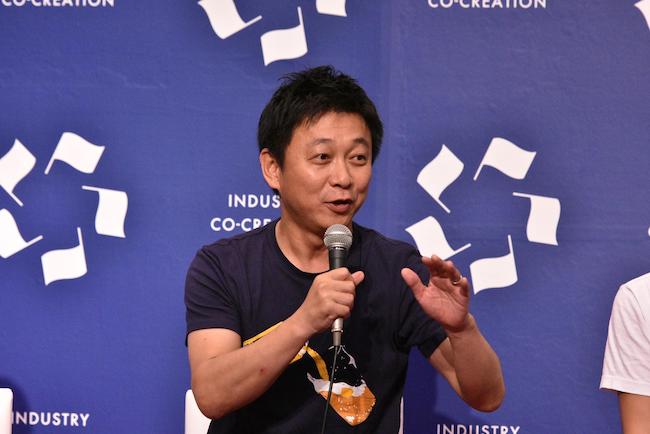
ヤッホーブルーイング 代表取締役社長 井手直行氏
長瀬氏「熱量は高い方から低い方へ流れていくんです。コミュニティをつくるときには、発信源が高い熱量を持っていないといけない。スタッフが、どれだけそのブランドやサービスを愛しているか。それがコミュニティに伝わり、全体の熱量が上がっていく。ヤッホーのファンイベントの成功は、プロダクトを愛する自社のスタッフが大勢いることも関係しているのではないでしょうか」
同時に、この高い熱量を「見せる」テクニックで、再帰的に熱量を高めることもできるという。
葦原氏「大事にしているのは『空気をつくる』ことです。スポーツビジネスでは『満員にする』ことが大切だとよく言われるんですが、誤解を恐れずに言うと、私は『満員』よりも『満員感』を出すことに注力しています。例えば、チケットの種類を細かく分けて、完売・即売を増やしていく。入場者数だけでなく、満員の試合がいくつあったかを伝える。バスケの本場のアメリカではスタジアム自体を小さくして、どんどん熱狂的なコミュニティを育ています。もちろん嘘はいけませんが、コミュニティの温度の高さを意識的に見せていく工夫はアリだと思います」
佐渡島氏「ヘッドスパ専門店『悟空のきもち』を知っていますか。日本一予約が難しい店と言われてるんですが、ウェブサイトにキャンセル待ちの人数を出しているんです。その数はなんと50万人以上(編集部注:2019年10月現在『東京 原宿神宮店・銀座店の全4店舗のキャンセル待ち合計は、511,095人』と表記されている)。利用すると次の予約を取れるんですが、それを逃すとキャンセル待ちの人に予約権が移るので、1回行くとやめられないんです(笑)。販売しているオリジナルの布団や枕も全然買えません。どのくらい熱量が高いか、しっかりと見せることで、更に熱量を上げていけるはずです」
「突き抜けた」コンテンツの力で、コミュニティの熱量を昇華させる
熱量の高いコミュニティを維持していくためには、コミュニティ内に提供するコンテンツ、メッセージの内容も大事な要素だ。
葦原氏「突き抜けたものをつくって、コミュニティを感動させることが大事だと思います。芸人の江頭2:50さんは『1クールのレギュラーより1回の伝説』と言ったそうです。とにかく一点突破で、濃くメッセージを届けたいです」

B.LEAGUE常務理事 葦原一正氏
井手氏「劇団四季のミュージカルってとてもレベルが高いですよね。私も昨年初めて観に行って感動したんですが、さらに驚いたのが、リピーターがそれなりにいるってことなんです。『ここで拍手する』『ここで声を出す』など客席側の『合いの手』があって、私の感覚では半分くらいの観客がそれを知っていました。演目は一緒でも演者が違う、と。その違いを楽しみに来ているそうです。この『同じだけど違う』はヒントになりそうだと思っています」
長瀬氏「同じものを見ているようで、違いがある。『何回も見ていくことで気づく魅力』に、気づけると『違いが分かる人』になる。違いを分かり合う人たちのつながりが生めたら、そのコミュニティはかなりのレベルまで昇華していると思います。B.LEAGUEだって、同じチームであっても、前の試合・今日の試合、それぞれの違いを理解し、楽しめる人がコミュニティをつくっているはずです」
「ビジネス視点」のコミュニティには、自然発生的に生まれるコミュニティとは違うところもある。その一つが、意識的にビジネスの役に立つように育てる必要があることだ。コミュニティが生まれたあとも、熱量を高め、維持することが不可欠となる。マスにも負けない媒体の役割を果たすことも、ピンチのときの救いの手になることもあるコミュニティ。これからの時代の企業は、その力を最大限、引き出すことが求められるだろう。
執筆/吉田瞳 編集/葛原信太郎 撮影/ICC