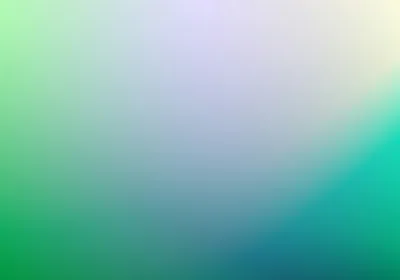「土産」はその土地ごとの進物として、昔からなによりの贈りものとされてきた。それが「手土産」となるとまた異なる“かろみ”がある。ビジネスの挨拶にもカジュアルな間柄のお礼にも……私たちの日常においてとても身近な習慣。そんな手土産に縁深いという「一冊の本を売る書店」森岡書店の森岡督行さんと、手土産のまさに定番といえる洋菓子の老舗・ウエストの取締役である野老山薫子さんに、銀座の街と手土産をめぐってお話してもらった。
(この記事は2022年12月14日(水)に発売された『XD MAGAZINE VOL.06』より転載しています)
出会いの喜びを分かち合う贈りもの

手土産の「和久傳」のすっぽんの煮こごりを渡す森岡氏。
森岡「早速ですが今日は『手土産』がテーマということで、薫子さんに手土産を持ってきました!」
野老山「わあ、ありがとうございます」
森岡「京都の料亭『和久傳』の手土産のシリーズで、すっぽんの煮こごりです。薫子さん、なにが喜ぶかなあと考えまして、いろいろな美味しいものに触れていらっしゃるかと思うのですが、すっぽんはあまり頻度が少ないのではないかなと」
野老山「すっぽんですか、すごい!」
森岡「すっぽんって普段あまり家庭では出ませんよね。実はすごく手軽で食べやすくて、コラーゲンとか栄養も豊富。朝に英気を養うでも、夜に一日の疲れを癒やすのにも良さそうです。ご家族は多くて5人ぐらいではないだろうかと予想して、一応5袋入っております」
野老山「そこまで考えていただけるなんて……。嬉しいです!」
森岡「喜んでくださる場面を想像しながら選ぶのは、自分も楽しいんですよね」
野老山「森岡さんはお仕事柄、お手土産をいただくことも多いのでは」
森岡「森岡書店では年間で50回ぐらいの展覧会を行っているんですけれども、そのときは著者さんと店頭に一緒にいることも多くて。そうすると、著者さんに手土産を持ってきてくださるお客様がよくいらっしゃいます。やはりその方にとって思い入れのある著者さんである場合が多くて、自ずと手土産も全力投球できてくださる。毎週毎週、そういう様々な手土産の現場の傍にいて、お裾分けしてもらっているという不思議な立ち位置です。ときどき中身はなにかと透視しようとしたりして。結構面白くて、当たると嬉しいんですよ」
野老山「ふふふ。お手土産にも流行というものがあるのでしょうか」
森岡「そうですね。たとえば、麻布十番『豆源』さんの豆菓子や、各地のたい焼きを持ってきてくださる方なども多いですね。『甘いものはたくさんいただくだろうから』と柿の葉寿司というのもありますね。
あとはやはり、私が好きだということもありますが、ウエストさんは多いですよ。リーフパイやダークフルーツケーキ、あれはもう、みんなが嬉しいですよね。場が沸くといいますか。そういう体験から、ウエストの焼き菓子は万人の心に入っていくということを学びました」

野老山薫子(ところやま・かおるこ)
1947年にレストランとして創業し今も銀座の街で人気を誇る「株式会社洋菓子舗ウエスト」の取締役。商品開発・企画・営業を担当。
野老山「それは嬉しいです。手土産って、贈る相手のことを考える時間があるということ。とても豊かな時間だと思います。受け取る側も『自分のことを思って選んでくれたんだな』ということが伝わると一層嬉しいですよね。
先日、久しぶりに会う友人が家に遊びにきてくれたのですが、絵本を2冊持ってきてくれて。絵本を贈っていただくことってなかなかない経験だったのと、その本の内容が素晴らしくて、『うちの子の教育のことまで考えてくれているんだなあ』ってすごく嬉しくなりました」
森岡「素敵です! 薫子さんはご自身が手土産を選ぶときは、どんなふうに選ばれていますか」
野老山「最近周りでお子さんが産まれることが多く、お手土産にベビーグッズをお贈りすることが多いのですが、そのときに、お母さんのためのお手土産もプラスしてお渡ししています。私も子どもが小さかった頃は、パッとつくれるインスタント食品を、栄養の偏りを気にしながらも食べるような感じで……。そういう経験から、無添加で罪悪感のない、それでいて手軽に食べられるインスタント食品を見つけてはお手土産にしています」

森岡督行(もりおか・よしゆき)
1974年、山形県生まれ。一冊の本を売る書店「森岡書店 銀座店」店主。展覧会の企画協力や連載、著書も多く、近著に『ショートケーキを許す』(雷鳥社、2023年)、『800日間銀座一周』(文春文庫、2022年)など。
森岡「優しい……。すごくいいですね! 手土産を選ぶときには、自分が楽しむというのが大切だなと思っています。選べる幸せというのがありますよね。ちょっとその人のことを考える。『ちょっと』というのが手土産のポイントで、少しぐらいがいいんですよ。あまり深く考えるのではなく、ほんの少し。それが尊い。
今日もこうやってご縁をいただいて、この日この場所でお会いすることって、突飛ながら宇宙のはじまりから考えるとすごい確率です。手土産って、そんな出会いの喜びを分かち合うことでもある。そのことは頭の片隅に置いておきたいなと思います」
銀座の手土産と美意識

森岡「薫子さんは贈る側、贈られる側という立ち位置に加えて、『つくる側』でもありますよね。ウエストのお菓子は、できるだけ添加物や保存料は使わずにつくられているとお聞きしたことがあるのですが、そういったこだわりは意識されていらっしゃるのでしょうか」
野老山「かなり意識していますね。新商品を考えるときも、素材の味がまず第一で、それを壊さないよう、なるべくシンプルに、どなたにも召し上がって頂けるようにというのが方針としてあります」
森岡「それがいいですよね。ウエストの特徴のひとつに、季節ごとのお菓子がありますよね。マンゴーのショートケーキとか、いちごのショートケーキも、その季節にしかないんです。私、ウエストのショートケーキが大好きで、携帯の待ち受け画面にしているんですよ。(待ち受け画面を見せる)」
野老山「本当だ!(笑)。いちごのショートケーキは多くのお店では定番として、通年でお出ししていることが多いと思うのですが、ウエストでは冬にしか出していなくて。季節のケーキは、その果物が一番美味しい時季にしか出さないと決めています。メニューに並ぶのが1週間ぐらいのときもあるので、あまりに短くて驚かれることもありますが、お客様が召し上がったときにがっかりされないようにと思っています」

季節ごとに異なる商品が並ぶ、銀座ウエストのショーケースは、まさに手土産の宝庫。
森岡「今のお話を聞いて、銀座の手土産のひとつ特徴として『手土産で季節を感じられる』というのがあるなと思いました。換言すると『東京の都市の豊かさ』といいますか、大都会の中なのに四季を感じられるよさかなと」
野老山「そのときにしか出会うことのできない味を、贈る側と贈られる側で共有できる喜びがありますね」
森岡「まさにその通りですね。あと、ウエストといえば白と金とアイボリーを基調にしたシンプルなパッケージも特徴的です。ここにも何か意識されているポイントはあるのでしょうか」
野老山「少し前まで紙袋には茶色でロゴマークが入っていたんですけれど、色も無くしてしまって真っ白に。一見するとわからないけれど、よく見たらウエストだってわかるぐらい。でも、それぐらいのさりげなさが『銀座らしい』じゃないかと」

銀座ウエストの包装と、エンボス加工を施した紙袋。
森岡「そう思います! 私もまだ8年ですが銀座で仕事をさせてもらっているなかで、この街には2つの美意識の働きを感じます。
日本の美を考えるとき、日光東照宮に象徴されるような将軍家の“盛って盛ってプラスの美意識”と、天皇家の桂離宮のような“引いて引いてマイナスの美意識”とがよく引き合いに出されますが、銀座にはその両方がありますよね。ウエストは、削ぎ落とされてシンプルなのに装飾されているというか、盛ってるのに洗練されているというか。銀座のセンスを象徴しているようで私は好きなんです」
野老山「季節限定のパッケージを考えるときも、社内でよく『それはすごく素敵だけど、ウエストっぽくないよね』という話し合いはしていますね」
森岡「そうした“らしさ”を守ることも銀座らしさな気がします。歌舞伎なんかでいわれる『守破離』のようなところがあるかなと。『破』『離』に行くにはやはり『守』がないといけない。そのベースとなるものがしっかり確立されている。でもそこを大切にしつつも、破っていくという意識もありますよね」
野老山「銀座の方とお話していると『変わらないふうに見えているけれど実は変えている』ということを、本当にいろいろな方からよく聞きますし、私もよく言っています(笑)」
森岡「すでにもう確立された技術があって、でも、よりお客様に喜んでいただけるように、常に切磋琢磨されているということなのかなと。そんなふうにひとつのものを追求していく」
野老山「ウエストのお菓子づくりもまさにそのように思います。素材を厳選して、そこからどうやって美味しいもの、喜んでいただけるものにしていくかということを、積み重ねていく。つくってから初めて原価計算をするというような感じです」

包装の中身は、定番の「ドライケーキ15袋入」(銀座ウエスト提供)。個包装された多様なスイーツは、好みの逸品を選ぶのも来客の席のお楽しみ。
森岡「どこまでもお客様のことを考えていらっしゃる。すごく愛がありますよね」
野老山「お客様はわかるんですよね。いちごの時期が終わりそうなときに、常連のお客様から『酸っぱい』とご指摘を受けたことがあったり。ああ、やっぱりすごくよく見ていらっしゃるんだなと実感することが多いです。大切なことはこれからも変えないでいきたいと思いますね」
森岡「まさに『守』の部分ですね。コロナ禍で世の中には様々な変化がありましたが、薫子さんは銀座の街の変化など感じることはありましたか」
野老山「銀座の商店からすると、街のつながりや、銀座で商売をしている人々のつながりはずっと変わらないなと思っています。コロナ禍で銀座にいらっしゃるお客様が減ってしまったことで、より一致団結したような気がします」
森岡「そうでしたね。銀座の皆さんと一緒に『銀座玉手箱』(※2020年6月、銀座の新旧店舗の有志が集まり、銀座の名品を詰め合わせたセットを発売したプロジェクト)が実現したのも、あの頃の危機感があったからだと思います。薫子さんが仰る通り街の結束が高まって、この街はやはり『大きな商店街』であるなと感じることが多くありました」
野老山「『まずはやってみよう!』と、普段だったらやらないようなこと、今まで挑戦できなかったことにたくさん取り組めました。通販で焼き菓子のバラ売りをはじめたり、他の銀座のお店さんたちとコラボレーションをしたり、私たちも楽しくて、お客様にも喜んでいただけた。勢いがついた数年だったなと思います。自分自身、銀座愛がより深まりました」
森岡「最近気づいたことに、銀座は『明治時代にできたスマートフォン』であるということがあるんですが……」
野老山「銀座が、スマートフォン!?」
森岡「はい。銀座にガス灯が通ったのが1874年らしくて、街が『発光』をしはじめた。スマートフォンも発光している。そして当時、時計台が方々に立っていた。あと、写真館があり、写真を撮る場所でもあった。出版社と新聞社が集まっていて情報が集積していた。喫茶店やビアホールができて、そこがチャット機能を有していた。銀行もあったので決済もできる……。碁盤の目状の街全体がネットになっていて、銀座という街のネットのなかに、スマホの機能であるアプリが点在していたんです」
野老山「なるほど……! これは大発見ですね」
森岡「私の単なるイメージではありますが、銀座がスマートフォンであるならば、街を支える人やお店同士の『つながり』が強いのも必然であるように感じています」
「小さな出来事」が紡ぐ文化
森岡「そんなネットワークのなかでお手紙や贈り物をたずさえて人は行き来していたのかもしれません。そこで手土産に話を戻しますと、やっぱり持ち運びしやすく軽い気持ちがあることが、いいんじゃないかなと思いました。銀座の街のたしなみもそうで、『かろみがある』といいますか。重たくない、消えるもの。Instagramのストーリーズとかも消えますよね。そういう儚さが時代に合っているんじゃないでしょうか」
野老山「ちょっとしたものだからこそ、そこまで親しくない方にも気兼ねなく贈ることができる。手土産ひとつあると会話も盛り上がりますし、距離もグッと縮まるような感じがしますよね」
森岡「そこからはじまる何事かがありますね。弱くて美しい、小さな出来事」
野老山「人にあらたまって気持ちをお伝えすることってなかなかないけれど、『贈る』ということを通してコミュニケーションができてしまうというのは、とても素敵な文化ですよね。あれ美味しかったなとか、嬉しかったなという気持ちがつながって、循環していくということもありますね」

森岡「ちょっとした出来事がつながっていく、愛のある小さなコミュニケーションが『手土産』のように感じます。そう思うと『手弁当で集まる』とか『手紙』とか『手仕事』とか、みんな『手』がついていますね……。『土産』と『手土産』だと意味が違ってきますし。『手』ってなんなんでしょうか。何事かを表している気がしますね」
野老山「ウエストの社是である『真摯』という言葉のなかにも、『手』が入っています」
森岡「『手』は私たちの暮らしのなかで特に繊細な感覚を伝えるもの。『かろみ』を象徴するキーワードかもしれませんね。愛と軽やかさが掌におさまるような、細やかな贈り物。
『手』といえば、銀座の街に、手土産を買う人をこうやって(手を大きく動かしながら)『フレー! フレー!』って応援してくれる『手土産応援団』がいたら面白いんじゃないかな。銀座には毎日、各店舗が力を込めた美味しいものがずらりと用意されている。甲子園の準々決勝、準決勝ぐらいの気合が入ってます。そこに私たちは大手を振って手土産を買いに行く。『今から手土産を買いに行くぞ!』と。すると、応援団が力強い声援をおくる(笑)。そんな感じで手土産という出来事がもっと盛り上がっていくと素敵ですね」

取材・文/裏谷文野 写真/白井晴幸
――XD MAGAZINE VOL.06 特集『贈る』は、全国の取り扱い書店のほか、プレイドオンラインストア、Amazonなどで販売中です。