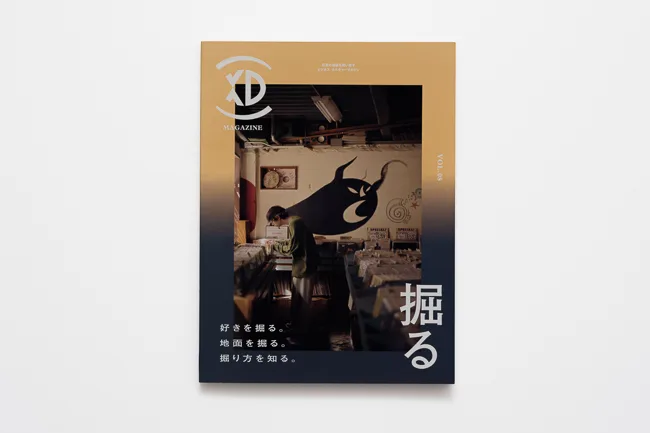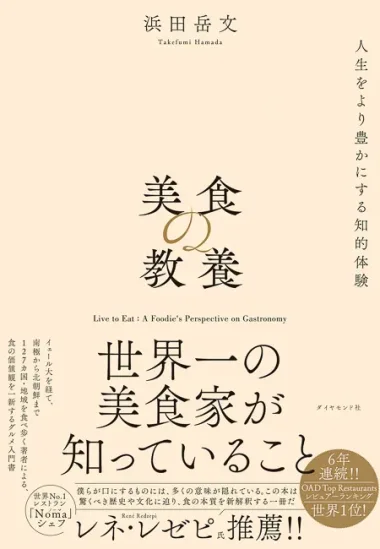「美食」=人生をより豊かにする知的体験として定義し、世界中のレストランを食べ歩く「美食家」浜田岳文さん。単なる味覚としての“うまさ”だけでなく、その背景にある文化や歴史、技術、哲学などさまざまな視点で食を掘り下げ、知ることでより美味しくなる“文化的に食べること”の奥深さを提唱している。「うまいものを食べたい」という欲求は誰しもあれど、その基準は人それぞれ。味覚の楽しみ以上の感動をもたらす食との向き合い方、探究することの喜びについて語ってもらった。
(この記事は2024年12月に発行された『XD MAGAZINE VOL.08』より転載しています)
浜田 岳文(はまだ・たけふみ)
美食家。1974年、兵庫県生まれ。大学在学中に、ニューヨークを中心に食べ歩きを開始。その後世界約128の国・地域を踏破。「OAD世界のトップレストラン」のレビュアーランキングでは、2018年度から7年連続第一位にランクイン。株式会社アクセス・オール・エリア 代表。エンターテインメントや食の領域で数社のアドバイザーを務めつつ、食関連のスタートアップ企業への投資も行っている。
〈美食〉の定義——「うまい」と「美味しい」の違い
近年だと、ロシアでの食事が思い出深いです。軍事侵攻に対する経済制裁が長らく続いているので、現地では海外の食材が仕入れにくい状況にあります。その影響で、皮肉にも地産地消のかたちが盛んになっている。地元の食材じゃないと使えないわけですね。ぼくが訪問した際には、フランス名産のフォアグラの代わりに地元の白鳥のフォアグラが出たり、イタリアからの輸入ができないチーズの代わりには、自分たちでつくったというモッツァレラのようなものをいただきました。
また、海外からのお客さんが減ったことで、お店の在り方も変化する。現在だと料理も国内の需要に合わせたメニューや味付けになっているかもしれませんね。
そんな状況ですので料理人たちも動く。ロシアの料理人たちが今多く集まっているのが、ドバイです。紛争に関して比較的中立な立場にある国ですが、ここに支店を出して活路を見出している料理人も少なくありません。
こんなふうに政治や経済が連動しながら食に帰結しているということが、個人的にすごく興味深い。もともと人間は、精神的に健康に生きるため文化を必要とする生き物です。そしてもちろん、食べ方にも文化がある。それは現地で食べてこそ気づけることが多く、ある種のフィールドワークを続けているようでもあります。社会を知るための入り口として「食」があるというわけです。
そうした考えのもと「美食」を提案しているわけですが、「美」の文字からしてえらく豪奢なものというイメージを持たれることもあります。だけどぼくの考える「美食」を端的に言い換えるとすれば、食と文化の関わり合いを考察することを表す「ガストロノミー」という言葉が適当でしょう。つまり、単に「うまい」をゴールとするのではなく、食を学問的に追求することで社会的な場面にもつなげて考えていく。大げさにいえば、食を通じた文化人類学というところでしょうか。
その対象となるのは主には、レストランという場所で提供される「食」を通じた体験、そして料理とサービスに込められるクリエイティビティです。
食の考え方は、人それぞれ。「うまい」を楽しむ食べ方もあれば、味にこだわらずお腹いっぱいになればいいという人もいるでしょう。しかし、食の背景に目を向け、学びながら食べることから得られる喜びがある。それこそが「うまい」とは異なる「美味しい」であると考えています。

世界のレストランを巡り、未知を掘り下げる
ぼくはそんなふうに「美食」を求めて、1年のうち9ヶ月以上はさまざまな国や地域で食べ歩いて過ごしています。これまでに巡ったのは128の国と地域。最近は北欧を周ってきたところです。
もしも「うまい」だけを求めるなら、こんなことをする必要はないでしょう。わざわざ遠くに食べに行かなくとも、良い食材の集まる東京にいればそれで事足りる。それどころか世界にはうまいものなんてあまりない国もあります。けれどそうした場所にもレストランという場所があり、料理人はそのハンディキャップの中でいろんな美味しい料理をつくり出している。
ぼくはそうした部分にこそ評価すべき価値があると感じていて、時間もお金も全てを食に集中して世界中を巡っているわけです。
世界中を飛び回って現地の一流の店を巡る人々を英語では「フーディー」と呼びます。ぼくもそのひとりですが、同じような食べ方をしている人は少ない気がします。多くのフーディーにとっては、「うまい」と分かっている店に行けば目的が果たせるから。
だけど「うまい」を基準にした評価には、個人の好き嫌いも影響します。そしてぼくの「美食」の評価の軸となる文化的価値は、個人の好みとはまた違う評価軸。一言で言うのは難しいですが、あえて言えば、文化や歴史の厚みが判断の軸になっています。ぼくが「OAD世界のトップレストラン(OAD Top Restaurants)*1」のレビュアーランキングで1位となっている理由も、単純に数多く食べ歩いているからではなく、そうした食べ方ゆえなのだと思います。

例えば「世界のベストレストラン50」にも選ばれているデンマークの「ノーマ(Noma)*2」。北欧文化をベースとした、発酵食品や野で採集するハーブやキノコ類(天然食材)を用いた料理を提供するレストランです。今でこそ旨味を取り入れた皿を提供するようになりましたが、もとはとても難解でした。伝統的な発酵の技法を使った料理はどれも酸味が強く、強烈。
しかし、そこには文化的な意義がありました。現地の気候に由来する発酵と採集による食文化は、現代では食材を買えない貧しい人がすること、というネガティブなイメージが定着していました。「ノーマ」は、その食の在り方を見直して、誇るべき文化として打ち出した。価値観を逆転させたそんなメッセージ性に打たれました。
その食べ方は面白いのか? そう思う人もいるかもしれませんが、自分の好みとは合わなくとも素晴らしいものがある。それもまた面白いんです。そんな料理に出会いたいし、こうした食との向き合い方をしてきたからこそ出会えた美味しさがあります。自分自身の食の傾向を客観視するきっかけにもなりますしね。
スペインのデニアという地中海沿いのリゾート地にある「キケ・ダコスタ(QUIQUE DACOSTA)*3」で出された品もまた、意義あるものでした。「そんなにいいものじゃないけど」と地元で採れた海藻を出されて、食べてみると確かにうまくはない。
なぜそんなものを出すのか聞いてみると、その昔、地域一帯は貧しさゆえに海藻以外にほとんど食べるものがなく、そんな歴史を示す一品なのだそう。後に続く皿はそれを踏まえた料理で、より深い理解につながりました。
*1|OAD世界のトップレストラン(OAD Top Restaurants)
世界各国に約5,000人いるレビュアーの意見を統合し、世界中の1万6,000超のレストランのランキングを決定するもの。国際的な名声を持つダイニングガイドとして知られている。
*2|ノーマ(Noma)
デンマーク・コペンハーゲンのレストラン。開業以来20年間、世界中のレストランからその年最旬の50軒のみに贈られる「世界のベストレストラン50」において5度の世界1位獲得、ミシュラン3つ星などの称号を獲得し、料理の独創性や先進性、レストランの在り方においても世界にさまざまな影響を与え続けてきた。2024年末で通常営業を終えることが発表されており、今後は研究や開発に主軸を置きながら、期間限定での営業を予定している。
*3|キケ・ダコスタ(QUIQUE DACOSTA)
芸術的な料理表現で世界的に名を馳せるスペイン・デニアの3つ星レストラン。同国出身のオーナーシェフ、キケ・ダコスタ氏が手がける、自らの地域と文化の誇りをテーマとした、地中海沿岸の伝統ある食文化を現代的に体現する料理が注目を集める。2024年「世界のベストレストラン50」では14位にランクイン。

好奇心の暴走に身を委ねる
本を出してから、ぼくの考える「美食」の在り方について読者の方からは「道」のようだと言われました。茶道のような、ある種の様式美といいますか。
そもそもはぼく自身の、興味を持ったことはとことん掘り下げないと気が済まない性格からですね。「食」を掘り下げるようになったのは、大学時代の寮のまずいご飯から逃れるために、必要にかられて外食をするようになってから。それを繰り返すうちにレストランごとの違いやその理由について考え、まさに「掘る」ようになったわけです。
そして会社勤めを経て、今こうして「食に全振り」の生活を送っています。それが楽しいか幸せなのかを問われても、正直なところよく分からない。楽しいから世界中で食べ歩いているというわけでもない。常に「知りたい」という欲求を満たす嬉しさを求めている。もともとあった好奇心が暴走し続けているんです。
思えば、音楽の趣味もそうですし、鑑賞するという行為が好きです。自分でつくり出すわけではなく。もっといえば、深掘りして体系的に理解したいという欲求ですね。

その在り方の分かりやすい例をあげると、『関ジャム 完全燃SHOW (現・EIGHT-JAM)』 (テレビ朝日)なんてTV番組がそうですよね。ぼくも好きなんですが。音楽番組というと、アーティストがパフォーマンスを披露したり、流れてくる音楽を楽しむイメージ。「関ジャム」はそうじゃなくて、音楽の仕組みを分析したり楽曲の背景を紐解いていく。例えば音楽と聴いた人の感情の関係をコード進行から分析してみたりする。
そんな理屈っぽいことをしなくても音楽は楽しめるものだけど、分かった方がより深く楽しめる。それがこの番組の提示していることです。
ぼくは『UMAMIHOLIC』というYouTubeチャンネルをやっていて、シェフや生産者との対談を通じた情報を発信しています。単純に誰がどう食べてもうまいものを、口に入れて「うまい」と感じて終わらせるのではなく、その理由を知ることでより楽しむことができるように、そんな思いで解説を届けています。
そこから派生して最近『UMAMIHOLICコミュニティ』*4を立ち上げました。皿に込められた料理人の考え方を一緒に学ぼうという趣旨で、定期的に食事会を開いています。料理の伝統やクリエイティビティを大切にしている店を訪問し、お店は貸切に。普段なら直接お話を聞けないような料理人さんに、一皿一皿に込められた考えなどを伺い、美味しさの秘訣を紐解きながら料理を味わいます。思いの他、参加者には若い世代の方も多く、今後の開催も楽しみに思っています。
こうした食べ方が広まることを望んでいる人が、つくり手の中にも増えているように思います。“食べ手”がその努力や苦労も含めて理解できるところまで掘り下げていくことができると、より深いところで分かり合える。そんな関係性から、さらに美味しい料理が生み出される可能性が広がっていくのではないでしょうか。
*4|UMAMIHOLICコミュニティについて
「フードを、ブームにしない。」をテーマに、2024年7月にローンチした。気候変動やインフレなどの影響で変化する食環境の中、サステナブルなレストランの在り方を考え、食文化を支える人々を応援することを目的に立ち上げられた。食事会やトークイベントを通じ、「美食」の視点から参加者とともに食を探求していく。

構成/編集部 写真提供/浜田岳文
――XD MAGAZINE VOL.08 特集『掘る』は、プレイドオンラインストアで販売中です。