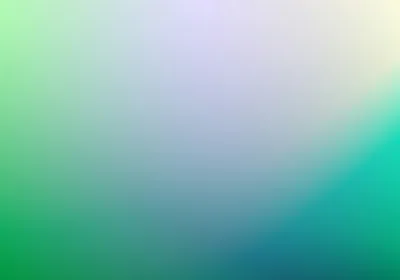「ブランドが支持されるためには、ディレクターがこめる“一方通行の熱量”が最も重要と考えています。その見えないパワーは、お客様に一番伝わりますから」
BAKE チーフクリエイティブディレクターの貞清誠治氏はこう語る。BAKEは、焼きたてチーズタルトの専門店「ベイクチーズタルト」やシュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」、東京駅のお土産として定番となったバターサンド専門店「プレスバターサンド」など、いずれも1ブランド1プロダクトの専門店として話題のお菓子ブランドを生み出してきた。
創業から約6年で国内外100店舗以上を展開し、2019年2月には新ブランドのガトーショコラ専門店「ショコラフィル」をオープンするといった新たな動きも見せている。
同社はどのように顧客に愛され続けるブランドを構築してきたのか。その過程には「8割主義」という考えのもと、徹底して商品と向き合うクリエイターの存在がある。貞清氏と、ベイクチーズタルトやショコラフィルでアートディレクターを務めた柿崎弓子氏に聞いた。
「食べる」までのストーリーをデザインする

貞清誠治氏
――BAKEの商品はどれもクリエイティブにかなりこだわっているかと思います。どうして、そこまでクリエイティブにこだわっているのでしょうか。
貞清:お菓子って自分のためにも買うけれど、人に持っていくシーンが多いじゃないですか。「あ、かわいい」って気持ちになるお菓子をもらえると、気分が上がりますよね。あまり難しく考えず、顧客としての自分がもらって嬉しいものにしたいなという気持ちはあります。
BAKEでは、食べるまでのストーリーを大きく「購入前」「購入時」「購入後」の3つに分けて考えています。例えば、購入前は商品開発からさかのぼってストーリ―を作ります。発表のときにどう伝わるかを考えるんです。発表の瞬間にワクワクしてほしいので。
次は、購入時。焼きたて状態で、シズル感のある体験をつくり、他のお店とは違うインパクトを顧客に感じてもらう。そして、購入後。誰かに渡したときに「いいね」と言ってもらうまでの体験が一連の流れだと捉えています。どのステップにも手を抜かないようにしていますね。
――そこまでこだわるようになったのはいつからだったのでしょうか。
貞清:初期からですね。BAKEは基本的に専門店なので、商品数が少ないです。例えば、チーズタルトなら、できたてが美味しい。そうすると、ショーケースに入れて食べてもらうのがもったいないんですよね。しかし、できたてを提供しようとすると、他のことがやれなくなる。チーズタルト以外をやろうとすると、手が回らないため商品数を絞っています。
ただ商品数を絞っているぶん、そのクオリティと伝えるメッセージは、Webサイトの一つひとつの文言も含めて、シンプルに強く伝わるようこだわっているつもりです。

ベイクチーズタルト
ブランドとディレクターは一心同体
――それだけクリエイティブにこだわろうとすると、内部で議論も起こるのでは?
貞清:いえ、あまり起こらないですね。BAKEでは、各ブランドにアートディレクターがいて、その人がクリエイティブの責任者として、世界観を構築することになります。BAKEに入社した時点で、クリエイティブディレクターの僕はその人を信用しているので、口を出すことは滅多にありません。
つまり、BAKEの商品開発は、己の戦いなんです。大変さも孤独感もありますが、そのぶん得られる感動や充実感はすごいです。みんな、そこを目指して持てる時間のすべてを投入しています。
柿崎:他の会社でも、プロモーションごとにコンセプトを作ることはあるかもしれませんが、常にブランドに専任のアートディレクターが一人付くのは珍しいと思います。統括するディレクターに求められるのは、絶対にブレないこと。ブランドとディレクターは存在が一心同体なんです。
貞清:デザインには、人の好みがあってどうしても好き嫌いが発生してしまいますよね。だから、私たちはどれだけディレクターの「熱量」が高いかを一番大事にしているんです。「熱量」という見えないパワーは、お客様に一番伝わると信じているので。そういう意味では、BAKEのクリエイティブは、完全にプロダクトアウトで、マーケットインはしていません。
――マーケットインはしていないとなると、商品開発はどのように行っているのでしょうか?
貞清:「8割主義」という考え方があります。新たに商品を開発する際は、市場規模としてシェアの大きいものを狙います。味に関しても、万人受けするものを作る。これまでに存在しなかったような、イノベーティブな商品を作ろうという考え方はありません。マーケットが成立している商材を選び、BAKEなりにアップデートして伝えていくスタイルです。
最初は、パティシエが考えるところから商品開発がスタートします。ただ、アートディレクターやマーケター、PRも開発の初期段階から入りますよ。どんな商品にするか、価格設定や形、味まで一緒に考えることで、チームとしても一方通行の熱量をもって仕上げていきます。
柿崎:デザインは装う手段ですが、アウトプットを作る前に探るフェーズがあります。だったら、入口からアウトプットをイメージしながら関わり、納得のいくものを作りたい。途中から入ると、「なぜこうなっているの?」と納得のいかないものがあったりする。それが決まる段階にいれば、変えられたのにとなってしまいますよね。だから、入口から関わります。

柿崎弓子氏
――ディスカッションでは、デザインに対するフィードバックもあるのでしょうか?
貞清:承認をとる場面もありますが、ほとんどはアートディレクターが一人で進めていきます。社内で熱量を持って進める人に口出す人はいないんですよね。これは創業からのカルチャーが影響していると思います。初期から「任せる」というスタンスでした。
柿崎:デザインに口を出さない会社の文化はありますね。もちろん、ブランドの責任を持つ立場として社内からの意見は聞きますし、経理の人に聞くこともあります。いろいろな意見を踏まえたうえで、最終的に世に出す際のデザインのジャッジは任せてもらっています。
BAKEのブランドには、全てに人格がある
――2019年2月には、ガトーショコラ専門店であるショコラフィルをオープンされました。ショコラフルのデザインは、どのような思いで設計されたのでしょうか?
柿崎:ショコラフィルのコンセプトは、「チョコレートよりもチョコレートを感じるガトーショコラ」です。最近はタブレット型の商品が流行っていますが、お菓子にすることでチョコレートをもっと味わえたり、口どけが良かったり、香りが感じられるようにしたいと思い、開発しました。
パッケージのデザインは、「ウルトラマリン」と「シルバー」をキーカラーとしています。ショコラフィルはコロンビア産のチョコレートを活用していて、海を越えて届いたカカオをイメージして、広大な海を思わせる鮮やかな色ということで、ウルトラマリンを据えました。
シルバーは、チョコレートの味や風味を守るために使われてきた「銀紙」を意識して、その機能を守りながら、デザインとしてもカッコイイと思えるものを表現しています。
――ショコラフィルのターゲット層などは決められていますか?
柿崎:ブランドターゲットは40代の女性をイメージしていますね。高価格帯ということもあるのですが、色んな経験をして遊び心を持った大人の女性に支持されるブランドになってほしいという思いがあります。

2019年2月にオープンしたショコラフィル
――ディレクターの熱量という言及はありましたが、デザインやターゲット層を決めるうえで、重要な要素みたいなものはあるのでしょうか?
貞清:BAKEのブランドは、全部人格を決めているんですよね。ペルソナとは違うのですが、家族構成や住んでいる場所、最寄駅、キャラクターなどを決めていて。つまり、ブランドを体現する類似キャラのような位置づけですね。これを意思決定をするときの参考にしています。
――人格、面白いですね。どのようにして決めていますか?
柿崎:商品開発の最初の段階でディスカッションします。例えば、私が担当したプレスバターサンドは「渋い」「職人気質のおじさん」という人格です。会社としてお土産業態は初めてのチャレンジで、最初は「お土産は女性が買うもの」という考えがあったのですが、お店のある東京駅は男性が多い場所。だから、男性にも買ってほしいという気持ちでデザインしました。
オープンした後に、男性のお客様が店舗に並んでくれているのを見たり、サラリーマンの人が会社の女の子に買って帰るとか、ソーシャルメディアで男性の反応が他のブランドと比較して多かったのを見たりしたときは、ブランドの人格が届いたと実感できましたね。
――これまで商品開発でのプロセスを聞いてきましたが、お客様と向き合う販売のプロセスにおいて工夫されている点や取り組んでいることがあれば教えてください。
柿崎:ブランドの思想は伝えるようにしています。そうすると、ショコラフィルだと「40代の女性に支持される身だしなみって何だろう」と考えるきっかけになりますよね。
私が入社した約2年前は、販売スタッフにブランドの思想について説明する機会をまだ持てていませんでした。そこで、マーケティングチームとスタッフ向けのブランドブックを作成したり、コミュニケーションツールを作って感謝を伝え合う機会を設けたりしました。
その結果、あるブランドで販売のリーダーをしているスタッフが、マーケティングチームに新しく加わった社員に、そのコンセプトや思いなどを伝える光景が見られるようになったんです。こうした取り組みも、お客様に“BAKEらしさ”を伝えることにつながったと思います。
――最後に今後どのような顧客体験を届けていきたいか教えてください。
貞清:各ブランドの事業部長が今注力しているのが、ファンコミュニティをどのように形成していくかということです。これまでにもイベントを開催したり、グループインタビューを行ったりはしていますが、ブランドごとのやり方も模索していきたいと思っています。
取材・文/庄司智昭 編集/モリジュンヤ 撮影/加藤甫