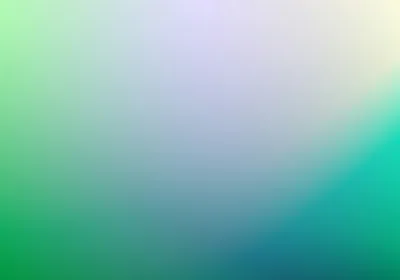新たなサービスの開発や、事業戦略の見直しなどに際して、CX(顧客体験)への言及が少しずつ増えてきたのではないだろうか。「モノからコト」に消費への関心が移行していく中で、「体験」を重視したサービス設計の重要性も指摘されており、具体的な取り組みを進める企業も見られるようになってきた。
各業界で議論される中で、外せないポイントが「経営との関係性」ではないだろうか。CXを追求することで、結局のところ収益にどう結びつくのか。この点をはっきりさせて、経営陣をはじめ社内を説得できない限り、CXを向上させるための施策に予算を割くのは難しい。
2019年9月2~5日に京都で行われた「ICCサミット KYOTO 2019」では、経営とCXをテーマにしたセッション「CXは経営に寄与するか。CXと経営の関係を議論する」が開催された。
登壇者は、協同商事/コエドブルワリー代表取締役 兼 CEOの朝霧重治氏、ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員CMO/CIOの志賀智之氏、THE GUILD代表の深津貴之氏、コメ兵 執行役員マーケティング統括部長の藤原義昭氏、プレイド代表取締役社長の倉橋健太の5名。モデレーターをインクワイア代表取締役社長のモリジュンヤが務めた。
「事業を継続させたい」なら、CXと向き合わなければいけない
異なる業界の経営者が集まった本セッションの冒頭では、各社が「CXをどう捉えているのか」が紹介された。
まずは、ブランド品を中心に実店舗とECサイトで買取・販売事業をおこなうコメ兵。マーケティング統括を担う藤原氏は、顧客に提供できる価値を2つの要素に分解して捉えているという。

左より、ゴルフダイジェスト・オンライン 執行役員CMO/CIO 志賀智之氏、コメ兵 執行役員マーケティング統括部長 藤原義昭氏、プレイド 代表取締役社長 倉橋健太
藤原氏「顧客を惹きつける要素は、大きく『機能的価値』と『感情的価値』に分けられると思っています。機能的価値とは『安い』『早く買える』など、利便性に関わる部分。感情的価値は“ここで買ってよかった”という、合理的に説明できない価値を指します。
どちらも追求するべきですが、機能的価値だけでは、顧客との継続的な関係は生まれにくい。自社より良い機能を持つ製品が出れば、あっさり関心が移ってしまいますからね。社員にも『安さだけで勝負していては儲からないよ』と言っています。お客様が本当に喜ぶことをして感情的価値を獲得し、中長期的な関係を構築していかなければいけない。それが、事業成長に重要なLTV(顧客生涯価値)の向上につながります」
比較不可能な価値を届けていくべきだという主張に対し、コエドブルワリーの朝霧氏も同意した。川越発のクラフトビール「COEDO」を販売する同社は、単なるビールメーカーではなく、「COEDOブランドを通して得られる体験を提供する企業」だとする。
朝霧氏「COEDOはただビールを提供しているわけではありません。ビールの“面白さ”を体験してもらうための活動を主体としています。なので、事業の原点からCXに直結しているといえますね。美味しいビールを提供するのは大前提として、飲む場所やグラスも厳選し、ビールを味わうことの楽しさ、面白さを最大化するにはどうしたらいいのかを日々考えています」

左から、インクワイア 代表取締役社長 モリジュンヤ(モデレーター)、協同商事/コエドブルワリー 代表取締役 兼 CEO 朝霧重治氏、THE GUILD 代表 深津貴之氏
また、オンラインでのゴルフ場の予約やゴルフ製品販売など、ゴルフに関するサービスを包括的に提供するゴルフ・ダイジェスト・オンライン(以下、GDO)の志賀氏も、LTV向上の重要性に触れた上で、「CXは中長期的な視点で取り組むべき」と話す。
志賀氏「5年前から、CXに取り組むためにCXD(お客様体験デザイン本部)という部署を持っていて、僕が管掌しています。ゴルフを中心に360度の事業を展開している当社は、各部署で直近の売上を追っているため、どうしても中長期的な目線を持ちづらい。そこをCXDで補完し、CXを最優先した施策を全部署横断で運用しています」
製品そのものではなく、その届け方まで配慮することで、情緒的な価値を見出してもらう。中長期的に顧客に貢献し、LTVの向上につなげる――3者が述べることは、一見すると製品を普通に販売するよりも、収益性が悪そうだ。「CX重視=コストがかかりすぎる」と考える経営者も、まだ多いかもしれない。
様々な企業のコンサルティングを請け負うTHE GUILD 代表の深津氏は、CXが経営に「もたらすもの」ではなく「もたらさないもの」について考える方がイメージしやすいと語った。
深津氏「CXが完全に損なわれている状態を想像してみてください。たとえば、顧客にメリットのない商品を騙して売りつけ、カスタマーサポートに問い合わせても全くレスがない、退会の手続きが意図的に複雑にされていてなかなかできない、などです。自分が利用者だったら、もう二度と使いたくなくなりますよね。そんな風に足を引っ張られる場面を考えた方が、CXの重要性を理解しやすいと思います」
企業を「人」に見立てると、CXの重要性を認識できる
では、顧客の体験価値を上げていくためには、具体的に何から始めればいいのか。藤原氏が指摘するのは、「顧客のネガティブな体験を0にすること」と、「その0をプラスにしていくこと」。取り組みやすいのは、ネガティブな体験を0にするための施策だという。
藤原氏「プラスにする、つまり喜びを増幅させる施策は、社員によって感じ方が異なります。顧客をすごく理解しないといけないし、立てた施策について全員が納得するのにも時間がかかる。一方、顧客が嫌がっている要因が明らかな場合、それを取り除くのに合意形成はいりませんから」

藤原氏「ネガティブな要因を潰しにいくために有効なのが、インタビューによる定性調査です。コメ兵では、定期的に1人の顧客に1時間ほどのインタビューを実施しています。30分ほど耳を傾けていると、大体の人がネガティブな意見や感情を出してくれるんですね。コストも労力もかかりますが、Webアンケートなどよりも遥かに大きな成果を得られます」
いきなり「加点」を目指すのではなく、まずは「減点」を見つけて解消すべき。この発言を受けて深津氏は、CXを設計する際に有用な1つの手法を紹介した。
深津氏「一度、自社を“人”にたとえてみてください。企業を擬人化したとき、どんな人物になるか。他者の話を聞かず、自分の主張ばかりを通そうとしたり、儲けだけを考えていたりするような人とは、関わりたくないですよね。そこから、“真っ当な人格”を持つ企業になるにはどうすればいいのかと考えると、スムーズにCX戦略を設計できると思います」

深津氏「僕がCXOを務めるコンテンツプラットフォーム『note』でも、『人だったらやばすぎるnoteとは何か?』をまず議論したんです。やたら点滅する広告を押しつけてくる人だとか、有料コンテンツばかりをお勧めしてくる人だとか。サービスの“ダークサイド版”をみんなで認識できれば、自社の健全度をチェックしやすいんです」
この意見に志賀氏も深く頷き、「まずは真っ当な人であろうよってことですよね。CXは企業理念から降りてくるべきもので、そこからとるべき行動を考えていくべきですよね」と語る。常に企業理念やミッションをベースで考えることができれば、事業が理想像から大きくズレることはない。
志賀氏「当社の場合は『ゴルフで世界をつなぐ』というミッションを掲げています。ハブの役割を果たそうとしているのに、嫌がられるほどのメルマガを送るなど、お客様が離れてしまう行動を取っては元も子もない。社内でもよく『良い店員さんってどんな人だろう?』というテーマで話し合っています」
また、CXプラットフォーム「KARTE」を提供するプレイドのCEO倉橋は、良いCXを生み出すために配慮するべきポイントとして、「EX(従業員体験)」にも言及した。

倉橋「EXの状態が、CXを大きく左右するなと感じています。従業員がサービスにおける数値面の効果ばかりを訴えていれば、顧客からも短期的な数字を求められる。でも、『こういう世界観がつくれる』サービスという部分が顧客に伝わるようになっていれば、その世界観が好きだという理由で使い続けてもらえるんです。現場でどう顧客と合意しているかで、求められるCXが変わるんですよ」
朝霧氏「提供する側のワクワク感が、EXにつながりますよね。ビールの楽しさを提供したいなら、まずはスタッフ自身が楽しめていなければいけません。スタッフが良いと思っているものは、自然と顧客にも良いと思ってもらえるはずなんです」
人が担うべきか、テクノロジーに任せるべきか
ここまでの議論で、CX向上施策の具体的な取り組みに「人」が欠かせないことが見えてきた。とはいえ、KARTEをはじめ、支援ツールとしてのテクノロジーも増加傾向にある。実際、どこまでテクノロジーに任せるべきなのか。
モデレーターのモリの投げかけに対し、志賀氏は、オンラインを主戦場とするGDOの場合、CX向上においてはテクノロジーの活用が不可欠だと語る。

志賀氏「当社は実際に、KARTEなどのツールを導入しています。顧客のセグメントごとに提案シナリオをいくつか作って入力し、その結果が良いものであれば、あとはCXを自動化していく。
一方で、オートメーション化しすぎてはいけない領域もあります。特に最近思うのは、商品のレコメンド。これを同じような手法で最適化していくと、結局は売れ筋ばかり表示されてしまうんですよね。パーソナライズがほとんどされていない。顧客が新たなディスカバリーをできるようにするには、アルゴリズムに遺伝子のような突然変異をさせることを考えていいのかな、とも感じています」
倉橋「テクノロジーでの自動化は、手段であって目的ではないんです。エンドユーザーにとって何がいいのかを考えたときに、必ずしも正確な情報だけが求められるとは限らない。全く見当違いだった提案が嬉しい場合だってありますよね。そんな出会いを生み出す“ラストワンマイル”の接客には、やはり人が介在する価値が高いと思います」
Webをベースに、顧客を知るためのデータを蓄積しているGDO。逆に、オフラインをメインに展開するCOEDOの朝霧氏は、顧客との有機的なつながりをある程度形成できたため、これからテクノロジー活用に踏み出すところだという。
朝霧氏「僕たちの場合、リアルの場で交流しているときは、どう感じていただけているか声を聞けるし、顔色などからもある程度わかります。しかし、そうでないときにどう感じているのか、本当に喜んでくれているのかまでは検証できていません。そこはテクノロジーの力を借りて、把握していかなければいけないと思っています」

当然、会社によってテクノロジーの使いどころは違う。結局どのような判断基準を持てばいいのか。深津氏はその指針を示した。
深津氏「自社のミッションと合致する部分には、人が介入するのがいいと思いますね。たとえばnoteでは、システムベースのランキングを設置せず、編集部が選んだおすすめ記事を人力でピックアップしています。PVをベースにすると、ネガティブな内容がランクインしやすく、それを見た人がさらにネガティブな記事を書いてしまう。
でも、『誰もが創作をはじめ、続けられるようにする』をミッションに掲げるnoteは、そのような世界を望んでいません。アップされる記事をできるだけ読み、“みんなが書きたくなるような記事”“誰かが救われて、新たな活動を促すような記事”を一つひとつ選んでいます。すごく非効率ですが、noteのミッションを実現するために手を抜いてはいけない部分なんです」
経営陣は、会食を減らしてでも顧客に会いに行け
セッション終盤には、「CXの重要性」を社内に浸透させる方法論に話が及んだ。CX向上の施策を進めるなら、特に経営陣全体の理解が必須だが、各社はどのようにクリアしてきたのか。
コメ兵の場合は、先に現場からアプローチし、出た小さい成果を共有していったという。
藤原氏「現場担当者の個々の目標設定の段階から入り込み、CX向上に寄与するKPIを設定しました。CXというと『お客様が喜んでくれたかどうか』という定性的な目標を設定しがちですよね。そうではなく、定量的計測ができ、かつ売上と相関するKPIを設けるべきです。KPI達成によって売上が増えたというデータが取れれば、他の経営陣も説得しやすくなる」
志賀氏「入り方としては、経営陣の説得に体力を使うよりも、先に現場の意識改革を進める方がいいでしょうね。当社も最初、担当役員をつけてCXを推進しようとしたんですが、うまくワークしませんでした。経営と現場の思考には、どうしてもギャップがある。でも時間をかけることで、だんだんとLTVの考え方が浸透し、1カ月先から1年先、3年先を見られるようになっていきました」

しかし、藤原氏や志賀氏ほど現場をうまく巻き込める経営者がいない場合、CXの重要性を示すためのエビデンスをどう示していくか。各企業で定量的な把握が進む中、「N=1」の顧客理解を助けるのが、プレイドの役割だと倉橋は話す。
倉橋「顧客一人ひとりと、そのコンテクストがまだまだ可視化されていません。各企業がそこを見えるようにする、ここのコストを下げていくことも、すごく重要なイノベーションだと考えています」
また、現場を押さえた上で、やはり最終的には経営陣全体の合意が必要だ。その説得にあたっても有効な手段がある、と深津氏は最後に語る。顧客と直接交流する場を設けるのだ。
深津氏「会食を1つ減らしてでも、顧客に会いに行ってもらうことをお勧めします。経営側に入るとどうしても中にこもりがちで、顧客との距離が遠のいてしまう。顧客と会ったり遊んだりする場を通じて、もっと顧客を知ってもらうべきじゃないかな、と思いますね」

ビジネスは「人」との関わり合いで成立する。それなのに、「企業」単位では途端に人格を失い、人対人ではありえないようなコミュニケーションが横行してしまう。
要因は様々だが、「目先の売上」を重視するあまり、企業本位の思考が強くなってしまうことはその一つだろう。売上目標を達成するために、顧客との関係性を犠牲にしてしまっては本末転倒だ。
登壇者らは今回、自社の“あるべき姿”の定め方、顧客への向き合い方について、実例を具体的に紹介してくれた。各社が目指すのは、顧客との中長期的な関係を構築し、LTVを向上させることで得られる「将来の売上や収益」という成果に他ならない。経営者はもはや、CX向上の施策に取り組まない理由がないのではないか――そんな確信を抱かせるセッションだった。
文/水落絵理香 編集/佐々木将史 撮影/ICC