「私たちの暮らし方、買い物の仕方、食事の仕方を変えた」
ロンドンにあるデザインミュージアムのティム・マーロウ館長は、テレンス・コンラン氏のことをそう評する。同氏がもたらした業績は多々あるが、その中のひとつが「ザ・コンランショップ」の設立だ。
1973年、ロンドンに1号店がオープンして以来、独自の視点で世界中の家具や照明、インテリア小物などをセレクトし、日々の生活をより豊かに楽しむことを提案してきた。イギリスだけでなく、韓国、日本、クウェートにも店舗を展開。その影響力は世界に広がっている。
日本では1994年に初となる店舗が新宿パークタワーにオープン。現在は新宿、丸の内、神戸、福岡、伊勢丹新宿、代官山、麻布台ヒルズの7ヶ所に店を構えている。初店舗がオープンした当時、国内に「ライフスタイル」を提案するセレクトショップはまだ少なかった。ザ・コンランショップは、ライフスタイルショップと呼ばれる存在のパイオニアのひとつであり、そう認識している人も少なくない。
だが、「テレンスはライフスタイルショップという言葉は好まなかったんです」と語るのは、株式会社コンランショップ・ジャパン 代表取締役の中原慎⼀郎氏だ。中原氏は、2020年にテレンス・コンラン氏が亡くなった後、偉大な創業者の影響が強く残る中、2022年に代表に就任した。
時代や場所と共に変化するライフスタイルを、日本においてどのように提案しようとしているのか。創業者の想いや姿勢をどのように受け継ぎ、更新しようとしているのか。日本で最初にオープンした店舗であるザ・コンランショップ 新宿店にて話を伺った。
歴史あるブランドを引き継ぎ、更新する
「僕にとって、ザ・コンランショップは特別な存在なんです」
そう語る中原氏が、コンランショップ・ジャパンの代表に就任してから、約1年半が経った。彼がインテリア業界でキャリアをスタートしたのは、地元・鹿児島で大学生活を送っていた頃のことだ。鹿児島にあるアンティーク家具を扱うショップでアルバイトを始めたのがきっかけだった。
大学卒業を機に上京、家具の製造販売を手がける「Landscape Products(ランドケーププロダクツ)」を設立。東京・渋谷にオリジナル家具や雑貨を中心に構成されたショップ「Playmountain」や、カフェ「Tas Yard」、コーヒースタンド「BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK」などを展開。家具のセレクトにショップの運営、イベントディレクションなど、インテリアの世界で幅広く活動してきた。
2017年にはサンフランシスコにショップをオープン、その後ランドスケーププロダクツのファウンダーになる。日本とアメリカを行き来する生活を続けていたが、新型コロナウィルス感染症の流行によってショップは閉店へ。その少し後のタイミングで、株式会社コンランショップ・ジャパンから、代表取締役へのオファーがあった。
中原氏「お話をいただいた時はとても驚きました。大学時代、インテリアショップでアルバイトをしていた時に、ロンドンに行く機会を与えてもらい、オープンして間もないザ・コンランショップに行ったことがあります。そこで衝撃を受け、インテリアの世界に本格的に興味を持つようになりました。僕にとって、ザ・コンランショップは、特別な存在なんです」

株式会社コンランショップ・ジャパン 代表取締役 中原慎一郎氏。1971年、鹿児島県生まれ、<ランドスケーププロダクツ>ファウンダー。東京・渋谷区にてオリジナル家具などを扱う「Playmountain」、カフェ「Tas Yard」などを展開し、家具を中心としたインテリアデザイン、企業とコラボレーションしたプロダクトデザインも行う。デザインを通して良い風景を作ることをテーマに活動。2022年4月に株式会社コンランショップ・ジャパンの代表取締役社長に就任
当時の感動を思い出しながら、中原氏はオファーをきっかけに、久しぶりに店舗に足を運んだという。しかし、「久々に行ってみたら、あまりドキドキしなかった」と振り返る。
中原氏「もちろんザ・コンランショップを好きな気持ちは変わりませんし、安心感もありました。でも、あの頃に感じたほどの勢いやおもしろさが感じられなかったんです。いろいろなメーカーのものが集まって並んでいるけれど、店のものらしく佇んでいない、といいますか」
ただ、「逆にこの現状を変えることができたらおもしろいな」という思いも、おぼろげに抱き始めていたという。
中原氏「ザ・コンランショップは本国で50年続いているショップで、扱う商品もお客さまの層もとても広い。自分が限られた時間の中でできることがあるとしたら、このザ・コンランショップという広い土俵で、自分がやってきたことを組み合わせること。そうすることで、日本独自のインテリアや日用品の進化に携わることができるのではないか。そう考えると、まだまだやれることはあると思い、お引き受けすることに決めました」
商品の背景を丁寧に掘り下げ、新しいスタイルを作る

1994年に日本最初の店舗としてオープンした新宿店。2023年9月、翌年に日本上陸30年を控えるタイミングで、リニューアルオープンを果たした
そうして2022年4月、コンランショップ・ジャパンの代表取締役に就任した中原氏。
ザ・コンランショップに今も受け継がれているのは、「PLAIN」「SIMPLE」「USEFUL」の3つのキーワードだ。色や素材、デザイン、機能性などのすべてを携えた商品を並べることがセレクトの軸であり、豊かな生活に欠かせない──テレンス・コンランの商品選びのコンセプトである。
他方、中原氏が代表となって見えてきたのは、そうしたコアコンセプトを受け継ぎながら、新しいスタイルを作っていく難しさだという。
中原氏「インテリア業界は、定番とされる商品も多く、新しいスタイルの商品が頻繁に出てくる世界ではありません。また、日本のザ・コンランショップは、本国で開発しているオリジナル商品をメインに扱う会社なので、もともと利益率も低い。だからこそ、日本という場所で、イギリス本国の利益率の低い商品を扱うのではなく、国内のオリジナル品の割合を増やして新しいスタイルを作ろうと思った時に、ビジネスとして成立させる難しさを痛感しました」
運営の難しさを感じたのは、仕入れ候補を発見する難しさや、利益率の面だけではなかった。イギリス本店でセレクトされた商品は、色合いや大きさなどが日本の生活様式にフィットするとは限らない。
また日本の生活様式にフィットしにくい商品を扱うとなれば、「なぜ、この商品を仕入れたのか」「この商品をどう生活に馴染ませるといいのか」といったことを深く理解することも難しい。結果として、スタッフの販売が受け身になってしまうこともあったという。
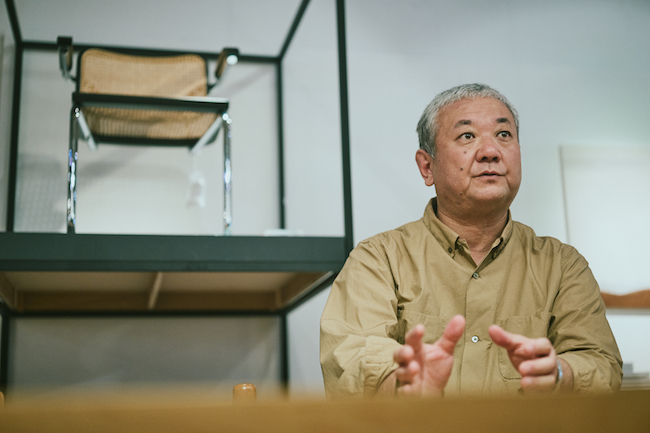
店舗に商品が馴染むことで“売りこなれ”ていく
ザ・コンランショップを、商品のストーリーや背景をしっかり掘り下げ、伝えていく場にしていきたい──そんな思いを抱きながら、代表としてのキャリアをスタートした中原氏。
着任後に挑んできたことの中でも、とりわけ目を引くのが、2023年4月に代官山ヒルサイドテラスにオープンさせた代官山店だ。
そもそも中原氏は、代官山ヒルサイドテラスで開催されるヒルサイドマーケットのディレクターを約15年務めている。代官山の町との縁は深く、行き交う人々にも思い入れがあった。
中原氏「代官山は、渋谷から1駅の距離で、高層ビルのないゆったりした空気が流れる特殊な場所です。そして長年、代官山のお客さまを見て感じていたのは、目利きの方や自分のスタイルを持っている方が多いということ。
そんな代官山の地に路面店を構えることで、お客さまに私たちのスタイルを見せ刺激を与えられるのではないか。代官山は、これまでのザ・コンランショップとは違う見せ方ができる場所だと感じました」

ザ・コンランショップ 代官山店(写真提供:コンランショップ・ジャパン)
代官山店は、従来のザ・コンランショップとは大きく異なる特徴を持つ。アジアの家具やプロダクトにフォーカスした初めての店舗で、企画から商品の選定、仕入れ、ディスプレイ、販売までを丸ごと作り上げる、「伝える」ことに主眼を置いた“自主編集型”のショップだ。
中原氏「これまでザ・コンランショップとしてアジアをきちんと掘り起こし、ミックスした店がまだないことは、以前よりずっと気になっていたことです。もし、テレンスが日本にいたら、アジアの商品を絶対に仕入れているだろう。世界中から厳選したアイテムにミックスして、いろいろなシーンで見せていただろうな、と思ったんです。ですから、自分のスタイルを持つお客さまが集う代官山で、アジアをテーマにした自主編集型のコンセプトショップを作ろうと決めました」
代官山店の大きな特徴は、スタッフがMD(マーチャンダイジング)を担当している点だ。店頭に並ぶ商品は、スタッフがアジア各地の目利きたちと協力し、直接作家やメーカーに会って話を聞き、数あるもののなかから選び抜いて買い付けてくる。スタッフ自らが足を運んでやりとりをすることで、商品が生まれた風土や背景などのストーリーを顧客に伝えることができるのだ。
中原氏「現地に足を運んで自主的に商品を見つけて仕入れ、それぞれのストーリーを他のスタッフやお客さまにきちんと伝える。これまでは本国の担当者や日本の商品部のスタッフが大半の仕入れを担ってきましたが、お客さまに近いスタッフが仕入れを行うことに、大きな意味があるのです」

さらに「伝える」を重視する視点から、実際に体感できる場所も作られた。地階に、東京・青山の日本茶専門店「櫻井焙茶研究所」の所長・櫻井真也氏による監修のTea Bar「聴景居」を併設。台湾茶や中国茶、日本茶などのアジアのお茶文化を、アジアの道具やしつらえに触れながら体験できる。
中原氏「聴景居を併設したのは、お客さまに実際にお茶のおもてなしを体感していただくためです。アジアを紹介するうえで欠かせない存在であるお茶に、気軽に親しんでほしい。飲食店でお茶やコーヒーを飲んだり食事をしたりするのは、究極の体験ですから」

TEA BAR「聴景居」(写真提供:コンランショップ・ジャパン)
自主編集型店舗への挑戦は、社内の現状を知る機会にもなった。日本やアジアでものを見つけて背景を知り、仕入れて販売をすることに社内は慣れきっておらず、オープン当初は店頭に並ぶまでに時間がかかった商品もあったという。
中原氏「仕入れた商品の中でも、特に家具はお店に馴染むまで時間がかかります。売れている家具を仕入れても店舗空間や他の商品ともフィットしないこともあり、“売りこなれる”までには時間が必要なんです。代官山店がオープンして半年が過ぎ、ようやく最近、家具がお店に馴染んできたように感じます」
代官山店には、ザ・コンランショップでこれまで扱ってきたヨーロッパのデザイン性のある家具ではなく、素朴でシンプル、プレーンなアジアの家具を中心に並んでいる。このアジアらしい特徴感がある家具は、“売りこなれる”にはチャレンジングな対象だった。
中原氏「私たちは、お客さまがアジアや和のテイストをどれくらい家に入れられる環境なのかを読み取る必要があります。家具を求めているお客さまに、アジアで見つけた家具を、どのようにして受け入れていただくか。売りこなれるまでにかかる時間を考えながら、お店を作っています」
生活者として体験しなければ、伝えることはできない
商品だけでなく、新たなスタイルやしつらえを提案できるようになるために、中原氏が強調するのが「商品を見る目」を育てることの重要性だ。
家具や小物を見て、説明を聞き、購入に至る人がいる一方で、「他のショップやホテルなどに置かれていないと、安心できない」という人もいるという。
中原氏「他の店舗で取り扱っていたり、映画で使われていたり、有名人が愛用していたり、お客さまにとって商品との接点が多いと、『いい商品なのだ』と安心感につながります。これは購入の動機にもつながる要素です。一方で、代官山店のようにアジアの一点ものの家具が並んでいる店舗のものは、お客さまが自ら選び取ることになります」
顧客がものを選ぶのに必要な情報を伝えるために、店舗のスタッフたちの商品を見る目を育むことが、一層大切になる。中原氏は、「もっと届ける喜びを体感してほしいし、アジアで暮らす人としてアジアをもっと体験してほしい」と語る。

スタッフ自身が生活者として体験しなければ、顧客に本当に良いものを伝えることは難しい。その際に重要なのは「自分で購入して使ってみる」体験だという。
中原氏「仕入れや店舗準備をするスタッフを連れて台湾やタイを訪れました。実際に訪れてみて『台湾茶っておいしい』『この器で飲むのか』など、現地の文化に触れさまざまなことを感じ、発見していきます。
そうして気になるものを見つけて、自分のお金で買い、普段の生活の中で使ってみる。すると、生活を豊かにする方法が見えてくる。例えば茶器を買うことで、『お盆に合わせて使いたい』『こんなふうにお茶を出したい』と、茶器を使うシーンや視点が意識的に広がり、しつらえの提案などにつながっていきます」
誰かから与えられたものを売るのではなく、自分たちで選び普段の生活に取り入れてみることで、売るために何を伝えるべきなのかが見えてきたのだ。
店舗ごとに「キャラ」を立てる
中原氏はランドスケーププロダクツ時代から、店長のキャラクターを尊重して店舗運営をしてきた。「ヴィンテージが好き」「キッズのものを扱いたい」など、意識的に店長の興味を押し出す形で店づくりを行ってきたという。

ザ・コンランショップの場合は、キャラクターは「場所」にあわせて設定。その上で、それぞれの店舗づくりを進めてきた。
中原氏「新宿店は、占有面積が広くたくさんの顧客が集まる場所で、場所柄インテリアや家具のプロフェッショナルの方も多くいらっしゃってくださるので、そうした人々にも向けた提案も行っています。目利きが集まる代官山は、アジアにフォーカスした自主編集型店舗に。丸の内店は、東京駅に近く、地方からの入り口のような場所でいわば“導入編”、気軽に使える家具や小物を揃えています。伊勢丹新宿店は、デパートの中のデザインショップと位置づけているのが特徴で、デザイン性の高いアイテムを一点ずつきちんと見せています」
そして、麻布台ヒルズにオープンした東京店は、「総合的に一番東京らしいお店」を目指しているという。アジアに特化した代官山店の専門性を持たせた店づくりや、長野県御代田町で出店したポップアップストアでの、外部のさまざまな専門性を持ったショップとコラボレーションしてきた学びを生かし、ショップインショップの形式を導入した。「それぞれのジャンルの専門家に、直接商品を紹介してもらうことで、私たちでは伝えきれなかったストーリーをお客さまに伝えられるのでは」と、中原氏は狙いを語る。

ザ・コンランショップ 東京店(写真提供:コンランショップ・ジャパン、photo: Yuna Yagi)
中原氏「東京店は、店舗のキャラクターを見せるというより、いろいろなショップが集まった集合体としてのおもしろさを大切にしました。ショップインショップとして専門店が入り混じる、コミュニティストアのような感覚です」
東京店は「極上の普通」をテーマに、日々使うもののなかから楽しく上質なものを選び構成している。店内には、東京・浅草の料理道具店「釜浅商店」や、京都で観葉植物を扱う「cotoha」など、数々の専門店がショップインショップとして集結しさまざまなキャラクターが混在。日本では初のレストラン「Orby(オルビー)」を併設し「uguisu」「organ」の店主紺野氏をヘッドシェフとして迎え、まさに「東京」を象徴する店舗となった。
中原氏「東京店には『楽しく上質なものは何か』という視点で、いろいろなものが集まっています。これまでは、ザ・コンランショップの中だけで店舗作りをしてきましたが、ショップインショップとして外の専門店が入ることは、とても新鮮です。専門の方と組むことでお店に違う魅力が生まることを期待しています」

いま「ライフスタイル」を提案する店舗のあり方を考え直す
一つひとつの店舗での挑戦を通して、日本で店舗を展開していく上でのキャラクター性、ザ・コンランショップとしての新しいスタイルの確立を一歩ずつ進めてきた中原氏。今後もさまざまな展開を構想しているというが、中でも一つ重要なのが、2024年が、ザ・コンランショップが日本に上陸して30周年を迎える年だということ。
同年10月には、東京ステーションギャラリーで「テレンス・コンラン展(仮称)」の開催を予定している。
中原氏「デザイナーのテレンス・コンランは、『お店を通してデザインを伝えた人』です。ザ・コンランショップを作り上げ、世界中に大きな影響を与えました。イギリスでは彼は“Terence Conran: Making Modern Britain(イギリスをモダンにした男)”と紹介されているんです。世界中の人々の生活を変え、お店のスタイルも変えたという意味で、彼の行ってきたことは偉業だと感じています。
展覧会ではそんな人物がいたことを、きちんと伝えていきたいと思います。『デザイナーになる』『お店を開く』など、これから何かを始める人たちにとって、彼からもらえるヒントはたくさんあるのではないでしょうか。彼の古びない発想力や心臓を突く言葉を伝えることに、展覧会の意味があると信じています」
テレンス・コンランが何を始め、何を実現したのか。冒頭でも触れた「PLAIN」「SIMPLE」「USEFUL」という3つのコンセプトを振り返り、「ライフスタイル」を提案する店舗のあり方を再考すべきなのではないか。中原氏はそう締めくくった。
中原氏「代々続く企業は、『創業●代目』といいますよね。1代というのは約30年。2代目、3代目と、異なるキャラクターの人が受け継ぎ、積み重ねていきます。
ザ・コンランショップが日本で店舗を展開し始めた後、国内でもライフスタイルショップと呼ばれる店舗が増えていきました。ライフスタイルを提案する店舗が増え、彼が亡くなった今、これからどのように受け継いでいくか、考え直す時がきたのだと思います」
50年の歴史を受け継ぎながら、現代の日本のライフスタイルを踏まえた、新たなスタイルへと更新していく。代表就任から2年と経たない間に、新たな展開を次々と重ねていく中原氏による「ライフスタイル」の提案を再考する挑戦は、まだまだ始まったばかりだ。

取材/モリジュンヤ 執筆/鈴木ゆう子 編集/小池真幸 撮影/伊藤圭




